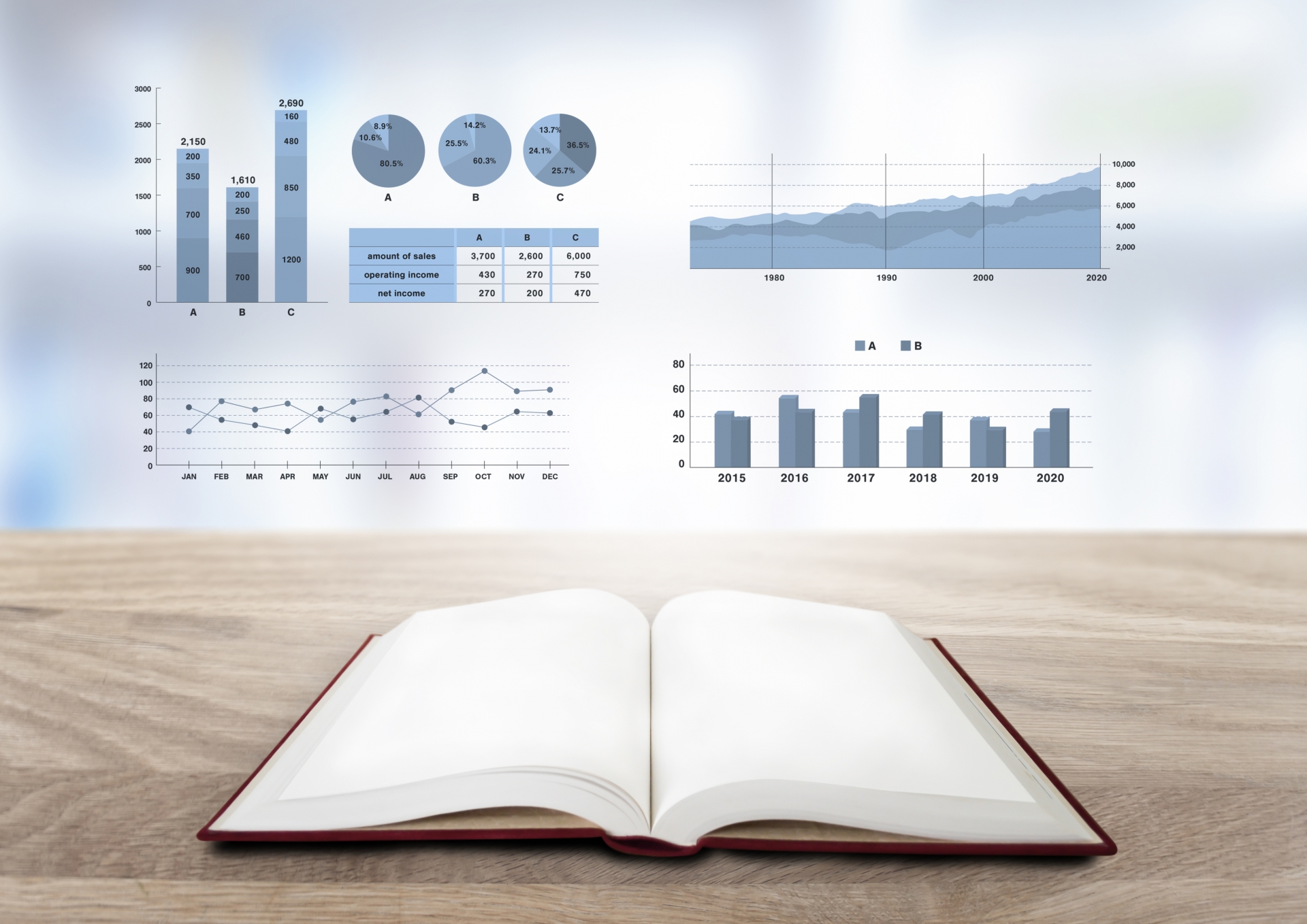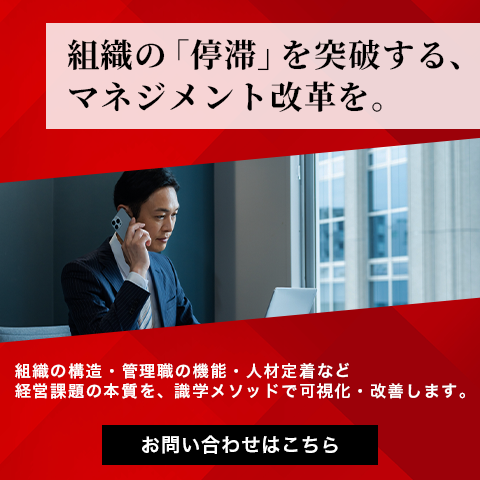0216.png)
「リプレイスって何?」
「どのような種類があるの?」
このように考えている方も多いのではないでしょうか。
この記事では、「リプレイスの基礎知識」について徹底解説していきます。リプレイスの基本的な進め方も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
評価制度に関する無料のお役立ち資料をご用意しております。
コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。
・「人事評価制度の極意3つ」13ページの無料資料はコチラ
・「その評価制度で、本当に大丈夫?」無料の漫画資料はコチラ
リプレイスとは?

まずは、リプレイスとは何か簡単に解説します。
■リプレイスの意味
リプレイスとは、英語で「交換する」「置き換える」等の意味を持つ言葉です。ビジネスやITの分野では、「既存のシステムの全体または一部を新しいものに交換する」という意味で使われます。
■リプレイスの目的
リプレイスの主な目的は、以下の3つです。
- システム老朽化への対応
- パフォーマンス劣化への対応
- セキュリティの向上
それぞれ簡単に紹介するので、頭に入れておきましょう。
●システム老朽化への対応
税法上、電子機器の耐用年数(減価償却期間)は、サーバーなどが5年、パソコンが4年、購入したアプリケーションソフトが5年と定められてます。そのため、約5年前後でハードウェアまたはソフトウェアのリプレイスが必要となります。
また、ハードウェアやソフトウェアには、メーカーのサポート期限も設定されており、通常はサポート期限終了の前にリプレイスを実施します。
古くなったハードウェアやソフトウェアについては、社内でメンテナンスできる人材も限られるため、早急にリプレイスを検討すると良いでしょう。
参考)
e-gov法令検索:減価償却資産の耐用年数等に関する省令
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=340M50000040015
国税庁:No.5461 ソフトウエアの取得価額と耐用年数
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5461.htm
●パフォーマンス劣化への対応
自社ビジネスが拡大するにつれて、取り扱うデータ量は増大します。古いシステムは機器の性能が乏しいため大量のデータを処理しきれず、動作が重くなったり固まったりするなどの不具合が起こります。
システムのパフォーマンスが悪くなると、自社内の従業員のみならず、取引先企業やエンドユーザーにも影響が及んでしまうかもしれません。
最新のハードウェアやソフトウェアへのリプレイスを定期的に行い、データ処理速度が十分担保できているかどうか、常に気を配りましょう。
●セキュリティの向上
古いハードウェアやソフトウェアには、セキュリティ面での懸念もあります。
メーカーサポートが終了している製品は、セキュリティパッチのアップデート等も行われないため、不正アクセスやマルウェア感染の標的になりやすくなります。重要情報の流出やマルウェア被害拡大など、重大なセキュリティインシデントは、企業イメージの低下を招きます。
セキュリティ対策を万全にするためにも、定期的にリプレイスを行い、最新のセキュリティパッチを適用させるようにしてください。
■マイグレーションとの違い
リプレイスとよく似た言葉に「マイグレーション」があります。
マイグレーションとは、英語で「移行する」「移転する」等の意味を持つ言葉です。ITの分野では、既存のシステムの全体または一部を、新しい環境に切り替えたり別の環境に移転したりする意味で使われます。
リプレイスは、既存のシステムや機器の一部を、新品または同等のものに入れ替えますが、基盤となるOSやプラットフォームは基本的に変更しません。
一方で、マイグレーションの場合は、基盤ごと新しいものに変更します。たとえば、自社で運用しているオンプレミス環境からクラウド環境へ移行するなど、システム構成がガラッと変わってしまうような入れ替えは、マイグレーションと呼ばれることが多いです。
こちらの記事もオススメ
【例文付き】5W1Hの意味とは?順番やビジネスでの使い方を解説
リプレイスの4つの種類

リプレイスには、主に以下の4つの種類が存在します。
- 一括移行方式
- 段階移行方式
- 並行移行方式
- パイロット方式
順に見ていきましょう。
■一括移行方式
システムを構成する全ての要素(ハードウェア、ソフトウェアなど)を一括で入れ替える方式です。
|
メリット |
・移行の手間やコストを最小限に抑えられる ・旧システムが抱えていた問題を一気に解決できる |
|
デメリット |
・システムを全面的に停止しなければならない ・複数の箇所で同時に不具合が起きるリスクが高く、根本原因の特定に時間がかかる |
■段階移行方式
システム移行をいくつかの段階に分け、部分ごとに新しいシステムに切り替えていく方式です。
|
メリット |
・システムを全面停止する必要がない(部分的な停止で済む) ・不具合が起きたときに原因を特定しやすい |
|
デメリット |
・新旧のシステムが混在することでどのような影響が生じるのか、事前に調査が必要 ・一括移行方式に比べて作業量や作業時間が増加する |
■並行移行方式
新旧システムを一定期間並行して運用し、新システムが機能するかどうかを検証しながら移行する方式です。
|
メリット |
・システムを停止せずに移行を進められる ・トラブル時には、旧システムに簡単に戻すことが可能 |
|
デメリット |
・2つのシステムが同時に稼働するため、コストや管理の負担が大きくなる |
■パイロット方式
影響範囲の小さい部署で新しいシステムを仮運用し、問題がない場合は全面的に移行する方式です。
|
メリット |
・テスト運用によって、移行の問題点を洗い出せる |
|
デメリット |
・手間がかかる ・テスト運用時には出なかった不具合が、本移行時に生じる可能性もある |
こちらの記事もオススメ
【自己顕示欲とは】自己顕示欲が強い部下との接し方について解説
リプレイスの基本的な進め方

この章では、「リプレイスの基本的な進め方」を紹介します。
- リプレイスの内容を決める
- リプレイスの計画を立てる
- 移行データの準備を進める
- リハーサルを行う
- リプレイスを実施する
ぜひ参考にしてください。
1.リプレイスの内容を決める
まずは、リプレイスの内容を決めなければなりません。現行システムの調査や分析を行い、リプレイスするハードウェアやソフトウェアの範囲を決め、優先順位付けを行います。現状のシステムの問題点や、新しいシステムへの要望などをまとめておきましょう。
2.リプレイスの計画を立てる
リプレイスの内容が決まったら、計画に落とし込みます。全体スケジュールのほか、移行方式、システム停止が必要な場合は停止期間、リハーサルやユーザー教育の期間などを具体的に盛り込み、ベンダーと共有してください。
3.移行データの準備を進める
続いて、移行データの準備を進めましょう。
リプレイス後のシステムでは、データフォーマットが変わるケースも少なくありません。仕様が変わることが想定される場合は、移行データ自体も調整する必要があります。
4.リハーサルを行う
一部のシステムを使用してリハーサルを行い、移行作業の手順を最終確認します。
システム停止が伴うようなリプレイスの場合、作業時間に大きな制約があるでしょう。「予定時間内に作業が完了するかどうか」をしっかりと確認してください。また、トラブルが起きた際の復旧手順なども入念にチェックしておきましょう。
5.リプレイスを実施する
リハーサルまで完了したら、いよいよリプレイスを実施します。
もちろん、想定外のトラブルが生じることもあるでしょう。ベンダーとのコミュニケーションを欠かさず、冷静に対処するようにしてください。
[識学の評価制度]評価制度作成にお悩みでは?是非チェックしてみてください。
→評価制度の基本!正しい作り方を徹底解説|NG事例も紹介
まとめ
「リプレイスの基礎知識」について分かりやすく解説しました。
ビジネスやITの分野におけるリプレイスとは、「既存のシステムの全体または一部を新しいものに交換する」ことを意味します。基本的には、以下のような目的で実施されます。
・システム老朽化への対応
・パフォーマンス劣化への対応
・セキュリティの向上
ぜひ当記事を参考にしながら、リプレイスについて理解を深めてください。
こちらの記事もオススメ↓
【勘違いしていませんか?】会社内における正しい風通しの良さとは
識学上席講師 大熊 憲二
2011年入社 ソフトバンク事業部に配属となり、史上最速の9ヵ月でマネージャーに昇進し、店舗拡大に貢献。
2014年モバイル事業部移動となり、業界全体が縮小傾向で低迷する中、200坪以上の超大型店等の新規出店に従事。
2016年に識学と出会い、識学に基づくマネジメントを徹底し、モバイル事業統括として史上初の年間目標完全達成を記録。
株式会社P-UP neo取締役常務執行役員兼識学上席講師として現在に至る。