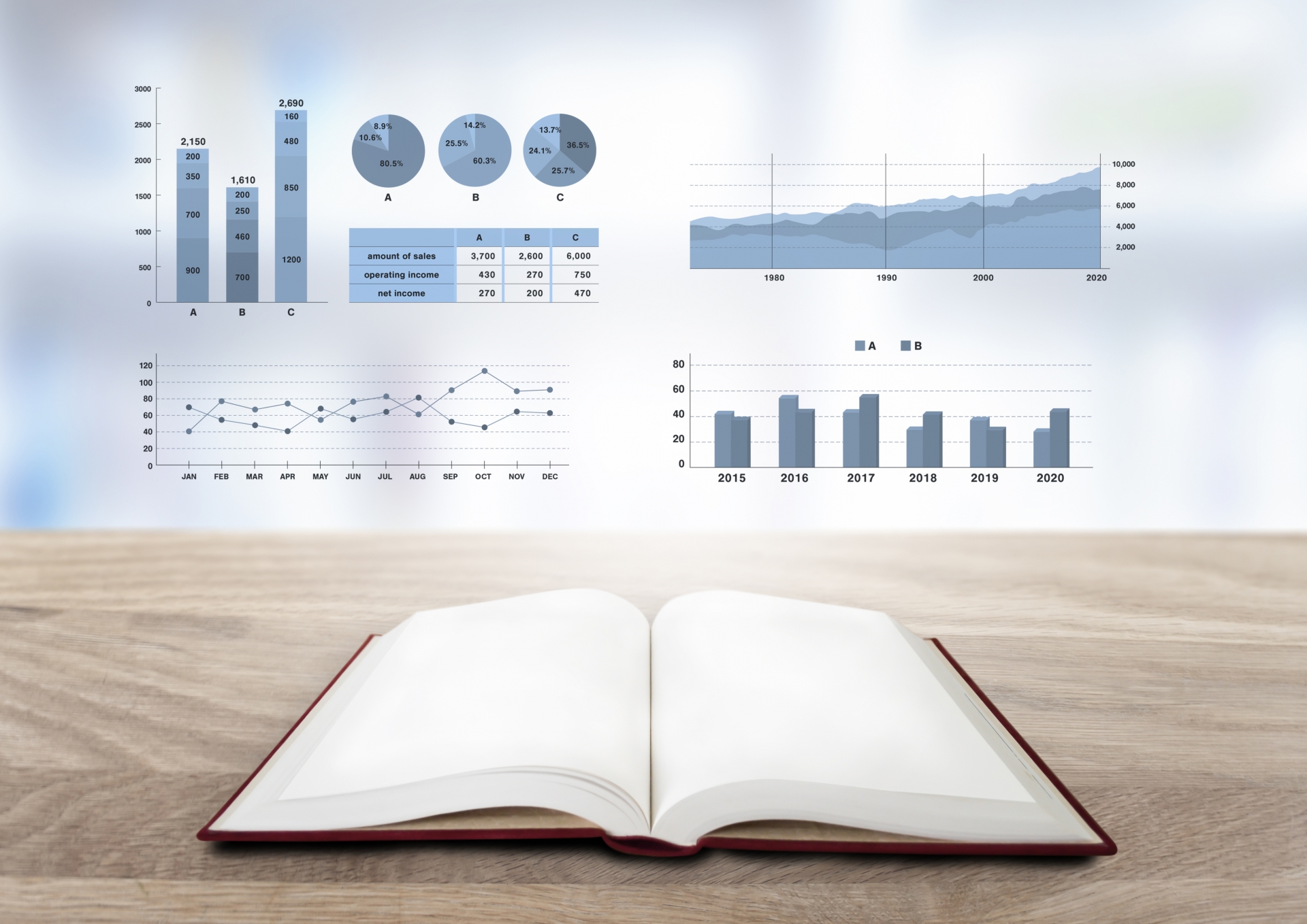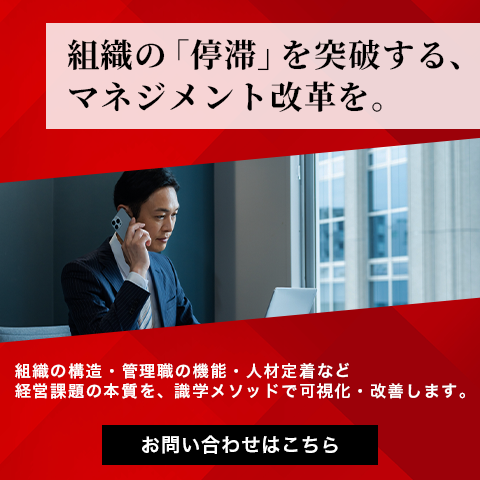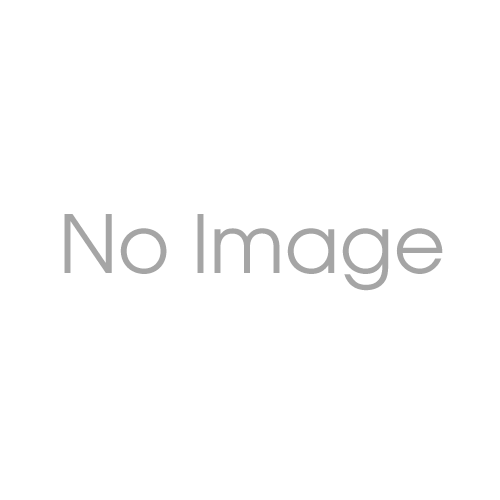
病院経営において、慢性的な赤字や職員の離職に頭を悩ませている経営者の方も多いのではないでしょうか?
外部環境の変化に対応しながら、医療の質を維持することは容易ではありません。
しかし、適切な改善策を実行すれば、組織力を高めながら財務体質を強化できます。
本記事では、人材マネジメントを軸とした組織改革から、財務改善や業務効率化まで、病院経営を立て直すための改善策を解説します。
ぜひ参考にしていただき、貴院の経営改善への第一歩を踏み出してください。
本気の組織改革なら
「識学 × P-UP neo」
病院経営の現状と直面する課題

少子高齢化や医療ニーズの変化を背景に、多くの病院が厳しい経営を迫られています。
長引く物価高や人件費の上昇は、病院経営を直接圧迫する大きな要因です。
また、深刻な医療従事者不足も、サービスの質を維持するうえで課題となっています。
とくに2024年度から始まった医師の働き方改革は、労務管理の複雑化を招きました。
こうした外部環境の変化に加え、地域内での競争も激化しています。このような複雑な課題に対応するため、従来のやり方を見直す視点が不可欠です。新たな経営改善策に取り組む重要性が高まっています。
参考資料:厚生労働省「労働経済動向調査(令和6年8月)の概況」
病院経営改善策の基本方針と方向性
山積する経営課題を前に、何から手をつければよいか悩むかもしれません。
しかし、場当たり的な改善策を講じても、持続的な効果は期待しにくいものです。
ここでは、基本方針を定めるうえで要となる3つの視点を紹介します。
- 地域医療における自院の役割を再定義する
- 診療機能の選択と集中で強みを作る
- 医療周辺事業で収益源を多角化する
それぞれ見ていきましょう。
地域医療における自院の役割を再定義する
自院の立ち位置を客観的に見つめ直すことは、経営改善の出発点です。
地域の人口動態や疾病構造、競合病院の動向などを分析することが大切です。
そのうえで、自院が地域から何を求められているのかを明確にします。
たとえば、急性期医療に特化するのか、あるいは回復期や慢性期医療で地域を支えるのかを判断します。
自院が担うべき役割を定めることで、経営資源をどこに集中すべきかが見えてくるでしょう。
地域にとってなくてはならない存在になることが、安定経営の基盤を築きます。
診療機能の選択と集中で強みを作る
すべての領域で高い評価を得るのは、現実的に困難です。
自院が持つ人材や設備といった資源を最大限に生かすため、診療機能の選択と集中を進めます。
これは、得意分野を伸ばして地域内での優位性を確立する戦略です。
たとえば、整形外科やリハビリテーションに強みがあれば、その分野への投資を強化します。
専門性を高めることで、手術件数の増加や専門スタッフの確保にもつながるでしょう。
強みが明確になれば、患者やほかの医療機関からの信頼も得やすくなります。
医療周辺事業で収益源を多角化する
診療報酬だけに依存する経営モデルは、制度改定の影響を受けやすく不安定です。
経営基盤を安定させるため、新たな収益源を確保する視点も肝心です。
自院の資源やノウハウを生かせる、医療周辺事業の展開を検討しましょう。
具体的には、健康診断や人間ドックの拡充、訪問看護や介護サービスの提供などが考えられます。
地域住民の健康を支えるという広い視野を持つことで、新たな事業機会が生まれるでしょう。
収益源の多角化は、経営の安定に直接貢献します。
人材マネジメント改革で組織力を高める
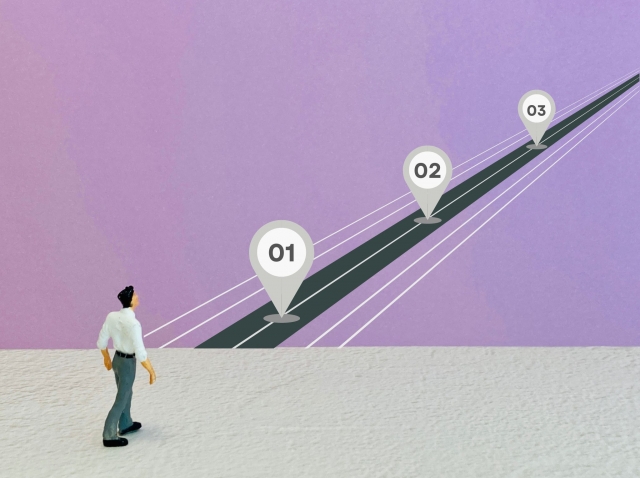
病院経営において、人件費は最大のコスト要因でありながら、医療の質を左右するもっとも重要な経営資源です。
単純な人件費削減ではなく、職員一人ひとりの能力を最大限に引き出し、組織全体の生産性を高めることが求められています。
ここでは、以下5つの施策を紹介します。
- 採用コスト削減につながる職場環境整備
- 多職種連携で業務負担を分散する仕組み
- 納得感のある評価制度で定着率を向上
- 医師の事務作業をコメディカルが担う体制
- 現場スタッフが改善提案できる風土作り
詳しく見ていきましょう。
採用コスト削減につながる職場環境整備
新たな人材を確保し続けるには、多大なコストがかかります。
もっとも効果的な採用コスト削減策は、今いる職員が辞めない職場を作ることです。
職員が長く働きたいと思える環境を整備しましょう。
たとえば、残業時間の削減や有給休暇の取得促進は、働きやすさに直結します。
また、院内保育所の設置や柔軟な勤務形態の導入も、職員の定着を後押しするものです。
魅力的な職場環境は、新たな人材を引きつける要因にもなります。
結果として、採用と定着の好循環が生まれます。
多職種連携で業務負担を分散する仕組み
特定の職種に業務が集中すると、一部の職員の負担が増大し、離職の原因となります。
多職種がそれぞれの専門性を生かして協力し合う、チーム医療の推進が欠かせません。
職種間の垣根を越えた情報共有の場を設け、互いの業務への理解を深めます。
たとえば、カンファレンスを定期的に開催し、患者情報を共有するのも有効な手段です。
業務が分散されれば、一人ひとりの負担が軽減され、組織全体の生産性向上にもつながるでしょう。
納得感のある評価制度で定着率を向上
職員が自身の働きや貢献を正当に評価されていないと感じると、仕事への意欲は低下します。
明確な基準に基づいた、公平で透明性の高い評価制度の構築が求められます。
評価基準を公開し、職員が何を目標にすればよいかを理解できるようにしましょう。
評価結果を伝える際は、一方的な通達ではなく丁寧な面談を行います。
自身の成長課題を認識し、前向きな行動につながる機会となるからです。
納得感のある評価は、職員のエンゲージメントを高め、定着率を向上させます。
医師の事務作業をコメディカルが担う体制
医師の業務の中には、医師でなくても実施可能な事務作業が多く含まれています。
具体的には、診断書の下書きや検査オーダーの代行入力、診療記録の作成補助などを医療クラークが担当する体制を構築します。
看護師についても、看護補助者へのタスクシフトを進めましょう。
ベッドメイキングや配膳、患者の移送などを看護補助者が担当することで、看護師は専門性の高い業務に集中できます。
タスクシフトを成功させるには、業務範囲の明確化と十分な研修が必要です。
コメディカルスタッフ のキャリアパスを整備し、モチベーションを維持することも有効です。
現場スタッフが改善提案できる風土作り
日々の業務の中にこそ、改善のヒントは隠されています。
しかし、トップダウンの指示だけでは、現場の小さな問題は見過ごされがちです。
現場のスタッフが「もっとこうすればよくなる」と感じたことを、気軽に提案できる仕組みを作りましょう。
たとえば、改善提案ボックスの設置や、優れた提案を表彰する制度が考えられます。
小さな提案でも積極的に採用し、実行することが大切です。
スタッフに当事者意識が芽生え、自律的に改善に取り組む組織文化が育ちます。
財務体質の改善と収益力の向上

病院経営の安定には、健全な財務体質が欠かせません。
ここでは、財務体質と収益力を向上させるための3つの視点を説明します。
- 材料の共同購入でスケールメリットを生かす
- 地域連携の強化で紹介患者を増やす
- 患者から選ばれるブランディング
これらの施策を組み合わせることで、より強固な経営体質を構築できます。
材料の共同購入でスケールメリットを生かす
医薬品や診療材料の購入費は、病院の支出の中で大きな割合を占めます。
このコストを削減する有効な手段が、ほかの医療機関との共同購入です。
単独で購入するよりも多くの量をまとめて発注することで、価格交渉を有利に進められます。
いわゆるスケールメリットを追求する考え方です。
地域の病院グループや医師会などで連携し、共同購入の仕組みを構築できないか検討しましょう。
個々の単価は小さくても、年間で見れば大きな経費削減効果が期待できます。
地域連携の強化で紹介患者を増やす
自院の機能を最大限に生かすためには、地域のほかの医療機関との連携が不可欠です。
とくに、近隣のクリニックや診療所との良好な関係構築は、紹介患者の増加に直結します。
自院の専門分野や特色を明確に伝え、どのような患者を紹介してほしいかを共有しましょう。
定期的に情報交換会を開催したり、診療情報提供書への返書を迅速かつ丁寧に行ったりすることも大切です。
信頼関係が深まることで、安定的・継続的な患者紹介につながります。
患者から選ばれるブランディング
同じような機能を持つ病院が地域に複数ある場合、患者は何を基準に選ぶのでしょうか。
決め手となるのが、その病院ならではの「価値」です。
自院の強みや理念を分かりやすく伝え、患者から選ばれるためのブランディング戦略を進めましょう。
たとえば「〇〇の分野ならこの病院」という専門性を打ち出すのも1つの手です。
また、親切なスタッフの対応や清潔な院内環境も、よい評判となって広がります。
地域における自院のブランド価値を高めることが、収益力の向上につながります。
業務効率化とサービス向上の両立
医療現場では職員の負担を軽減し、その分のエネルギーを患者サービスに向けるという発想が欠かせません。
ここでは、効率化とサービス向上を実現する3つの方法を掘り下げます。
- 電子カルテ導入で記録業務を効率化
- 待ち時間短縮で患者満足度を向上
- オンライン診療で受診機会を拡大
これらの取り組みは、職員と患者の双方にとって大きなメリットをもたらします。
電子カルテ導入で記録業務を効率化
紙カルテの運用は、情報の検索や共有に時間がかかり、保管場所も必要です。
電子カルテを導入することで、これらの課題を解決し、記録業務を大幅に効率化できます。
医師や看護師が記載した情報を、院内のどこからでもリアルタイムで確認可能です。
これにより、部署間の情報伝達がスムーズになり、指示の確認漏れなども防げます。
導入にはコストがかかりますが、長期的に見れば業務時間を短縮でき、患者との対話などに充てられます。
待ち時間短縮で患者満足度を向上
患者が病院に抱く不満の中で、もっとも多いのが「待ち時間の長さ」です。
この課題を解決することは、患者満足度の向上に直接つながります。
予約システムの導入や改善は、待ち時間短縮に効果的です。
患者は自分の都合に合わせて予約でき、病院側も来院患者数を予測しやすくなります。
受付から診察、会計までの流れを見直し、ボトルネックになっている工程を特定することも重要です。
スムーズな院内誘導を工夫するだけでも、患者が感じるストレスは軽減されます。
オンライン診療で受診機会を拡大
地理的な制約や身体的な理由で、通院が困難な患者も少なくありません。
オンライン診療を導入することで、こうした患者にも医療を提供する機会を広げられます。
スマホやパソコンを通じて、自宅から診察を受けられる仕組みです。
再診の患者や病状が安定している、慢性疾患の患者などがおもな対象となります。
病院にとっては、新たな患者層の獲得につながる可能性があります。
また、院内の混雑緩和にも貢献するため、ほかの患者の待ち時間短縮という効果も期待できるでしょう。
院内改革の限界を感じたら外部専門家の活用がおすすめ
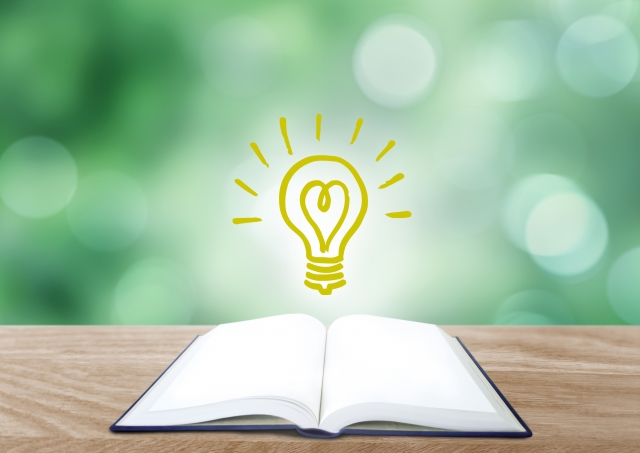
自院の努力だけで解決できる問題には、限界があるかもしれません。客観的な視点を持つ外部の専門家(コンサルタント)の力を借りることも、有効な選択肢の1つです。第三者の立場から課題を分析し、院内の人間では思いつかないような解決策を提示してくれるでしょう。
ここでは、外部専門家の活用を検討するうえで重要な2つのポイントを解説します。
- 内部での解決が困難な課題を見極める
- 信頼できるコンサルタントの選び方
専門家の力を上手に活用することが、改革を加速させるきっかけになります。
内部での解決が困難な課題を見極める
すべての課題に専門家が必要なわけではありません。
まずは院内で解決できることと、外部の知見が必要なこととを冷静に切り分けましょう。
たとえば、部署間の対立が根深い場合や、人事評価制度のような専門知識を要する仕組みを構築する場合は、外部の力が必要です。
経営陣が何度も改善を指示しても現場が変わらない場合も、専門家の介入が有効です。
自院の弱みや限界を正直に認めることが、適切な専門家活用への第一歩となります。
信頼できるコンサルタントの選び方
コンサルタントと一口にいっても、得意分野や実績はさまざまです。
自院の課題に合った、信頼できるパートナーを選ぶことが肝要です。
選ぶ際は、まず病院経営に関する深い知見と豊富な支援実績があるかを確認しましょう。
過去の改善事例を具体的に提示してもらうのが賢明です。
机上の空論を振りかざすのではなく、現場の職員と真摯に向き合ってくれる姿勢も大切なポイントです。
複数の候補者と面談し、もっとも信頼できると感じる相手を選んでください。
まとめ:病院経営改善のため専門家への相談で次の一歩を踏み出す
さまざまな改善策を検討しても管理職が機能せず、離職が絶えないといった課題が解決しない場合、その原因は根深い部分にあるのかもしれません。
意識構造に着目したマネジメント理論「識学」は、そうした組織課題への明確な答えを示します。
P-UP neoは識学の認定パートナーとして、自らも組織改革を成功させたノウハウに基づき、貴院への効果的な導入を支援します。
もし貴院の組織改革に行き詰まりを感じているなら、まずは識学の理論に触れてみませんか?
具体的な導入ノウハウが分かる資料のダウンロードや、無料でのご相談も承っております。次の一歩を踏み出すことで、組織の課題を解決する糸口が見つかるはずです。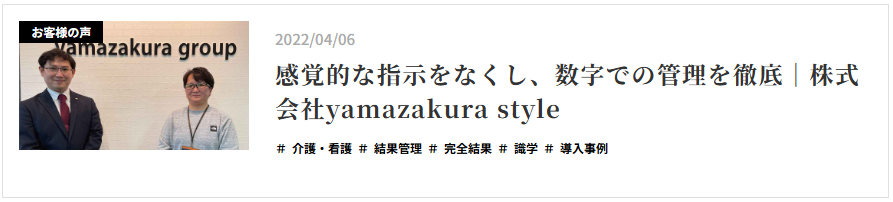
本気の組織改革なら この記事の監修者 有馬大悟 Arima Daigo 株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント 《資格》 識学認定コンサルタント 《プロフィール》 慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。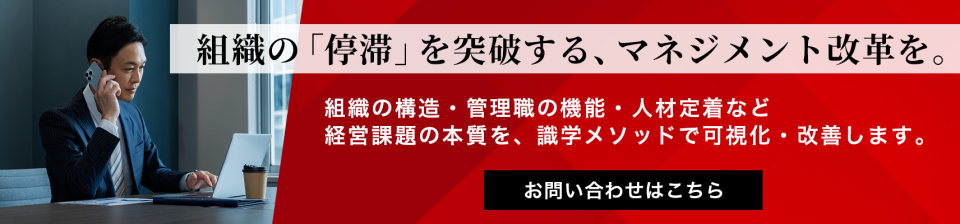
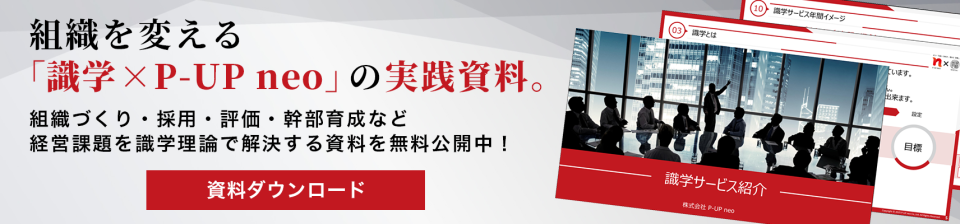
「識学 × P-UP neo」
社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。
他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。
非営利法人における初年度更新率=満足度は100%