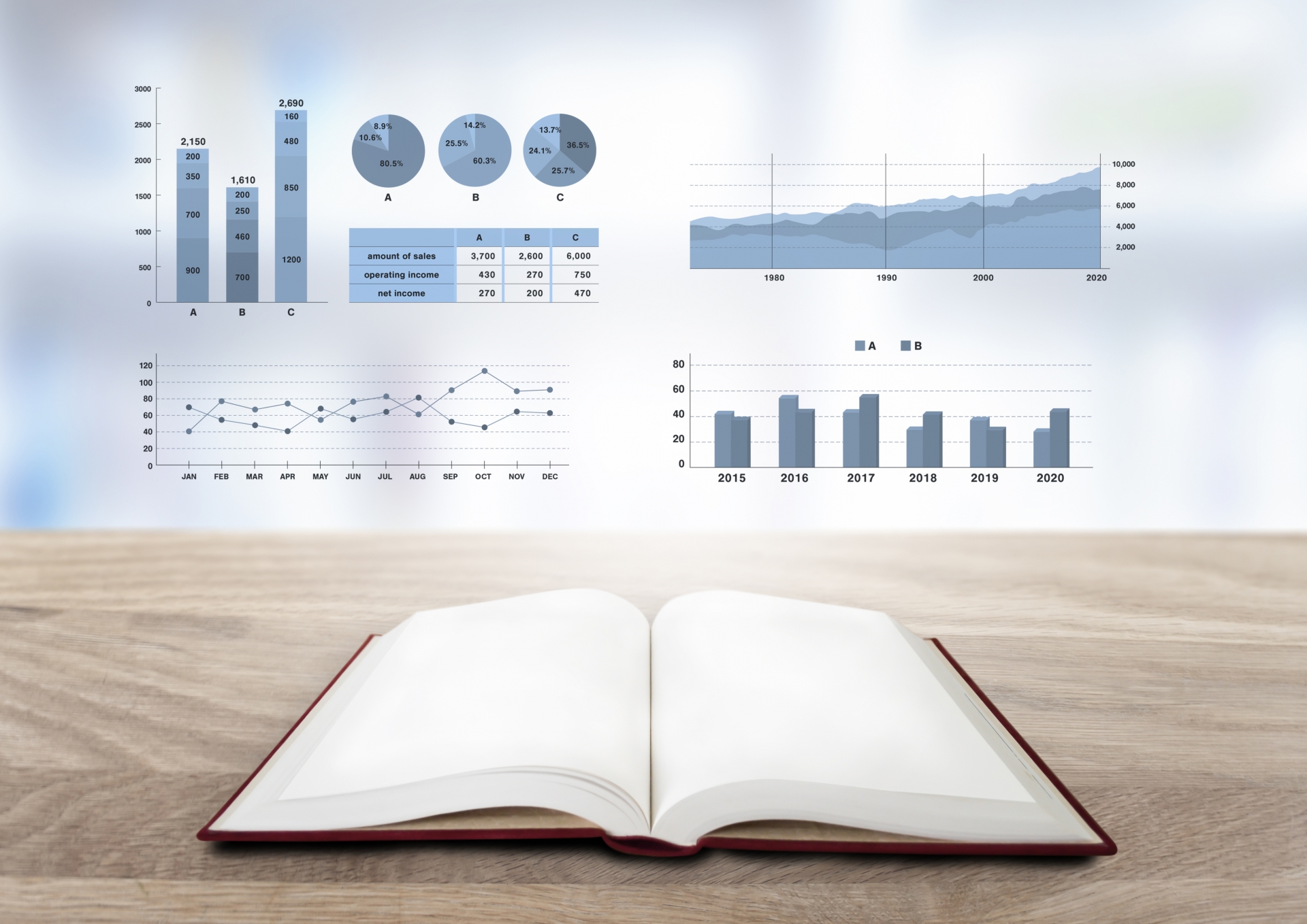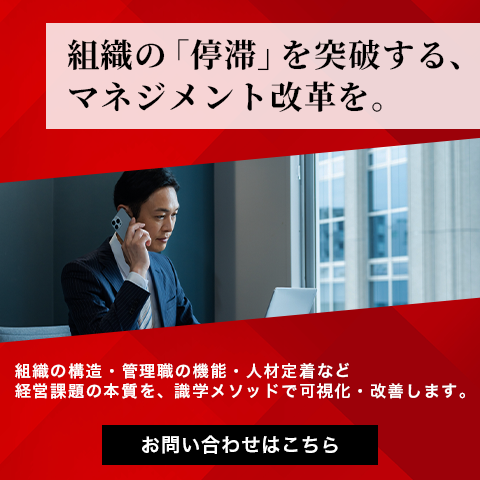.png)
「部下の言い訳が多い」
「言い訳をなくしたい」
このような悩みを多く持つ経営者や管理層の方が多くいるのではないでしょうか。
この記事では、言い訳の発生原因とそれを排除する方法を識学に沿って解説していきます。
評価制度に関する無料のお役立ち資料をご用意しております。
コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。
・「人事評価制度の極意3つ」13ページの無料資料はコチラ
・「その評価制度で、本当に大丈夫?」無料の漫画資料はコチラ
1. 言い訳とは?

まずは、言い訳とは何か、識学に沿って説明していきます。
・識学的に
辞書で調べると、辞書によって異なりますが、大項目としては「そうせざるをえなかった事情を説明して、了解を求めること」などこのような内容が出てくるかと思います。
物事の結果が出た時、芳しくいない結果の場合は、誰でも心の中に言い訳が発生します。言い訳が全く発生しないという方は、おそらくおられないのではないでしょうか。
しかし、言い訳を心の中に発生していたとしても、実際には外部に発しない人は存在します。その人は、言い訳は自分の内部では発生はしているが、ぐっとこらえて発生させないようにしている人が多いかと思います。
では、言い訳とは何のために、なぜ発生するのか。
それは、自分の芳しくない結果という事実を、言い訳によってごまかす、煙に巻く、責任を回避するためと考えます。
つまり、結果と言う事実をごまかす、極めて自己中心的なものと言えます。
ただし、注意は必要です。
「言い訳」は「課題」と紙一重の違いとなります。
例えば、「時間が足りなかった」とか、「人が足りなかった」とか、これは「言い訳」なのか、「課題」なのか。
内容が事実であれば、課題であり、対策が必要となる場合もあります。
これを見極める為には、部下にその「言い訳」に対する、次の行動変化を決めさせ、その行動によりもたらされる結果を上司と約束できれば、それは「言い訳」ではなく「課題」となります。
2. どのように言い訳を排除するのか
言い訳は誰にでも発生します。
だから、部下には言い訳があるなら出させればいいのです。
「言い訳なんてするな、けしからん!!」などという感情的なマネジメントでは、たしかに言い訳は減るかもしれませんが、上司に対して、「上司」という役割としての上下関係ではなく、「●●さん」という個人としての恐怖を与える形となり、更にマネジメント効率は悪化する可能性があります。
つまり、欲しい情報、必要な報告も上がってこなくなります。
ですので、言い訳があるなら出させればいいのです。
そして、上司が行うマネジメントは、その言い訳を淡々と排除する事です。
排除する方法としては、「で、どうするの?」と次の行動変化を確認します。
結果が芳しくないために言い訳が発生している為、結果に対して不足があります。
その不足を埋めるための行動変化を出させます。
部下から行動変化が出てきて、部下とその行動変化によりもたらされる次の結果を約束が出来れば、その「言い訳」は「課題」となります。
しかし、行動変化を出せない、出さない部下も存在します。
その場合は、その言い訳が【事実】かどうかを確認します。
事実でなければ、その確認だけで即排除できます。
事実であるなら、上司が「課題」に変えてあげることで、部下の言い訳を排除することが出来るということになります。
3. まとめ
マネジメントに正解はありません。
本コラムもあくまで識学理論では、という内容です。
しかし、識学理論は最短・最速で組織構築・組織成長するために、誰もが学ぶべき内容であると自負しております。
言い訳は誰でも発生するという前提で、上司の感情による恐怖で言い訳を出させない環境を作るという事では、結局、その他のマネジメントに支障をきたします。
言い訳が出てきたから感情的に対応するのではなく、事実に基づいて淡々と対応することで、「言い訳」が「課題」に変わり部下が成長できる環境も作れますし、事実以外の報告は無意味であるという組織、つまり組織として本来あるべき環境を作り上げられるのではないでしょうか。
こちらの記事もオススメ↓
【勘違いしていませんか?】会社内における正しい風通しの良さとは
識学講師 畔上 十吉
大学卒業後、ドイツのワインメーカーに就職、セクション別トップセールスとなる。飲食業界に転職、大手外食企業で本社課長職、全国の赤字店舗再建チームに所属し担当全店舗黒字化、同部署にて流行語大賞獲得、その後同社営業部長職として全国歴任。別会社に転職、ラーメン業態60店舗の事業部長を経験する。その後も転職し、馬肉専門外食企業の営業本部長として勤務、馬肉焼肉業態を開発、都内6店舗展開。さらに別会社にて唐揚げブランドの事業部長として、コロナ禍にて過去最高売上・最高利益記録。
自身の経験を積めば積むほど、自分の中にこれまでの経歴にマネジメント根拠がないことを痛感、識学に出会い、感銘を受け、自分の求める物であることを認識、識学講師を目指し、現在に至る。