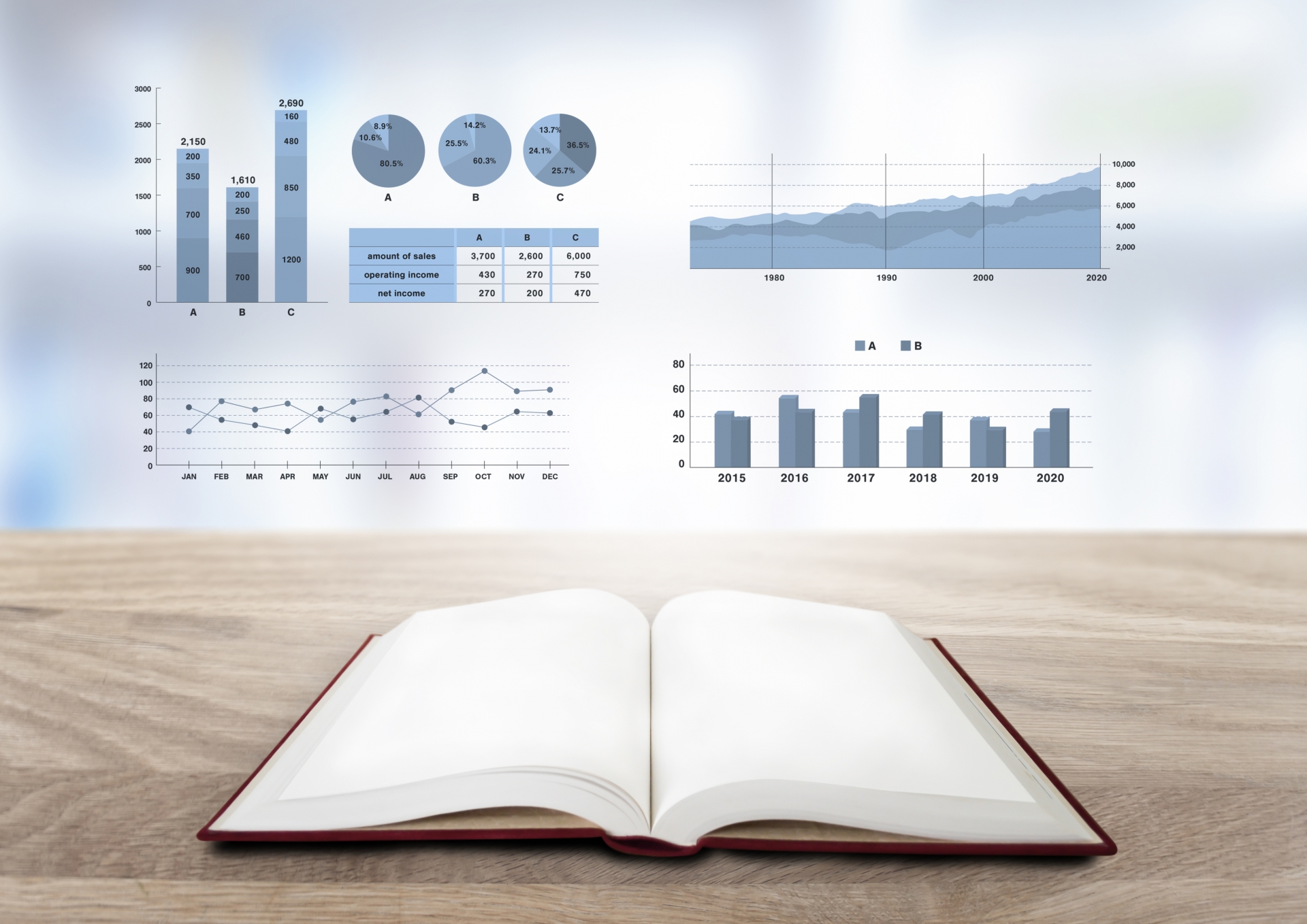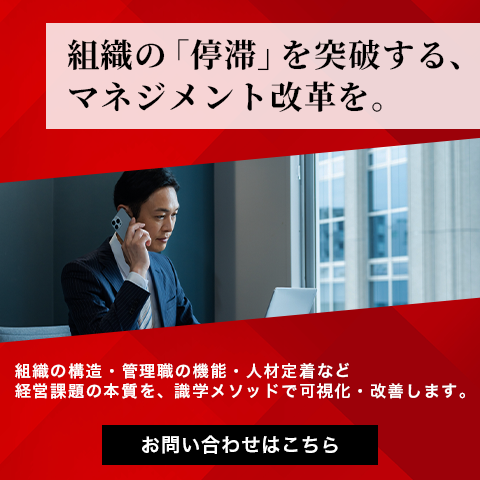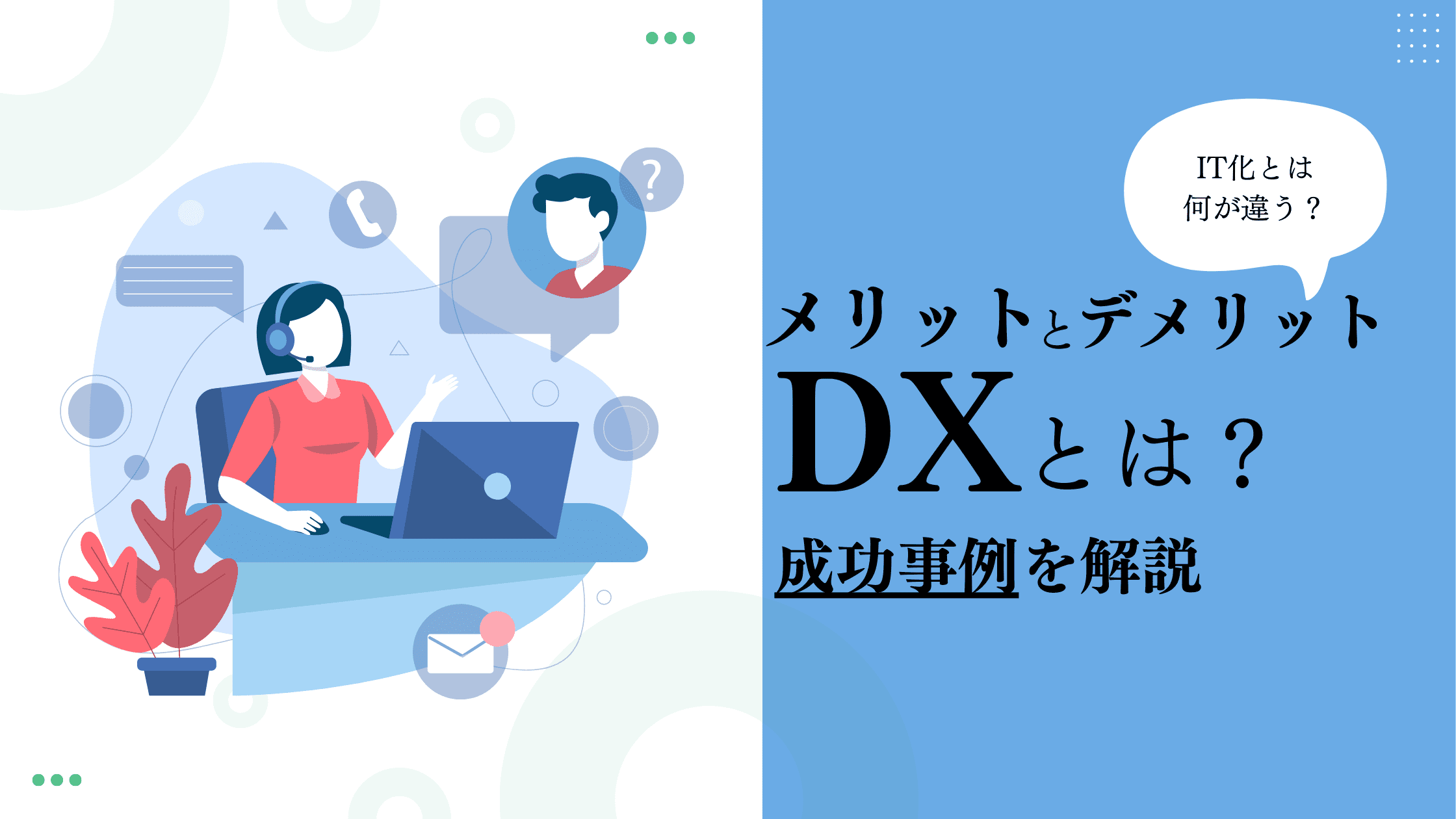
評価制度に関する無料のお役立ち資料をご用意しております。
コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。
・「人事評価制度の極意3つ」13ページの無料資料はコチラ
・「その評価制度で、本当に大丈夫?」無料の漫画資料はコチラ
DXとは
DXとは、「Digital Transformation(デジタルトランスフォーメーション)」の略です。Transformationは、日本語で「変化」という意味で、DX化は、デジタル技術を用いてビジネスや暮らしを変化させていくことです。
DXが初めて提唱されたのは、2004年でスウェーデンのウメオ大学教授のエリック・ストルターマン氏によって提唱されました。
DX化とIT化の違い
DX化と混同しやすい言葉に「IT化」があります。ITとは、「Information Technology」の略で、日本語で「情報技術」呼ばれます。これまでアナログで進めていたことをインターネットなどのデジタル技術に変えていく技術のことです。DX化はITなどのデジタル技術を用いてビジネスや暮らしを変化させていくのが目的のため、DX化とIT化には、目的と手段といった違いがあります。IT化の中にDX化があるといったイメージを持つと良いでしょう。
■DX化が注目された背景
では、なぜDX化は注目を集め、必要とされているのでしょうか。本項目では、DX化が注目された背景を解説していきます。
・2025年の壁
2025年の壁とは、経済産業省によって発表された日本の将来に対する喚起です。2018年に経済産業省が発表したDXレポートには、「日本のあらゆる産業において、今後DX化を進めなかった場合、2025年以降、最大12兆円/年(現在の約3倍)の経済損失を被る可能性がある」と記載されています。この発表には、多くの企業が驚き、様々な業界でDX化を進める動きが加速しました。
・労働人口の減少
日本の総人口は、2008年をピークに減少しており、2048年には1億人を割るといった予測があります。それに伴い労働人口も減少し、2060年には1人の労働者を1.3人の労働者で支える超高齢社会が予測されています。
このように日本の労働人口が減少しており、今後も減少し続けると予測されている中では、DX化のようにデジタル技術を用いて業務の効率化や自動化が必要とされます。
DX化のメリット
近年多くの企業がDX化を推進していますが、DX化は企業にどのようなメリットを与えてくれるのでしょうか。本項目では、DX化のメリットについて解説していきます。
■メリット1:業務効率化や生産性の向上に繋がる
DX化の最大のメリットは、業務効率化や生産背の向上が期待できる点です。ルーティーンワークをRPAによって自動化し、手間のかかる分析作業を人間に代わってAIに任せることができます。
また、DXに取り組むことで、ビジネスプロセス全体の見直しもできます。それにより、業務の無駄を見つけ出し、より効率的な業務内容へと変更が可能です。
このように、DXの導入によって、会社の部署・部門関係なく企業全体の業務効率や生産性の向上が期待できます。
■メリット2:新商品・新サービスの開発がしやすくなる
DX化の推進の一つとして、SNSやWebサイトから顧客情報を取得する場合があります。
取得した情報を分析して経営に活かすことで、新製品や新サービスの開発に繋がるケースがあります。
このようにDX化の推進は、新製品や新サービスを開発しやすいと言ったメリットがあります
■メリット3:BCP対策に有効的
BCPとは、「Business Continuity Plan」の略で、日本語で「事業継続計画」と呼ばれます。
地震や津波、火災などの災害が発生した場合でも、システムへの被害を最小限に抑え、事業を継続するために事前に対策しておくことを意味します。
DX化を推進しておくと、予期せぬ災害が起きた際でも、柔軟に対応が可能です。最近だと、2020年に発生した新型コロナウイルスの影響で、多くの企業がダメージを受けました。しかし、DX化によってデジタル化を進めていた企業は、そうでない企業と比較して、テレワークを行いやすく、感染症による業務への影響を最小限にとどめることができました。このように、DX化の推進は、BCP対策に有効的です。
識学の評価制度についてはこちらの記事に詳しく記載しておりますので、是非チェックしてみてください。
→評価制度の基本!正しい作り方を徹底解説|NG事例も紹介
DX化のデメリット
では、DX化を企業に推進することによるデメリットはないのでしょうか。本項目は、DX化のデメリットを解説します。
■デメリット1:初期費用やランニングコストがかかる
DX化には、ITツールやシステムが必要不可欠です。そして、これらのツールやシステムは高額な場合がほとんどです。そのため、DX化に取り組む企業は、巨額の初期費用が掛かる場合があります。
また、システムは定期的にメンテナンスする必要があり、それにはエンジニアなどの専門家を雇う必要があります。さらに、サーバーやシステムのレンタル代など、DX化にはランニングコストもかかります。
このように、DX化には、初期費用やランニングコストがかかるケースがあるため、自社に予算があるか、DX化にいくら予算を投資できるかを確認しましょう。
■デメリット2:技術者の確保が難しい
DX化の推進における課題としてよく上がるのが技術者の人材不足です。
技術者の確保には、中途採用として社員を雇う方法と若手社員を教育して育成する方法の2種類があります。中途社員は、雇う費用が高く、雇ったとしても即戦力にならない場合もあります。そのため、若手社員の育成は必須と言えるでしょう。育成には時間とコストがかかるため、焦らずじっくりと取り組む姿勢が大切です。
■デメリット3:短期間では効果が出ない
DX化には、これをやれば必ず成果が得られるという成功法は存在しません。そのため、自社にとって、最適でない戦略を取ってしまうと効果が表れるまでに長期間かかる場合があります。
これからDX化に取り組む企業は、短期間で成果を出そうとせずに、試行錯誤を繰り返しながら進めていく心構えが重要となります。
DX化の成功事例
DX化により業績を伸ばした企業は具体的にどのようなDX化を行ったのでしょうか。本項目では、DX化の成功事例として、2社ご紹介します。
■成功事例1:ユニクロ
アパレルの大手企業ファーストリテイリングのユニクロは、RFIDを活用し、業務改善を行いました。RFIDとは、「Radio Frequency IDentification」の略称で、無線通信技術を活用し、同時に複数の情報の読み取れる技術です。ユニクロは、RFIDをレジに導入することで、お客様の「レジ待ち」の時間短縮に成功しました。これにより、店舗の回転率が上がるだけでなく、レジの店員の削減にもなるため、従業員コストの削減にも繋がりました。
■成功事例2:日本郵便
日本郵便は、人材不足を補うためにドローンを活用した配送に取り組みました。2018年にドローンを使用したに配達を試験的に開始し、2020年には、ドローンを使用した個人宅の配送によって、配送時間が従来の約半分に短縮できるといった結果を示しました。日本郵便だけでなく、今後ますますドローンなどのロボット技術は活躍するでしょう。
まとめ
本記事では、DX化について解説しました。本記事内でも解説した通り、少子高齢化が加速している日本では、DX化によって業務を効率化、自動化できているか今後企業が生き残れるかの鍵となります。DX化を検討している方は、早めに取り組むことをオススメします。
識学では、生産性の高い組織運営に必要なノウハウを発信しています。DX化についてお悩みの方は、プロの専門家に相談するのも良いでしょう。
株式会社P-UP neo コラム制作部
株式会社P-UP neo内にある、コンテンツを企画・制作する編集部です。 マネジメント業務の助けになる記事を続々制作中です。