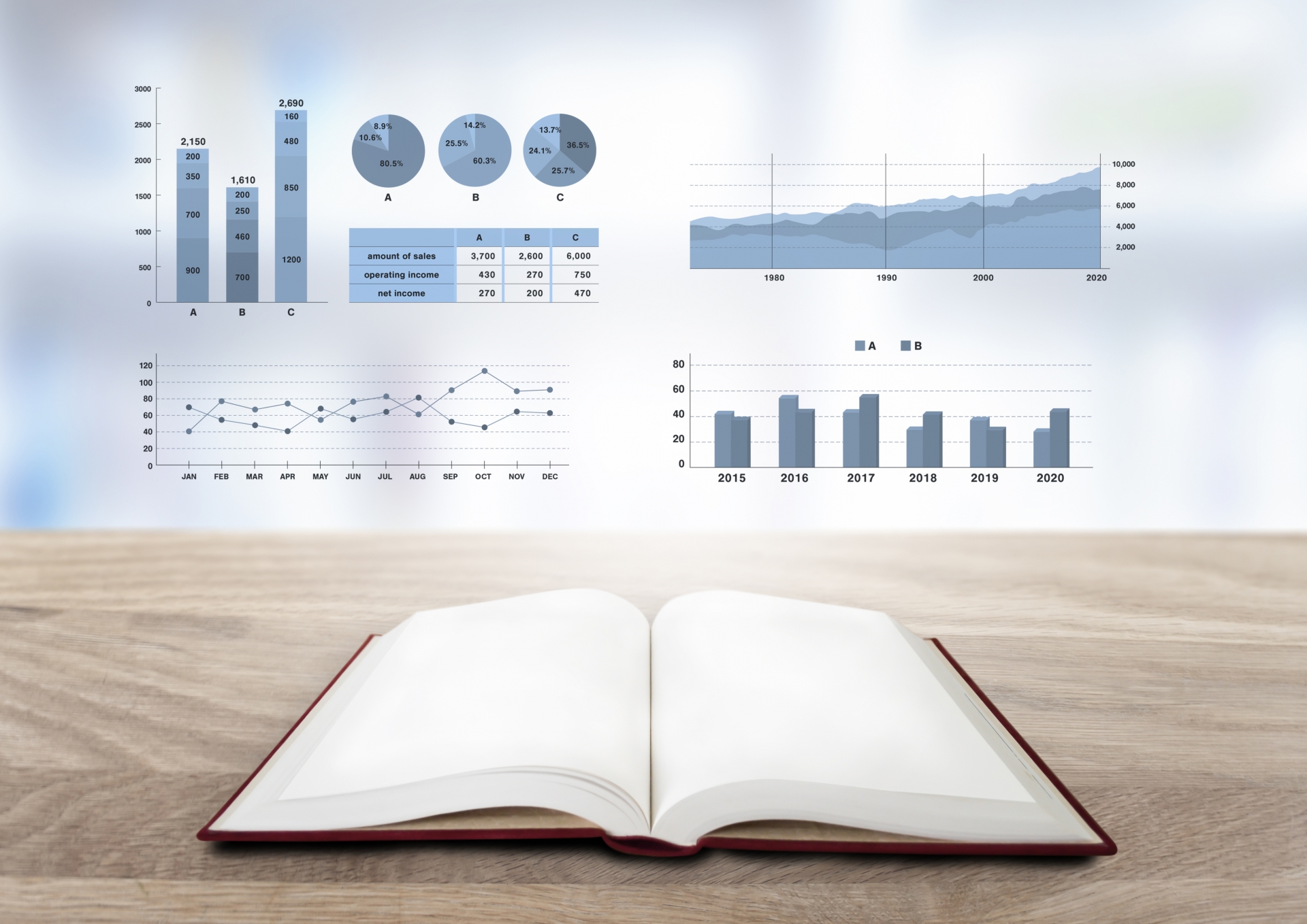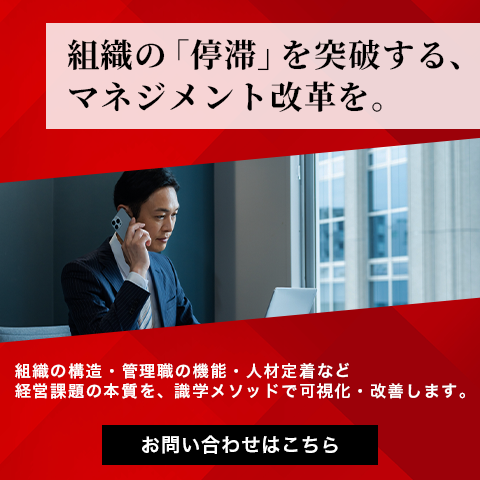みなさん、「環境アセスメント」という言葉をご存じでしょうか。最近よく耳にするようになった言葉です。令和2年4月には再生可能エネルギー事業である太陽電池発電所の設置事業が法対象事業として追加されたことや、地球温暖化が問題視されていることから「環境アセスメント」はますます注目を浴びています。実際にどのような事を行うのでしょうか?詳しく解説していますので是非ご覧ください。
評価制度に関する無料のお役立ち資料をご用意しております。
コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。
・「人事評価制度の極意3つ」13ページの無料資料はコチラ
・「その評価制度で、本当に大丈夫?」無料の漫画資料はコチラ
環境アセスメントとは
環境アセスメント(環境影響評価)とは、大規模な開発事業などを実施する際にその事業が環境に与える影響がないか調査・予測・評価を行い、住民や地方公共団体などの意見を聞くとともに専門的立場からその内容を審査し、事業の実施において適正な環境配慮がなされるようにするための制度です。省略して、「環境アセス」と呼ぶことも多くあります。
交通の便をよくするために道路や空路をつくったり、水を利用するためにダムをつくったり、生活に必要な電気を得るために発電所をつくる。これらは私たち人間が豊かに生きていく上では必要不可欠なものです。しかし、だからと言って環境に大きな悪影響を及ぼして良いということはありません。
事業の構想をした後、「安全性」「必要性」「採算性」などいろいろな観点から環境配慮においての検討を行います。
また、この環境アセスメントは事業を開始する事業者自らが行います。これは事業を開始する事業者自身が責任をもって環境への影響を配慮するべきであるためです。
環境アセスメントの実施後は、得られた結果を事業内容に反映させることで、今後開始する事業によって起こる可能性のある環境影響を未然に防ぐことが出来ます。
また、この環境アセスメントを行うことは、「環境影響評価法(環境アセスメント法)」という国の法律で定められています。もともとは1969年(昭和44年)にアメリカにおいて「国家環境政策法(NEPA)」が世界で初めて制度化されたことで導入が進んできました。日本においては1972年(昭和47年)に公共事業での環境アセスメントが導入されました。その後統一的なルールを設け、地方公共団体においても条例の制定が進められたことにより、1997年(平成9年)6月に現在の「環境影響評価法」が成立しました。
対象となる事業
- 道路
- 河川:ダム、放水路、湖沼開発
- 鉄道:新幹線鉄道、鉄道、軌道
- 飛行場(空港)
- 発電所:水力発電所、火力発電所、地熱発電所、原子力発電所、太陽電池発電所、風力発電所
- 廃棄物最終処分場
- 埋め立て、干拓
- 土地区画整理事業
- 新住宅市街地開発事業
- 工業団地造成事業
- 新都市基盤整備事業
- 流通業務団地造成事業
- 宅地の情勢の事業
以上の13事業が対象となっています。
また、必ず環境アセスメントを行う事業である「第1種事業」と、環境アセスメントが必要かどうかを個別に判断する「第2種事業」があります。この2つは事業の規模や種類によって異なります。
また、これらのうち
①免許等が必要な事業
②補助金・交付金等が交付される事業
③独立行政法人が行う事業
④国が行う事業
以上の4つが対象となります。
環境アセスメントでの調査内容
環境アセスメントにて調査する内容は以下の項目から、地域特性や事業特性に応じてどの項目を調査・予測・評価するのかを検討します。また、必要に応じて記載していない項目についても調査の対象となる場合があります。
<環境の自然的構成要素の良好な状態の保持>
・大気環境
・水環境
・土壌環境、その他の環境
<生物の多様性の確保及び自然環境の体系的保全>
・植物
・動物
・生態系
<人と自然との豊かなふれあい>
・景観
・触れ合い活動の場
<環境への負荷>
・廃棄物等
・温室効果ガス等
<一般環境中の放射性物質>
・放射線の量
環境アセスメント実施の内容
地域特性や事業特性に応じてどの項目を実施するかを決定した後は実際に調査・予測・評価を行います。
調査…予測・評価をするために必要な地域の環境情報を収集するための調査を行います。(既存の資料を集める、実際に現地に行って測定や観察を行う)
予測…事業を実施した結果、環境がどのように変化するのかを予測します。(各種の予測式に基づいて計算する方法、景観等ではモンタージュ写真の作成等の方法)
評価…事業を行った場合の環境への影響について検討します。(実行可能な最大限の対策が取られているか、環境保全に関する基準、目標等を達成しているか)
環境アセスメントの手続き

■配慮書の手続き
配慮書…事業への早期段階における環境配慮を可能にするため、第1種事業を実施しようと擦る者が事業の位置・規模等の検討段階において、環境保全のために適正な配慮をしなければならない事項について検討を行い、その結果をまとめた図書
配慮書作成の際には、①事業の位置②規模、に関する複数案の検討を行います。また、対象事業の実施が想定される地域の生活環境、自然環境などに与える影響について、その地域に住んでいる住民の方々や専門家、地方公共団体などの意見を取り入れるよう努める事とされています。
また、第2種事業を実施する者に関してはこれら一連の手続きを任意で実施できます。
■準備書の手続き
準備書…調査・予測・評価・環境保全対策の検討の結果を記載、環境の保全に関する事業者自らの考えを取りまとめたもの
調査・予測・評価が終わると事業者はこの「準備書」を作成し、都道府県知事、市町村長に送付します。そして準備書を作成したことを、地方公共団阿知の庁舎。事業部の事務所やウェブサイトなどで1か月間縦覧し、だれでも見られるような状態にします。そうすることで、一般の方々から意見が届くようになります。また、準備書は量が多く、内容も専門的であるため、内容についての説明会を開催します。
■評価書の手続き
準備書に対して、都道府県知事や一般の方々からの意見の内容について事業者は必要に応じて準備書の内容の見直しを行います。そして「環境影響評価書」作成します。作成された評価書は、事業所の免許等を行う者等、及び環境大臣に送付されます。環境大臣は免許等を行う者等を通して環境保全の見地からの意見を述べ、事業の免許等を行う者等はその意見を踏まえ、事業者に意見を述べます。事業者は意見の内容を検討したのち、見直しを行ったうえで最終的な評価書の確定を行います。また、評価書の確定後は準備書と同じく、地方公共団体の庁舎、事業者の事業所やウェブサイトなどで1か月間縦覧をします。
■報告書の手続き
報告書…事業者は
①工事中に実施した事後調査
②それにより判明した環境状況に応じる環境保全対策
③重要な環境に対して行う効果の不確実な環境保全対策の状況、
について工事終了後にまとめ、報告、公表を行います。これを報告書といいます。
評価書の手続きが終了し、実際に工事に着手した後でも、環境の状態を把握するために様々な調査は継続します。
このような調査を事後調査といいます。この事後調査は行う事業が環境への影響の重大性が大きいほど必要性も大きくなります。
事業者は事後調査を行う必要性についての判断も評価書に記載を行います。
環境アセスメント調査員に依頼できる!

前述にもある通り、環境アセスメントの実施は事業を開始する事業者本人が基本的に行いますが「環境アセスメント調査員」に依頼をすることも可能です。
環境アセスメント調査員は環境調査会社に勤務し、地域開発を計画している自治体や建設会社からの依頼で環境アセスメントの調査を行います。調査の結果、環境への影響が甚大であると判断した場合、建設設計の修正案を提案します。また、建設終了後に調査を行うこともあります。
まとめ
いかがでしたか?本記事では環境アセスメントの手続きや対象事業について解説をしていきました。環境アセスメントは現在の環境を守っていくために必要不可欠なものです。環境省のサイトにはより詳しい情報が記載してありますので、興味のある方は是非ご覧になってみてくださいね。
株式会社P-UP neo コラム制作部
株式会社P-UP neo内にある、コンテンツを企画・制作する編集部です。 マネジメント業務の助けになる記事を続々制作中です。