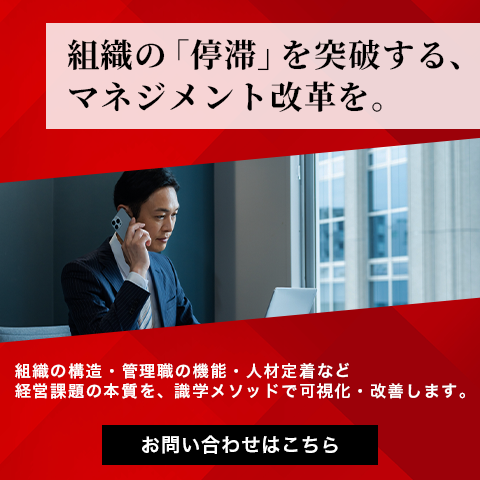世の中の会社の多くは複数の部門や部署があり、各々の視点から会社が掲げる一つの目標に向かって働きます。営業部、人事部、総務部、財務部、マーケティング部など、様々な部門がありますね。
業務スタイルや分野の違う部門が存在するということは、自ずと業務量や成果も部門ごとに多少差があると思います。代表例として、営業部と研究開発部を比較した場合、一般的に営業部には数や金額で示すノルマがあります。対して研究開発部は、このようなノルマがないことが多いでしょう。その代わり研究するテーマや題材があり、それを達成するという目標があります。
ではこのように部門ごとに目標や業務内容が異なる場合、各部門をどのように評価して成果報酬を与えるべきでしょうか。今回は、異なる部門が存在する会社での評価方法のポイントを解説していきます。
評価制度に関する無料のお役立ち資料をご用意しております。
コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。
・「人事評価制度の極意3つ」の無料資料はコチラ
・「その評価制度で、本当に大丈夫?」無料の漫画資料はコチラ
部門ごとに差をつける
複数の部門を持つ会社の場合、部門ごとに仕事内容が異なれば目標や成果の度合いも異なります。このような場合、社員への評価はどのように行うのが適しているでしょうか。
それは、部門ごとに異なる評価方法で評価や給料報酬を与えることです。
給料報酬とは「どれだけ利益貢献できたか」の対価を表すものですが、より多くの利益貢献したものがより多くの給料や報酬を受け取ることができます。これを、利益貢献していないものにも同様の程度の給料報酬を与えることは会社にとって不利益な行動につながります。つまり、社員一人一人の利益貢献度に応じて、給料報酬額を変更すべきなのです。
評価の場合も同様に、利益貢献度に応じて変化させるべきです。例えば、営業部と研究開発部を比較した場合、会社の利益に直接的な利益を生むのは営業部です。この二つの部門の一か月の利益貢献度がお互い150%であった場合、一見、営業部も研究開発部も同じだけの対価を示すことが妥当と思われがちですが、直接利益を生む機会の多い営業部の方が、同じ利益貢献度であってもその数値の価値がより高くなります。このことから、営業部へより高い評価を与えることが妥当と言えます。
部門ごとに利益貢献度の会社に与える数値的価値が違います。これに対して部門ごとに格差をつけなければいけません。
社員から不満が出た場合は
部門ごとに格差をつけることで、自ずと部門同士で差があることは社員も知ることとなります。そうすると「〇〇部は羨ましい」や「なぜ達成率80%の〇〇部の方が報酬が高いのか」というように、不平・不満を言う社員が現れることがあります。
このような場合は、「実際に〇〇部に行ったらどれだけの利益貢献ができるのか」ということを聞いてみてください。不平・不満の多くは、一時的な感情によるものであり、事実や根拠に沿っていない場合があります。もし同じだけの利益貢献を行うことができる場合は部署異動等で組織の生産性を最大化できる配置を考え直し、そうでない場合は聞く耳を持たないことが賢明でしょう。

決算賞与にも差をつける
多くの会社では、決算賞与制度を設けていると思います。決算賞与とは、企業がその年度の業績に応じて支給する、臨時の賞与ですが、多くの場合、平等に分配して報酬を与えます。つまり、部門ごとに賞与の金額が異なるわけでなく、社員の役職やランクによって変わる場合が多いです。
このような場合「利益貢献度の高い部門に所属しているのに、役職が与えられていない社員は相当の報酬を受け取ることができない」や、逆に「利益貢献度が低い部門に所属していても、課長だから多くの報酬を受け取ることができる」といったように、より多くの利益貢献をした物へ相当の報酬を満遍なく与えることが難しくなります。決算賞与制度を設けることは良いのですが、決算賞与の分配においても、利益貢献度に対する評価に基づいて変更することが重要になります。
まとめ
人事評価制度において、社員個人の目標達成度と利益貢献により変化する個人評価と、所属する部門が持つ目標の達成度に応じて変化する相対評価を組み合わせて評価することが重要です。同じように、どれだけ利益貢献できたかを対価で表す報酬や利益貢献度に応じて変わる評価制度も、個人の実績のみならず、部門ごとに差をつける評価方法が最適です。ぜひ異なる部門が存在する会社の評価制度構築に活用してみてください。
評価制度に関する資料をご用意しております!
識学上席講師 大熊 憲二
2011年入社 ソフトバンク事業部に配属となり、史上最速の9ヵ月でマネージャーに昇進し、店舗拡大に貢献。
2014年モバイル事業部移動となり、業界全体が縮小傾向で低迷する中、200坪以上の超大型店等の新規出店に従事。
2016年に識学と出会い、識学に基づくマネジメントを徹底し、モバイル事業統括として史上初の年間目標完全達成を記録。
株式会社P-UP neo取締役常務執行役員兼識学上席講師として現在に至る。