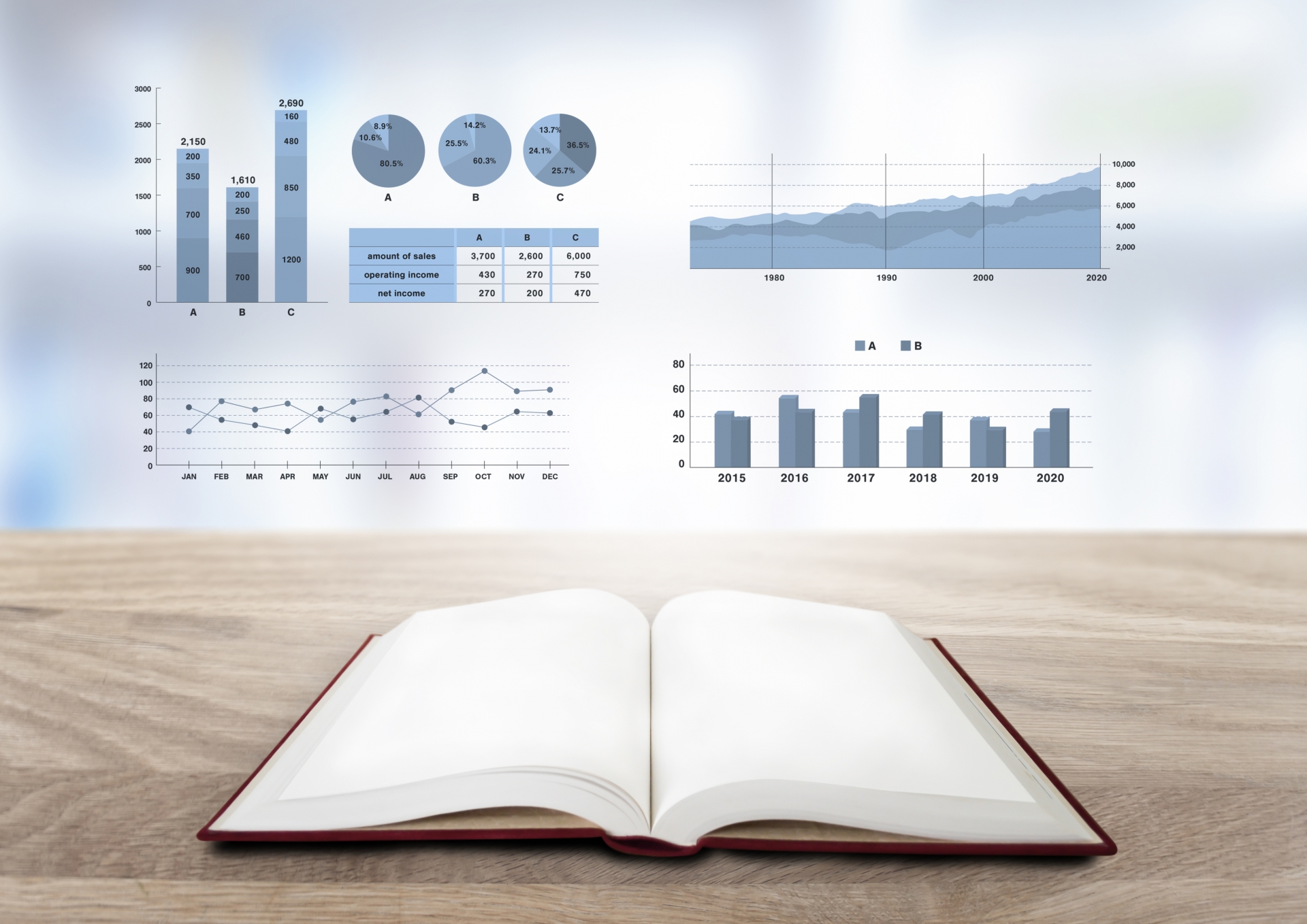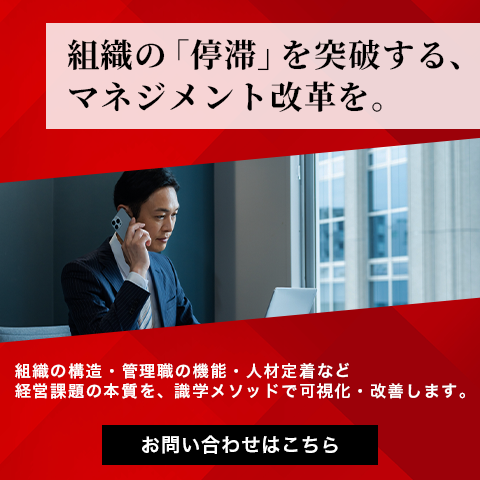どんな会社であっても、自社に必要な人材を育成することは不可欠です。そこでまず必要になるのが評価制度です。人材育成のための適切な評価制度設計は重要です。
そこでこの記事では、適切な評価制度設計の方法や流れなどについてまとめて解説します。
目次
評価制度に関する無料のお役立ち資料をご用意しております。
コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。
・「人事評価制度の極意3つ」の無料資料はコチラ
・「その評価制度で、本当に大丈夫?」無料の漫画資料はコチラ
人材育成のための人事評価制度設計の重要性
人材育成のためには、適切な評価制度の設計を行うことが必要です。ここでは、評価制度設計の重要性について解説します。
適正に評価されるとモチベーションになる
社員を適切に評価することは、社員のモチベーション管理を行ううえで重要です。会社に対して貢献したり成果を上げたりしている社員に対し、プラスの評価を行うことで、社員の動機づけにつながります。逆に、パフォーマンスが悪い場合には何が悪かったのか指摘することで、努力の方向性がわかり、適切なモチベーションが維持されます。
会社として欲しい人材像を示せる
きちんと評価制度を設計することで、会社が求めている人材像を示せます。例えば、自社で必要なスキルを評価する制度などを盛り込むことで、そのスキル獲得に向けて会社の人材を促すことができます。英語力やパソコンスキルなど、会社として必要なスキルを評価することで、人材育成につなげている会社は多数あります。
管理職にも人材育成のモチベーションを持たせられる
一般的に管理職は、仕事のマネジメントに追われています。そのため、きちんと評価制度の中で、人材育成に関する評価を行うよう設計することは、部下の育成に対するモチベーションを高めるうえでも必要不可欠です。そのようなことがないように、評価制度の中で人材育成について評価する旨盛り込まなければなりません。
人材育成のための評価制度の種類・方法
人材育成のための評価制度にはさまざまな種類・方法があります。評価制度設計の方法を解説します。
目標管理制度(MBO)
目標管理制度(MBO)とは、現在も多くの会社で採用されている人事評価制度です。期初にその期間の業績目標やスキル獲得などの目標を立て、期末に上司がその目標達成度合いを評価します。社員それぞれが達成度合いを自己評価するケースもあります。
コンピテンシー評価
コンピテンシー評価とは、業績の向上につながるような社員の行動特性を評価する制度です。業績の達成度合いなどではなく、行動特性を評価する点に特徴があります。会社ごとに達成したい成果が異なる以上、評価するコンピテンシーもさまざまです。
職務評価
職務評価とは、それぞれの職務ごとに評価する度合いを決め、それをもとに評価する制度です。例えば、会社の売上に直接的に貢献する度合いの高い営業職は、高めの貢献度で評価し、あまり売上に関係ない事務職などは、低めの貢献度で評価する、などの評価基準が挙げられます。
360度評価
360度評価とは、直属の上司が部下を評価するだけではなく、同僚や部下など、社内にいるあらゆる人から評価を受けるタイプの人事評価制度です。普段関わりのある人を中心に評価を受けますが、直接的な関わりがあまりないメンバーからも評価を受けるケースもあります。
パフォーマンスディベロップメント
パフォーマンスディベロップメントとは、それぞれの社員が出したパフォーマンスについて、上司が頻繁にフィードバック・評価する人事評価制度です。頻繁にフィードバックを行うため、部下が間違った方向に行かないようマネジメントしやすいことがメリットです。また、改善のサイクルが早く、スピード感を持って成長を促せます。
ノーレイティング
ノーレイティングとは、社員一人ひとりにランクをつけることなく、目標に対する達成度合いや、日頃の勤務態度などについて評価する人事評価制度です。ランクづけをしないため、導入・運用が容易ではないというデメリットがあります。相対的な評価ではなく、絶対評価であることもポイントです。
人材育成のための評価制度導入の流れ
人材育成のための評価制度を導入するには適切な手順があります。人材育成のための評価制度の導入手順を解説します。
評価方法を決める
人事評価制度を導入する際には、まず評価制度を採用します。それぞれの評価制度にメリット・デメリットがありますが、自社に合った評価制度を選びましょう。また、評価制度設計の際には、重要度が高い職務を優先的に評価する設計が必要です。例えば、直接的に売上に貢献する営業職や、プロダクトの質を左右するエンジニアなどを優先的に評価しましょう。
評価基準・評価者を決める
導入する人事評価制度が決まったら、次に評価基準を設定します。評価基準は厳密に数値に則ったものにしましょう。「これくらいの売上を達成したら、これだけ評価する」などと厳密に決めていきます。また、部下を評価する評価者は直属の上司にしましょう。組織構造が明確でない場合には、評価のために組織構造に曖昧さがないよう設計し直す必要があります。
評価制度を発表・運用を開始する
最後に、評価制度導入のアナウンスをしましょう。評価制度を変更することをアナウンスすることで、社員に新しい制度に対応するための準備を促します。評価制度を変更すれば、社員も評価されるために行動を変えます。制度変更のための準備期間を十分に設けるとよいでしょう。

人材育成のための評価制度実施の流れ
以下では、人材育成のための評価制度を実施する流れについて解説します。
期初面談
期初にはまず、その期間で達成するべき目標を社員それぞれが設定します。そして、それぞれが設定した目的が適切かどうか、上司が確認し、その段階でフィードバックしましょう。不適切な目標を設定してしまっては、人材育成にはつながりません。目標はあくまで数値化した定量的なものにします。
期中面談
期中には、部下が目標に対してどの程度進捗しているのか、フィードバックする面談を設けましょう。週次のミーティングでの管理を行い、それ以外は部下に自走させることが大切です。
期末面談
期末には必ず上司と部下で、目標達成ができたかどうかの面談の機会を作りましょう。このとき、上司が評価するのはあくまで目標達成できたかどうかという点です。目標が達成できていなかったのであれば、どのように目標達成すべきだったか、上司は部下に考えさせるとよいでしょう。
評価
定量的な目標設定をしているため、その目標を達成できていたかどうかを見て評価を決定します。
人材育成のための評価制度におけるKPI設定の重要性
人材育成のために評価制度設計をするうえで、KPI設定は非常に重要です。ここでは、KPI設定の重要性について解説します。
評価がしやすくなる
適切なKPIを設定しておくことで、社員それぞれもKPI達成のための目標設定がしやすくなります。数値化された明確な目標設定ができれば、期末の評価もしやすくなります。
会社側が育成したいスキルを示しやすい
KPIを設定することで、会社側が社員に求めるスキルやコンピテンシーが明確になります。求めるスキルが明確になれば、社員もそのスキル獲得に向けて行動しやすくなるでしょう。
人材育成のための評価制度設計における、KPI設定の例
人材育成のための評価制度設計において、KPI設定は重要です。KPI設定の具体例を紹介します。
売上やコスト削減など、業務に直結する成績
人材育成のための評価制度設計のKPIにおいて、一番わかりやすいのは、売上に直結する数字を設定するパターンです。「売上1億円達成」、「テレアポ件数1日100件」など、売上につながる数字を設定するとよいでしょう。
スキルや資格
スキルや資格の取得もKPIとして設定しておきましょう。「今期中に簿記2級を取得する」など、具体的なスケジュールについても設定するとより効果的です。
人材育成のための評価制度設計のポイント
人材育成のための評価制度設計を行うにあたって、いくつかポイントがあります。人材育成のための評価制度設計のポイントについて解説します。
育成したい人材像に沿った制度を選択する
自社が育成したい人材像によって、適切な人事評価制度は異なります。そのため、最適な人事評価制度を選ぶことは非常に重要です。
例えば、営業職が多い会社であれば、数値目標を達成できたかどうかを厳格に見る評価制度にするとよいでしょう。また、エンジニアが中心の会社であれば、スキル獲得についての評価の比重を高める必要があります。
このように、自社に最適な評価制度は異なります。どのような職種が自社にとって重要なのかを考慮し、最適な評価制度を選択してください。
運用しやすい制度を選択する
自社に合った評価制度を採用したとしても、適切に運用できなければ意味がありません。そのため、導入後にも自社で運用しやすい評価制度を設定するとよいでしょう。
定期的に評価制度自体を見直す
自社に最適な評価制度を導入したと思っていても、運用をしていく中でその評価制度が適切でなくなってくる可能性もあります。会社の成長フェーズなどによっても最適な評価は変わります。そのため、定期的に自社の人事評価制度を見直すことが重要です。
まとめ
自社に最適な人材を育てるためには、評価制度設計は非常に重要です。さらに評価を定量的な目標で評価することもポイントです。さまざまな評価制度があるため、自社にあった制度を採り入れ、人材育成につなげましょう。
評価制度設計について具体的な方法がわからない方には、人材マネジメント理論「識学」の導入をおすすめします。弊社「株式会社P-UP neo」は、社内に「識学」を実際に導入し、成果を上げています。自社への導入経験をベースに「識学」導入のコンサルティングをするため、具体的なサポートが可能です。以下のリンクから、ぜひ資料をダウンロードしてみてください。
評価制度に関する資料をご用意しております!
識学認定講師 日暮 裕規
2005年に明治大学商学部を卒業後、関東で50店舗以上を運営しているアミューズメント会社に入社。
最年少で管理職となり、60名を超えるスタッフのマネジメントを8年間従事、その後人事総務にて新卒採用・研修に携わる。2014年に上場企業(広告会社)に転職。
営業職で入社し、2年でトップセールスを受賞。
設立二人目8年ぶりの飛び級で支社長に昇格。
これまでの率先垂範、部下のモチベーションを重視したスタイルに限界を感じていた時期に識学に出会う。同じ悩みを持つ管理職や経営者の役に立ちたいと思い、株式会社P-UP neoに転職。識学認定講師として現在に至る。