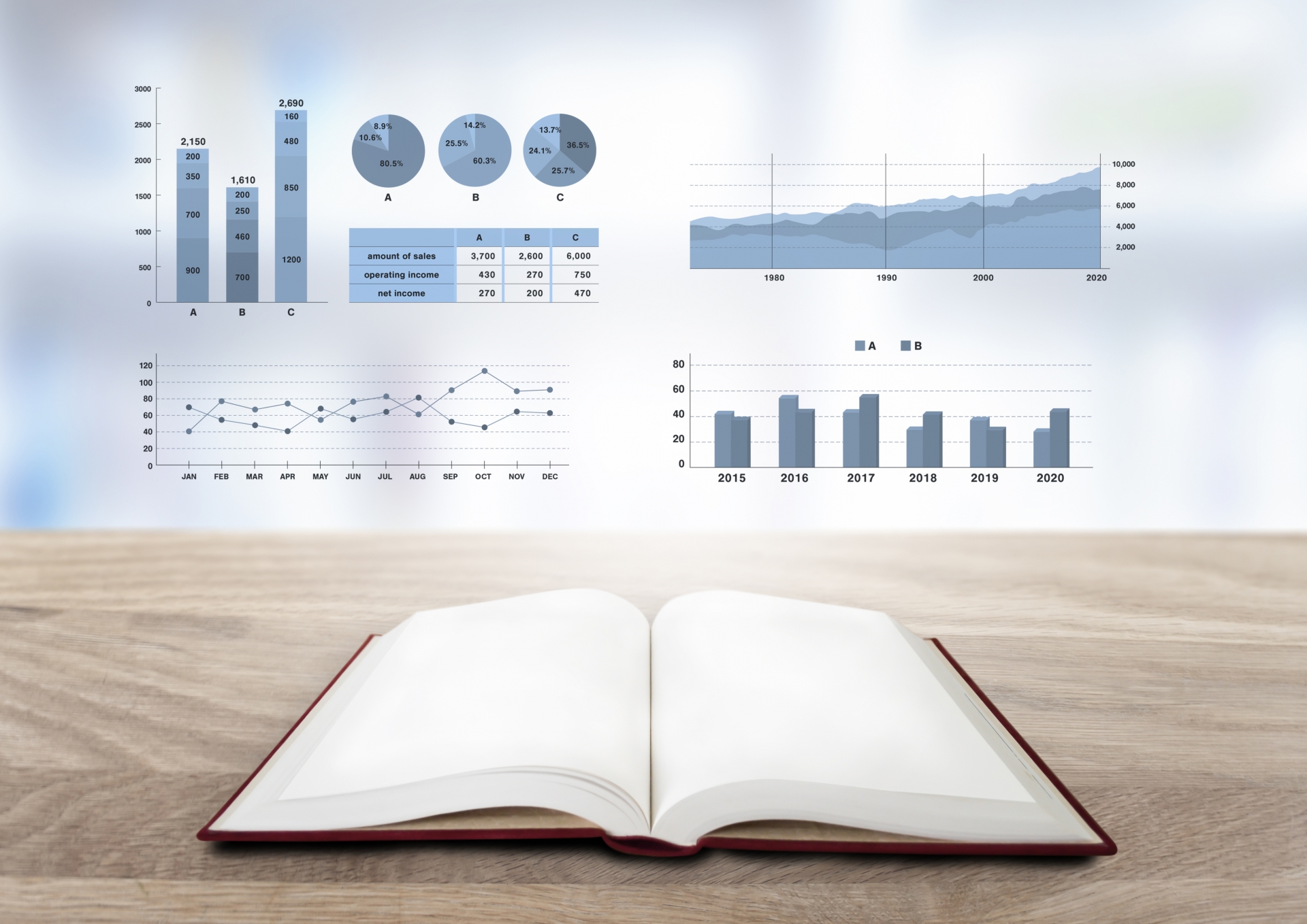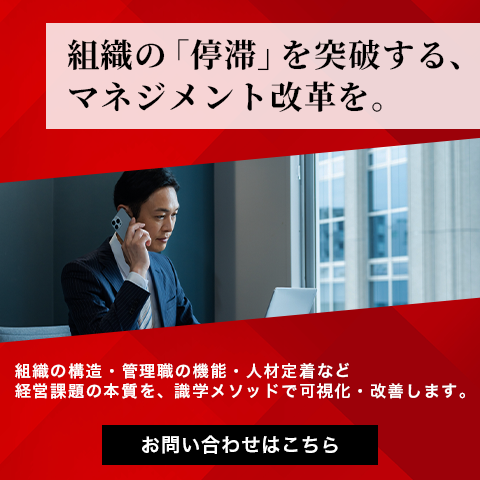評価制度とは、従業員の能力や実績を評価する人事制度のひとつです。昇給や昇進などの処遇を決める基準にもなり、従業員の満足度や業績の向上にもつながるため、自社にとって最適な評価制度を導入することが重要になります。
この記事では、評価制度がないリスクや評価制度を導入するメリット、導入や改善時に注意したいポイントなどについて解説します。評価制度の導入や見直しを検討しているなら、ぜひ参考にしてください。
評価制度に関する無料のお役立ち資料をご用意しております。
コラム記事と併せてこちらもご覧くださいませ。
・「人事評価制度の極意3つ」の無料資料はコチラ
・「その評価制度で、本当に大丈夫?」無料の漫画資料はコチラ
なぜ評価制度がない会社が多いのか
最近は、評価制度を導入していない、あるいはあえて無くしてしまう会社も増えています。なぜ評価制度を設けていない会社が多いのか、その理由を解説します。
評価制度とは
評価制度とは、従業員の能力や働きぶり、会社への貢献度などを評価して、昇進や昇格などの処遇を決める人事制度のひとつです。一般的に評価制度は、等級ごとに必要な役割を提示する等級制度や、従業員の給与や賞与などを決める報酬制度と連動して使われることが多くなっています。
評価が高まれば給料アップなどにもつながるため、従業員のモチベーションや能力の向上、生産性、業績アップに役立てられます。
評価制度がない会社が多い理由
評価制度を設けていない会社が多い理由として、以下が挙げられます。
評価制度に不満がある従業員の流出
理由のひとつが、透明性や公平性を感じられない従業員が会社を辞めてしまうといった流出を防ぐためです。不透明な評価基準だったり、評価者によって評価にばらつきがあったりすると、納得がいかない従業員が増えていきます。不満を抱えて辞められると、会社の悪評も拡散しかねません。
訴訟の恐れがあるため
一般的に評価制度は、給与や昇進・昇格などの処遇と連動しています。自分の評価に納得できない従業員がいれば、会社に訴訟を起こす可能性もあるかもしれません。こうしたリスクを避けることも、導入しない理由のひとつです。
評価制度は不完全であるため
評価制度により従業員同士に差がつくこともあるため、全ての従業員が納得できる制度を制定するのはとても難しいことです。また、時代によって価値観や求められる能力が変化するため、その全てに対応できる制度もあり得ません。不完全な評価制度はマイナス面も大きく、そもそも設定しない会社が増えているのです。
評価制度策定が簡単ではないため
評価制度を作るにしても、何を基準にするのか、会社の方針に合った評価制度はどう作るのか、どの部署が主導するのかなど、その策定は非常に困難な作業です。
また、評価基準だけではなく、評価方法や評価のタイミング、評価者など、運用方法で決めなくてはならないことも多岐にわたります。定期的な更新も必要となるでしょう。対応する人材や時間などが不足している会社であれば、導入自体が難しいこともあります。
作るだけではなくその後の管理・運用も容易ではなく、リソースが必要となることも、評価制度を導入しない会社が多い理由として挙げられます。
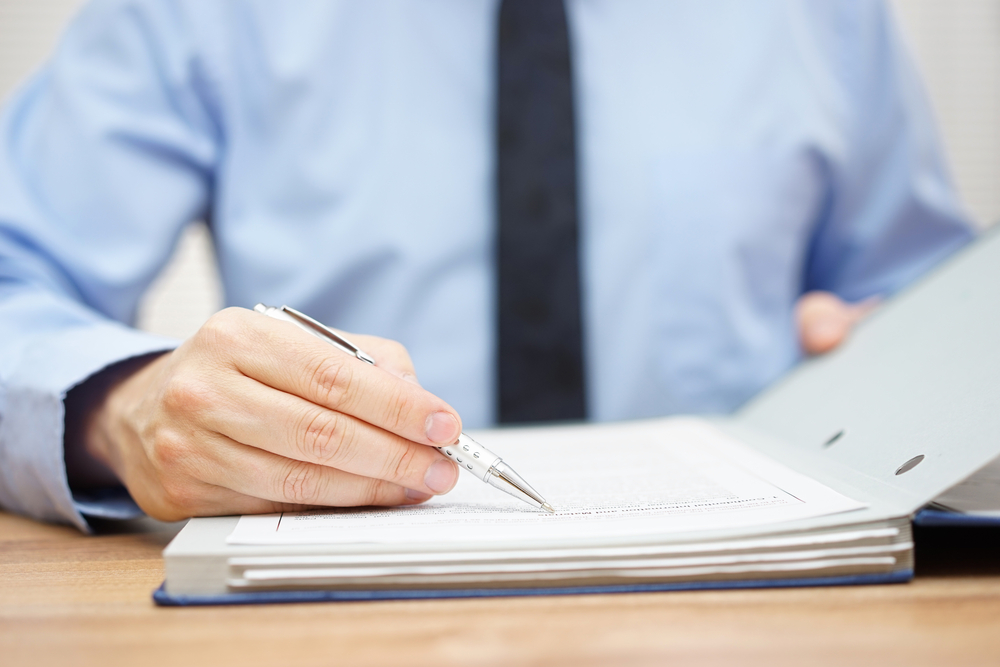
評価制度がない会社のリスク
評価制度がないと、どのようなリスクがあるのでしょうか。
モチベーションや生産性の低下
自分の業績や貢献度、前向きな姿勢などに対する評価がなされないため、従業員のモチベーションを低下させる恐れがあります。結果生産性の低迷や業績悪化、会社のイメージダウンにつながる可能性もあります。
人材流出による退職率の増加
評価制度がないと会社や個人の目標があいまいになり、優秀な人材ほど日々の努力や結果を正当に評価してくれる他社へ移る可能性が高まります。退職率が上がるため、新たな人材採用のために余計なコストがかかることもあるでしょう。
人間関係の悪化
評価制度がなければ、部下の仕事ぶりを可視化できないため、特に上司と部下の人間関係が悪化するリスクが高まります。上司の感情や感覚で評価されると信頼関係が薄れ、人材流出を増長しかねません。
管理職の負担増加
評価制度がないと、管理職の一存で昇進・昇格が決まる可能性もあります。明確な基準がない中で決めなくてはならないため部下の不満が蔓延しやすく、管理職側の心理的負担も大きくなります。
評価制度を導入するメリット
評価制度を導入することで、以下のような多くのメリットがあります。
従業員のモチベーション向上
従業員にとっては自分の目標やビジョンがはっきりするため、モチベーションや自己啓発力が向上します。会社から何を求められ、何が必要なのかが明確になり、自発的に業務を遂行する力も鍛えられます。
従業員満足度の向上
納得のいく基準で評価されると、自分が会社に評価されているという自信につながります。会社に役立っているという従業員満足度も向上し、生産性や業績アップも期待できるでしょう。
退職率の低下
評価制度があれば、特に優秀な人材の流出を防ぐことにつながります。離職率が低下すれば、会社のイメージアップにもなるでしょう。
能力・業績に合った待遇や配置の決定
一定の評価基準や指標ができると、従業員の能力や業績に合った処遇や、適材適所の配置を決めることができます。従業員の実力や実績を重視する会社では、客観的な指標が求められるため必要不可欠な制度といえます。
人材開発につながる
評価制度があれば、従業員の現状のスキルや課題を発見できます。これにより、スキル向上研修や教育プログラムの策定、配置換えなどの対策を組めるようになります。これらを活かせば、今後の人材開発にもつなげられるでしょう。
会社と従業員の信頼関係の構築
透明感や公平感のある評価制度であれば、従業員の間に安心感や帰属意識が育まれます。会社と従業員に信頼関係がうまれれば、組織全体のポテンシャルが向上します。
業績の向上と働き方改革の実現
正当な評価制度で従業員の従業員のモチベーションが上がると、業績アップを期待できます。また、適切な人材配置で業務の効率化が進み、働き方改革の実現も可能となるでしょう。

評価制度を導入・改善する際の注意点
評価制度を自社に導入する場合、もしくは現状の評価制度を改善するなら、以下のポイントに注意しましょう。
経営戦略と連動させる
評価制度は、自社の経営戦略と連動している必要があります。会社の目標やビジョンに合わせて、それぞれの従業員が何をすべきかが明確になるような仕組みでなくてはなりません。両者がかみ合っていないと制度が形骸化しやすく、従業員の成長を妨げる要因となってしまいます。
等級制度・報酬制度と連動させる
評価制度は独立して機能するものではなく、処遇に関わる等級制度や報酬制度とも連動させることが重要です。評価が高ければ給料やボーナスが増え、昇格などの目標ができ、モチベーションの向上につなげられます。
公平性と納得性のある評価基準にする
従業員の多くが納得し、公平性と透明性の高い評価制度を制定する必要があります。そのためには事前に従業員からヒアリングを行い、客観的に判断できる基準を決めるようにします。また、説明会などを実施して、従業員と評価基準のすり合わせを行っておくのもよいでしょう。
一貫性のある評価制度を導入する
評価制度は、経営戦略や従業員の行動指針と連動させるほかに、全部署で評価基準や評価方法を統一させておくことが重要です。部署の業務内容により評価項目が変わることがあっても、評価基準や方法が異なれば不公平な評価になりかねません。誰が行っても公平な評価となるような制度を取り入れるようにしましょう。
自社に合った評価制度を策定する
評価制度は、自社の業界や風土、環境に合わせたものにすることも大切です。大企業が導入して成功している制度を、中小企業の自社が取り入れてもうまくいくとは限りません。年功序列を大事にしている会社が能力重視の評価制度にすると、従業員の混乱を招き不満が爆発することでしょう。あくまでも、自社の経営戦略やビジョンに基づいた評価制度にすることが重要です。
自社で策定できないならプロに相談する
公平性のある評価制度を自社で策定することは容易ではありません。できるだけ公平性の高い評価制度を作りたいなら、外部のプロにアウトソーシングすることも検討しましょう。客観性が高くプロのノウハウを活かした質の高い制度を期待できるため、さまざまなリスクを最小限に抑え、結果コストダウンにつながる可能性も高まります。
まとめ
評価制度は、従業員の働きぶりや実績を評価して昇給や昇進などの処遇を決める基準に利用できます。そのため、従業員のモチペーションや生産性の向上、業績アップを可能にします。自社の経営方針や行動指針に合った評価制度を導入することが重要なものの、公平性のある制度の策定は難しく、必要であればプロに任せることも検討した方がよいでしょう。
弊社「株式会社P-UP neo」は、組織運営理論を体系化した組織マネジメント理論「識学」の唯一のパートナー企業です。各社に適切な評価制度の策定はもちろん、識学の導入サポートやさまざまな人材育成マネジメントのお手伝いを行っています。
公平な評価制度で人材育成や業績改善を検討しているなら、ぜひご相談ください。
評価制度に関する資料をご用意しております!
識学上席講師 大熊 憲二
2011年入社 ソフトバンク事業部に配属となり、史上最速の9ヵ月でマネージャーに昇進し、店舗拡大に貢献。
2014年モバイル事業部移動となり、業界全体が縮小傾向で低迷する中、200坪以上の超大型店等の新規出店に従事。
2016年に識学と出会い、識学に基づくマネジメントを徹底し、モバイル事業統括として史上初の年間目標完全達成を記録。
株式会社P-UP neo取締役常務執行役員兼識学上席講師として現在に至る。