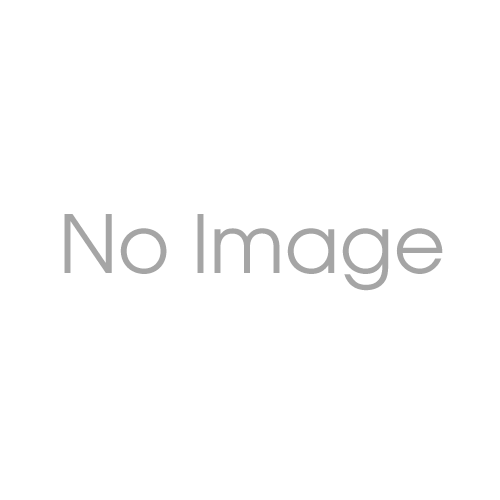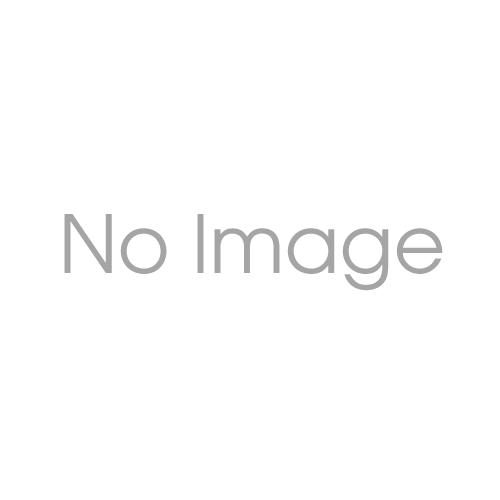2024年度の診療報酬改定、迫り来る2040年問題、そして深刻化する医療人材の不足。
現代の病院経営は、かつてないほど複雑で困難な課題に直面しています。
日々の診療に追われる中で、増え続ける経営課題に頭を悩ませている院長・経営者の方も少なくないでしょう。
多くの病院がコスト削減や増患対策といった目先の施策に注力しますが、実は、それらの課題の根底には共通する一つの本質的な問題が横たわっています。
それは「人事」と「組織」の問題です。
この記事では、なぜ今、病院経営の課題が「人事」に行き着くのかを解き明かし、その本質的な問題を解決するための「経営コンサルティング」、特に人事・組織に強いコンサルティングの失敗しない選び方について、専門的な視点から徹底的に解説します。
現代の病院は、激変する外部環境と、疲弊する内部環境という二つの大きな圧力に晒されており、院長一人のリーダーシップだけでは乗り越えられない複雑な課題に直面しています。
2年に一度の診療報酬改定は、病院の収益構造に大きな影響を与えます。
2024年度の改定では、賃上げや医療DXの推進、高齢者救急への対応などが大きなテーマとなり、これまで以上に戦略的な対応が求められています。
さらに、厚生労働省が推進する「地域医療構想」は、各地域における医療機能の分化・連携を促し、自院が地域でどのような役割を担うべきか、そのポジショニングを明確にすることを迫っています。
こうしたマクロな変化に適応し、持続可能な経営を実現するためには、専門的な知見に基づいた経営戦略の策定が不可欠です。
厚生労働省の統計によると、医師や看護師といった医療専門職の有効求人倍率は依然として高い水準で推移しており、採用競争は激化の一途をたどっています。
問題は採用難だけではありません。苦労して採用した人材が、数年で離職してしまうケースも後を絶ちません。
慢性的な人手不足は、残業の常態化や一人ひとりの業務負荷の増大を招き、職員のモチベーション低下や心身の疲弊につながります。
疲弊した組織では、医療の質の低下や医療事故のリスクも高まり、まさに負のスパイラルに陥ってしまうのです。
これらは一見すると別々の問題に見えますが、その根源を深く掘り下げていくと、すべてが「人事」と「組織」のあり方に繋がっています。
表面的な問題解決に終始するのではなく、この本質的な課題にメスを入れない限り、病院経営の好転は望めません。
「職員は皆、真面目に働いているはずなのに、なぜか収益が上がらない」。
その原因は、個人の能力ではなく、組織体制そのものにあるかもしれません。
例えば、各部署の役割分担が曖昧で、業務の重複や押し付け合いが発生していないでしょうか。
あるいは、部門間の連携が悪く、患者情報や業務の引継ぎがスムーズに行われず、無駄な時間や手間が発生していないでしょうか。
こうした組織の非効率性が、結果として人件費率の上昇や患者一人当たりの収益性の低下を招き、経営を圧迫するのです。
職員が離職を決意する理由は、「給与が低いから」だけではありません。
むしろ、「自分の働きが正当に評価されていない」という不満や、「この病院で働き続けても、キャリアアップが見込めない」という将来への不安が、より深刻な動機となるケースが多く見られます。
何をすれば評価され、どのようなキャリアを歩めるのか。
その基準となる人事評価制度や、個々の職員に求められる役割が明確に定義されていなければ、職員はやりがいを見失い、より良い条件を求めて組織を去ってしまいます。
採用活動においても、自院の魅力として明確な評価制度やキャリアパスを提示できなければ、優秀な人材を惹きつけることは困難です。
医療の現場において、組織体制の問題は経営だけでなく、患者の安全に直結します。
公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業の報告書を見ても、事故の背景要因として「コミュニケーション不足」や「連携不足」が繰り返し指摘されています。
医師、看護師、薬剤師、技師といった多職種が連携して一人の患者を診るチーム医療において、明確な指示命令系統や情報共有のルールが確立されていなければ、些細な伝達ミスが重大なインシデントにつながる危険性があります。
医療安全の確保は、個人の注意喚起だけでなく、エラーが起こりにくい組織の「仕組み」を構築することから始まります。
しかし、一口に経営コンサルティングと言っても、その専門領域は様々です。
自院の課題の本質を見極め、最適なパートナーを選ぶ必要があります。
財務・会計コンサルティングは、病院の「お金」に関する課題解決を専門とします。
主な支援内容としては、資金繰りの改善、借入金の最適化、診療報酬請求(レセプト)業務の効率化、医薬品や医療材料のコスト削減などが挙げられます。
決算書の分析を通じて経営状態を客観的に把握し、短期的な収益改善を目指す場合には非常に有効です。
患者数の減少に悩む病院にとって、増患・マーケティングコンサルティングは重要な選択肢となります。
ウェブサイトやSNSを活用した広報戦略の立案、近隣のクリニックや介護施設との連携強化(病診連携・病老連携)、自院の強みを活かしたブランディングなどを通じて、新規患者の獲得と地域における認知度の向上を目指します。
前述の通り、病院経営における多くの課題は、突き詰めると「人」と「組織」に行き着きます。
人事・組織コンサルティングは、この最も本質的で根深い課題の解決に特化しています。
人事評価制度の構築、役割定義の明確化、次世代リーダーの育成、組織内のコミュニケーション活性化などを通じて、職員が最大限のパフォーマンスを発揮できる「仕組み」を構築します。
財務やマーケティングといった施策の効果を最大化するためにも、その土台となる組織基盤の強化は不可欠な領域と言えるでしょう。
高額な費用を払ったにもかかわらず、「効果がなかった」と後悔しないために、コンサルティング会社を選ぶ際には以下の3つのポイントを必ず確認してください。
病院は、一般的な企業とは大きく異なる、極めて特殊な組織構造を持っています。
医師を頂点としたヒエラルキー、看護師、薬剤師、コメディカルといった多種多様な専門職集団、そして医療法人としてのガバナンス。
こうした医療業界ならではの文化や力学を深く理解していなければ、机上の空論で終わってしまいます。
コンサルタントが、医療機関特有の課題に対する豊富な支援実績や知見を持っているか、必ず確認しましょう。
「院長がもっとリーダーシップを発揮するべき」「職員の意識改革が必要です」といった、精神論や個人の資質に頼るアドバイスしかできないコンサルタントは危険です。
優れたコンサルティングは、特定の個人の能力に依存するのではなく、誰がその立場についても組織が正しく機能する「仕組み」や「ルール」を構築することを目指します。
曖昧な役割や評価基準を明確な言葉で定義し、組織全体が迷いなく動けるような、再現性の高いソリューションを提案できるかどうかが重要な見極めポイントです。
どんなに素晴らしい制度や戦略を立案しても、それが現場の職員に理解され、実行されなければ意味がありません。
コンサルティングの役割は、計画書を作って終わりではないはずです。
新しい評価制度を導入する際の説明会の実施、管理職向けのマネジメント研修、制度定着までの定期的なフォローアップなど、改革を「絵に描いた餅」で終わらせないための、現場を巻き込んだ具体的な実行支援まで提供してくれるかどうかを確認しましょう。
代表的な4つのテーマを見ていきましょう。
コンサルティングを通じて、公平で透明性の高い人事評価制度と、等級に応じた明確な給与テーブルを構築します。
これにより、職員は自身の働きが正当に評価されていると実感でき、将来のキャリアパスも描けるようになります。
結果として、エンゲージメントが高まり、離職率の低下につながります。採用面接の場でも、これらの制度を魅力として具体的にアピールできるようになり、採用競争力の向上にも貢献します。
各役職に求められる役割、責任、権限を明確に定義します。
これにより、職員は自分のなすべきことを正しく認識し、自律的に行動できるようになります。
特に、部門長などの管理職に対しては、部下を正しく評価し、指導するためのマネジメントトレーニングを実施します。
院長の指示を待つだけでなく、自ら考え、組織を動かせる次世代の経営幹部が育つ土壌を醸成します。
「頑張っているのに評価されない」「上司の好き嫌いで評価が決まる」といった不満は、職員のモチベーションを著しく低下させます。
コンサルティングでは、評価項目、基準、プロセスを全職員に公開し、誰もが納得できる客観的な評価制度を設計します。
評価結果は必ず本人にフィードバックされ、次の成長への具体的な目標設定につなげます。
これにより、組織全体のパフォーマンス向上と、職員の成長意欲の喚起を両立させます。
「誰の指示に従えばいいのかわからない」「言った、言わないの水掛け論が頻発する」。
こうした現場の混乱は、曖昧な指示命令系統が原因です。
組織図や役職ごとの責任範囲を明確化し、報告・連絡・相談のルールを定めることで、スムーズな情報伝達と意思決定を可能にします。
これにより、業務の非効率性を解消し、職員間の無用なストレスや労務トラブルのリスクを低減させます。
「識学」とは、組織内の人々が持つ「誤解」や「錯覚」に着目し、それらを排除することで、組織のパフォーマンスを最大化させる独自のマネジメント理論です。
なぜこの理論が、病院という特殊な組織に有効なのでしょうか。
病院は、医師、看護師、技師など、それぞれが高い専門性を持つプロフェッショナルの集団です。
その専門性の高さゆえに、「自分のやり方が一番正しい」「あの部署は何もわかっていない」といった、他者や他部署に対する誤解や、自身の役割に対する錯覚が生じやすくなります。
「識学」では、組織における唯一のルールとして、個々の「位置(役職)」と、その位置に求められる「役割」を徹底的に明確化します。個人の感情や経験則ではなく、定められたルールに基づいて行動することで、属人的な判断によるブレや対立がなくなり、組織全体の目標達成に向けた、機能的で生産性の高い連携が可能になります。
多くの院長が、日々の細かなマネジメント業務に忙殺され、本来注力すべき経営戦略の立案や、高度な診療、地域連携といった重要な業務に時間を割けていないのが実情です。
「識学」を導入し、組織運営の「仕組み」が構築されると、院長が細かく指示を出さなくても、各職員が自らの役割を認識して自律的に動くようになります。
これにより、院長のマネジメント工数は劇的に削減され、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。
これは、院長自身の疲弊を防ぐだけでなく、病院全体の成長を加速させる上で極めて重要な効果をもたらします。
表面的な問題に一喜一憂するのではなく、その根底にある人事・組織の課題に目を向けることこそ、持続可能な病院経営を実現するための唯一の道です。
そして、その本質的な課題解決のためには、個人の意識改革に頼るのではなく、誰もが正しく動ける「仕組み」を構築することが不可欠です。
失敗しない経営コンサルティングの選定を通じて、自院の組織を根本から見直し、変革していく。
その決断が、職員にとっても、患者にとっても、そして地域にとっても価値ある病院であり続けるための、最も確実な一歩となるでしょう。
現代の病院経営は、かつてないほど複雑で困難な課題に直面しています。
日々の診療に追われる中で、増え続ける経営課題に頭を悩ませている院長・経営者の方も少なくないでしょう。
多くの病院がコスト削減や増患対策といった目先の施策に注力しますが、実は、それらの課題の根底には共通する一つの本質的な問題が横たわっています。
それは「人事」と「組織」の問題です。
この記事では、なぜ今、病院経営の課題が「人事」に行き着くのかを解き明かし、その本質的な問題を解決するための「経営コンサルティング」、特に人事・組織に強いコンサルティングの失敗しない選び方について、専門的な視点から徹底的に解説します。
なぜ今、多くの病院が経営コンサルティングを必要としているのか?
かつてのように、質の高い医療を提供していれば自然と患者が集まり、経営が成り立っていた時代は終わりを告げました。現代の病院は、激変する外部環境と、疲弊する内部環境という二つの大きな圧力に晒されており、院長一人のリーダーシップだけでは乗り越えられない複雑な課題に直面しています。
外部環境の激変|診療報酬改定と地域医療構想への対応
国の医療政策は、病院経営を直接的に揺るがす最も大きな外部要因です。2年に一度の診療報酬改定は、病院の収益構造に大きな影響を与えます。
2024年度の改定では、賃上げや医療DXの推進、高齢者救急への対応などが大きなテーマとなり、これまで以上に戦略的な対応が求められています。
さらに、厚生労働省が推進する「地域医療構想」は、各地域における医療機能の分化・連携を促し、自院が地域でどのような役割を担うべきか、そのポジショニングを明確にすることを迫っています。
こうしたマクロな変化に適応し、持続可能な経営を実現するためには、専門的な知見に基づいた経営戦略の策定が不可欠です。
内部環境の課題|深刻化する「人材不足」と「組織の疲弊」
外部環境の変化以上に、多くの病院を苦しめているのが内部の課題、とりわけ「人材」に関する問題です。厚生労働省の統計によると、医師や看護師といった医療専門職の有効求人倍率は依然として高い水準で推移しており、採用競争は激化の一途をたどっています。
問題は採用難だけではありません。苦労して採用した人材が、数年で離職してしまうケースも後を絶ちません。
慢性的な人手不足は、残業の常態化や一人ひとりの業務負荷の増大を招き、職員のモチベーション低下や心身の疲弊につながります。
疲弊した組織では、医療の質の低下や医療事故のリスクも高まり、まさに負のスパイラルに陥ってしまうのです。
病院経営の課題は、すべて「人事」と「組織」に行き着く
収益改善、採用難、医療安全の確保。これらは一見すると別々の問題に見えますが、その根源を深く掘り下げていくと、すべてが「人事」と「組織」のあり方に繋がっています。
表面的な問題解決に終始するのではなく、この本質的な課題にメスを入れない限り、病院経営の好転は望めません。
収益改善の壁となる、生産性の低い組織体制
「職員は皆、真面目に働いているはずなのに、なぜか収益が上がらない」。その原因は、個人の能力ではなく、組織体制そのものにあるかもしれません。
例えば、各部署の役割分担が曖昧で、業務の重複や押し付け合いが発生していないでしょうか。
あるいは、部門間の連携が悪く、患者情報や業務の引継ぎがスムーズに行われず、無駄な時間や手間が発生していないでしょうか。
こうした組織の非効率性が、結果として人件費率の上昇や患者一人当たりの収益性の低下を招き、経営を圧迫するのです。
採用難・離職の根本原因は、不透明な評価制度と役割定義
職員が離職を決意する理由は、「給与が低いから」だけではありません。むしろ、「自分の働きが正当に評価されていない」という不満や、「この病院で働き続けても、キャリアアップが見込めない」という将来への不安が、より深刻な動機となるケースが多く見られます。
何をすれば評価され、どのようなキャリアを歩めるのか。
その基準となる人事評価制度や、個々の職員に求められる役割が明確に定義されていなければ、職員はやりがいを見失い、より良い条件を求めて組織を去ってしまいます。
採用活動においても、自院の魅力として明確な評価制度やキャリアパスを提示できなければ、優秀な人材を惹きつけることは困難です。
医療安全を脅かす、コミュニケーションエラーと連携不足
医療の現場において、組織体制の問題は経営だけでなく、患者の安全に直結します。公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業の報告書を見ても、事故の背景要因として「コミュニケーション不足」や「連携不足」が繰り返し指摘されています。
医師、看護師、薬剤師、技師といった多職種が連携して一人の患者を診るチーム医療において、明確な指示命令系統や情報共有のルールが確立されていなければ、些細な伝達ミスが重大なインシデントにつながる危険性があります。
医療安全の確保は、個人の注意喚起だけでなく、エラーが起こりにくい組織の「仕組み」を構築することから始まります。
【種類別】病院経営コンサルティング|自院の課題に合うのはどれ?
こうした複雑な課題を解決するために、外部の専門家である経営コンサルタントの活用を検討する病院が増えています。しかし、一口に経営コンサルティングと言っても、その専門領域は様々です。
自院の課題の本質を見極め、最適なパートナーを選ぶ必要があります。
財務・会計コンサルティング|資金繰りやコスト削減が主目的
財務・会計コンサルティングは、病院の「お金」に関する課題解決を専門とします。主な支援内容としては、資金繰りの改善、借入金の最適化、診療報酬請求(レセプト)業務の効率化、医薬品や医療材料のコスト削減などが挙げられます。
決算書の分析を通じて経営状態を客観的に把握し、短期的な収益改善を目指す場合には非常に有効です。
増患・マーケティングコンサルティング|集患力強化とブランディング
患者数の減少に悩む病院にとって、増患・マーケティングコンサルティングは重要な選択肢となります。ウェブサイトやSNSを活用した広報戦略の立案、近隣のクリニックや介護施設との連携強化(病診連携・病老連携)、自院の強みを活かしたブランディングなどを通じて、新規患者の獲得と地域における認知度の向上を目指します。
人事・組織コンサルティング|本質的な課題解決に不可欠な領域
前述の通り、病院経営における多くの課題は、突き詰めると「人」と「組織」に行き着きます。人事・組織コンサルティングは、この最も本質的で根深い課題の解決に特化しています。
人事評価制度の構築、役割定義の明確化、次世代リーダーの育成、組織内のコミュニケーション活性化などを通じて、職員が最大限のパフォーマンスを発揮できる「仕組み」を構築します。
財務やマーケティングといった施策の効果を最大化するためにも、その土台となる組織基盤の強化は不可欠な領域と言えるでしょう。
失敗しない!人事・組織に強い病院経営コンサルティングの選び方
組織という目に見えないものを扱う人事コンサルティングは、その実力を見極めるのが難しい領域でもあります。高額な費用を払ったにもかかわらず、「効果がなかった」と後悔しないために、コンサルティング会社を選ぶ際には以下の3つのポイントを必ず確認してください。
ポイント①:医療業界特有の組織構造への深い理解があるか
病院は、一般的な企業とは大きく異なる、極めて特殊な組織構造を持っています。医師を頂点としたヒエラルキー、看護師、薬剤師、コメディカルといった多種多様な専門職集団、そして医療法人としてのガバナンス。
こうした医療業界ならではの文化や力学を深く理解していなければ、机上の空論で終わってしまいます。
コンサルタントが、医療機関特有の課題に対する豊富な支援実績や知見を持っているか、必ず確認しましょう。
ポイント②:属人的な指導ではなく「仕組み」で解決する提案力があるか
「院長がもっとリーダーシップを発揮するべき」「職員の意識改革が必要です」といった、精神論や個人の資質に頼るアドバイスしかできないコンサルタントは危険です。優れたコンサルティングは、特定の個人の能力に依存するのではなく、誰がその立場についても組織が正しく機能する「仕組み」や「ルール」を構築することを目指します。
曖昧な役割や評価基準を明確な言葉で定義し、組織全体が迷いなく動けるような、再現性の高いソリューションを提案できるかどうかが重要な見極めポイントです。
ポイント③:院長・経営層だけでなく、現場を巻き込む実行支援力があるか
どんなに素晴らしい制度や戦略を立案しても、それが現場の職員に理解され、実行されなければ意味がありません。コンサルティングの役割は、計画書を作って終わりではないはずです。
新しい評価制度を導入する際の説明会の実施、管理職向けのマネジメント研修、制度定着までの定期的なフォローアップなど、改革を「絵に描いた餅」で終わらせないための、現場を巻き込んだ具体的な実行支援まで提供してくれるかどうかを確認しましょう。
【課題別】人事コンサルティングが解決する具体的なテーマ
では、人事・組織コンサルティングは、病院が抱える具体的な課題に対して、どのような解決策をもたらすのでしょうか。代表的な4つのテーマを見ていきましょう。
課題①:採用と定着|優秀な人材が辞めない組織の作り方
コンサルティングを通じて、公平で透明性の高い人事評価制度と、等級に応じた明確な給与テーブルを構築します。これにより、職員は自身の働きが正当に評価されていると実感でき、将来のキャリアパスも描けるようになります。
結果として、エンゲージメントが高まり、離職率の低下につながります。採用面接の場でも、これらの制度を魅力として具体的にアピールできるようになり、採用競争力の向上にも貢献します。
課題②:人材育成|院長の右腕となる次世代リーダーが育たない
各役職に求められる役割、責任、権限を明確に定義します。これにより、職員は自分のなすべきことを正しく認識し、自律的に行動できるようになります。
特に、部門長などの管理職に対しては、部下を正しく評価し、指導するためのマネジメントトレーニングを実施します。
院長の指示を待つだけでなく、自ら考え、組織を動かせる次世代の経営幹部が育つ土壌を醸成します。
課題③:評価制度|職員の不満をなくし、モチベーションを高めるには?
「頑張っているのに評価されない」「上司の好き嫌いで評価が決まる」といった不満は、職員のモチベーションを著しく低下させます。コンサルティングでは、評価項目、基準、プロセスを全職員に公開し、誰もが納得できる客観的な評価制度を設計します。
評価結果は必ず本人にフィードバックされ、次の成長への具体的な目標設定につなげます。
これにより、組織全体のパフォーマンス向上と、職員の成長意欲の喚起を両立させます。
課題④:労務管理|曖ेंな指示命令系統が引き起こす現場の混乱
「誰の指示に従えばいいのかわからない」「言った、言わないの水掛け論が頻発する」。こうした現場の混乱は、曖昧な指示命令系統が原因です。
組織図や役職ごとの責任範囲を明確化し、報告・連絡・相談のルールを定めることで、スムーズな情報伝達と意思決定を可能にします。
これにより、業務の非効率性を解消し、職員間の無用なストレスや労務トラブルのリスクを低減させます。
「識学」に基づく組織コンサルティングが、病院経営の未来を変える
数ある人事・組織コンサルティングの中でも、近年、多くの医療法人から注目を集めているのが「識学」という組織運営理論に基づいたコンサルティングです。
なぜ医療法人に「識学」が有効なのか?
「識学」とは、組織内の人々が持つ「誤解」や「錯覚」に着目し、それらを排除することで、組織のパフォーマンスを最大化させる独自のマネジメント理論です。なぜこの理論が、病院という特殊な組織に有効なのでしょうか。
専門職集団にありがちな「誤解」や「錯覚」をなくす
病院は、医師、看護師、技師など、それぞれが高い専門性を持つプロフェッショナルの集団です。その専門性の高さゆえに、「自分のやり方が一番正しい」「あの部署は何もわかっていない」といった、他者や他部署に対する誤解や、自身の役割に対する錯覚が生じやすくなります。
「識学」では、組織における唯一のルールとして、個々の「位置(役職)」と、その位置に求められる「役割」を徹底的に明確化します。個人の感情や経験則ではなく、定められたルールに基づいて行動することで、属人的な判断によるブレや対立がなくなり、組織全体の目標達成に向けた、機能的で生産性の高い連携が可能になります。
院長のマネジメント工数を削減し、本来の業務に集中できる環境を創出
多くの院長が、日々の細かなマネジメント業務に忙殺され、本来注力すべき経営戦略の立案や、高度な診療、地域連携といった重要な業務に時間を割けていないのが実情です。 「識学」を導入し、組織運営の「仕組み」が構築されると、院長が細かく指示を出さなくても、各職員が自らの役割を認識して自律的に動くようになります。
これにより、院長のマネジメント工数は劇的に削減され、より付加価値の高い業務に集中できる環境が整います。
これは、院長自身の疲弊を防ぐだけでなく、病院全体の成長を加速させる上で極めて重要な効果をもたらします。
組織が変われば、病院経営は必ず成長する
診療報酬改定への対応、人材不足の克服、医療安全の徹底。病院経営が直面するこれらの課題は、すべて健全な「組織」という土台があってこそ、乗り越えることができます。表面的な問題に一喜一憂するのではなく、その根底にある人事・組織の課題に目を向けることこそ、持続可能な病院経営を実現するための唯一の道です。
そして、その本質的な課題解決のためには、個人の意識改革に頼るのではなく、誰もが正しく動ける「仕組み」を構築することが不可欠です。
失敗しない経営コンサルティングの選定を通じて、自院の組織を根本から見直し、変革していく。
その決断が、職員にとっても、患者にとっても、そして地域にとっても価値ある病院であり続けるための、最も確実な一歩となるでしょう。