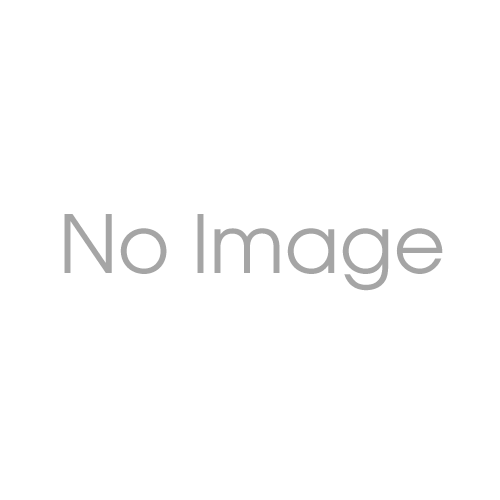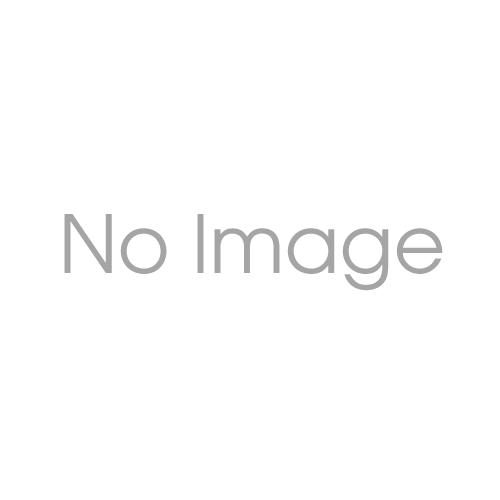医療という、人の生命を直接預かる崇高な事業。
その経営は、常に目に見えない無数の「リスク」と隣り合わせです。
医療過誤や院内感染といった直接的な医療安全リスクはもちろんのこと、深刻化する人材不足、頻発する労務トラブル、そして厳しさを増す経営環境など、現代の病院経営者が向き合うべきリスクは、かつてなく多様化・複雑化しています。
多くの病院では、インシデントレポートの収集や定期的な研修、マニュアルの改訂といった対策が講じられています。
しかし、それでもなお、なぜ同じような問題が繰り返し発生するのでしょうか。
なぜ、組織の疲弊は止まらないのでしょうか。
その答えは、多くの経営者が見過ごしがちな場所にあります。
実は、院内で発生するほぼすべてのリスクの根源は、個々の職員のスキルや意識の問題ではなく、組織全体の「構造」と「仕組み」、すなわち「組織マネジメント」の不備に起因しているのです。
「ヒューマンエラーは起こるもの」という前提に立ち、それを個人の責任に帰するのではなく、エラーが起こりにくい、あるいはエラーが起きても重大な結果に至らない「組織」をいかにして構築するか。
これこそが、現代の病院経営者に求められるリスクマネジメントの新常識です。
本記事では、病院経営を取り巻くリスクの全体像を改めて整理するとともに、なぜ従来の対策では限界があるのかを解き明かします。
改めて問う、病院経営における「リスク」の全体像
リスクマネジメントの第一歩は、自院がどのようなリスクに晒されているのかを網羅的かつ客観的に把握することから始まります。病院経営におけるリスクは、多岐にわたる領域に存在し、それぞれが複雑に絡み合っています。
ここでは、主要なリスクを5つのカテゴリに分類し、その全体像を整理します。
【分類①】医療安全に関わるリスク
医療安全に関わるリスクは、患者の生命や健康に直接的な影響を及ぼす、病院にとって最も根源的かつ重大なリスク領域です。
ひとたび発生すれば、患者やその家族に多大な苦痛を与えるだけでなく、病院の信頼を失墜させ、経営に致命的なダメージを与えかねません。
医療過誤・医療訴訟
医療過誤は、医療従事者の過失によって患者に損害が発生する事象を指します。誤診、投薬ミス、手術ミス、検査ミスなど、その内容は多岐にわたります。
公益財団法人日本医療機能評価機構の報告によれば、医療事故の背景には、確認不足や観察不足といったヒューマンエラーだけでなく、多忙な業務環境や部門間の連携不足といった組織的な要因が深く関わっていることが指摘されています。
医療過誤が発生した場合、患者側から損害賠償を求める医療訴訟に発展するリスクがあり、その対応には多大な時間、費用、そして精神的負担を要します。
訴訟の結果によっては、億単位の賠償金が命じられるケースも少なくありません。
院内感染
院内感染は、病院内で患者や職員が新たな感染症に罹患することです。特に、免疫力が低下している患者が多い病院環境では、MRSA(メチシリン耐性黄色ブドウ球菌)のような薬剤耐性菌や、新型コロナウイルスのような新興感染症によるアウトブレイク(集団発生)が大きなリスクとなります。
院内感染の発生は、患者の治療期間の長期化や死亡リスクの増大につながるだけでなく、病棟閉鎖や外来診療の制限といった措置が必要となり、病院の診療機能そのものを麻痺させ、大幅な減収に直結します。
手指衛生や消毒といった基本的な感染対策の徹底はもちろんのこと、感染経路の早期特定や迅速な情報共有といった組織的な対応体制の構築が不可欠です。
医療機器の不具合・誤操作
現代医療は、人工呼吸器、輸液ポンプ、生体情報モニタ、手術支援ロボットなど、高度で複雑な医療機器に大きく依存しています。これらの医療機器の定期的なメンテナンス不足による不具合や、職員の知識・スキル不足による誤操作は、患者に直接的な危害を及ぼす重大なリスクです。
医療機器の安全な使用を確保するためには、定期的な保守点検計画の策定と実施、職員に対する継続的な操作研修、そして使用前後のダブルチェックといった手順を組織のルールとして徹底することが求められます。
【分類②】人事・労務に関わるリスク
病院という組織は、「人」によって成り立っています。そのため、職員に関わる人事・労務リスクは、医療の質と経営の安定性を根底から揺るがす、極めて重要なリスク領域です。
このリスクへの対応を怠れば、組織は内側から崩壊していくことになります。
人材の採用難と離職
少子高齢化に伴う労働力人口の減少は、医療業界においても深刻な影響を及ぼしており、医師、看護師、薬剤師、介護職員など、あらゆる職種で人材不足が常態化しています。厚生労働省が公表する有効求人倍率を見ても、医療・福祉分野は常に全産業平均を大きく上回る水準で推移しており、採用競争は激化の一途です。
問題は採用の困難さだけではありません。
高いコストをかけて採用した人材が、数年、あるいは数ヶ月で離職してしまう問題も深刻です。
慢性的な人材不足は、既存職員の業務負荷を増大させ、さらなる離職を招くという悪循環を生み出します。
この負のスパイラルは、医療の質の低下、患者満足度の低下、そして収益の悪化に直結します。
労務トラブル(残業代未払い、ハラスメント)
長時間労働が常態化しやすい医療現場では、残業代の未払いといった労務リスクが潜在しています。労働基準監督署による是正勧告や、職員からの訴訟に発展した場合、多額の未払い賃金の支払いだけでなく、企業の社会的信用の失墜という大きな代償を払うことになります。
また、近年特に問題視されているのが、職場内のパワーハラスメントやセクシャルハラスメントです。
医師とコメディカル、先輩と後輩といった職務上の優位性を背景としたハラスメントは、被害者のメンタルヘルスを著しく損ない、離職の直接的な原因となります。
ハラスメントを許さない組織文化の醸成と、相談窓口の設置や懲戒規定の整備といった具体的な対策が急務です。
職員のメンタルヘルス不調
人の生死に直面するストレス、長時間労働、複雑な人間関係、患者や家族からのクレーム対応など、医療従事者は極めて高い精神的負荷に晒されています。職員のメンタルヘルス不調は、休職や離職につながるだけでなく、注意力の散漫による医療ミスの誘発や、組織全体の士気の低下を招くリスクがあります。
ストレスチェックの実施や相談体制の整備といった基本的な対策に加え、個々の職員の業務負荷を適切に管理し、過度なストレスがかからないような組織的なマネジメントが不可欠です。
【分類③】経営・財務に関わるリスク
医療の質を追求する上でも、その土台となる安定した経営基盤は不可欠です。診療報酬の動向や市場の変化、投資判断の誤りなど、経営・財務に関わるリスクへの備えがなければ、病院の存続そのものが危うくなります。
診療報酬のマイナス改定
病院収入の大部分を占める診療報酬は、2年に一度の改定によって点数が変動します。国全体の医療費抑制政策を背景に、特定の領域でマイナス改定が行われた場合、病院の収益は直接的な打撃を受けます。
自院の診療内容が、将来の改定でどのような影響を受ける可能性があるかを予測し、収益構造の多角化や、新たな医療ニーズへの対応といった戦略的な手を打っておく必要があります。
風評被害・ブランディングの失敗
医療過誤や院内感染、職員の不祥事といったネガティブな情報が、インターネットやSNSを通じて瞬時に拡散される現代において、風評被害は極めて大きな経営リスクです。一度損なわれた地域の信頼を回復するには、長い時間と多大な努力を要します。
日頃から質の高い医療を提供し、地域社会との良好な関係を築くことはもちろん、万が一の事態に備えた広報対応体制を準備しておくことが重要です。
設備投資の失敗
MRIやCTといった高額な医療機器の導入や、新病棟の建設といった大規模な設備投資は、病院の競争力を高める上で重要ですが、同時に大きな財務リスクを伴います。事前の診療圏分析や需要予測が不十分なまま投資を実行し、想定した収益が得られなかった場合、多額の借入金返済が経営を圧迫することになります。
客観的なデータに基づいた、慎重な投資判断が求められます。
【分類④】情報管理に関わるリスク
電子カルテの普及により、医療情報のデジタル化が急速に進む中、情報管理に関するリスクはかつてないほど高まっています。個人情報(患者情報)の漏洩
患者の氏名、住所、病名、治療内容といった情報は、個人情報の中でも特に機密性の高い「要配慮個人情報」に該当します。これらの情報が、USBメモリの紛失や職員の誤操作、不正アクセスなどによって外部に漏洩した場合、患者に多大な精神的苦痛を与えるだけでなく、個人情報保護法に基づく厳しい行政処分や、損害賠償請求の対象となります。
病院の信頼は、地に落ちることになるでしょう。
サイバー攻撃
近年、国内外で医療機関を標的としたサイバー攻撃が急増しています。特に、病院のシステムを暗号化して使用不能にし、復旧と引き換えに金銭を要求する「ランサムウェア」による被害が深刻化しています。
電子カルテシステムが停止すれば、診療そのものが不可能となり、患者の生命に危険が及ぶ事態も想定されます。
セキュリティ対策ソフトの導入といった技術的な対策と同時に、職員への情報セキュリティ教育の徹底が不可欠です。
【分類⑤】災害・インシデントに関わるリスク
予測が困難な自然災害や、突発的な事故・事件への備えも、病院のリスクマネジメントとして欠かせない要素です。自然災害(地震、水害)
地震や台風、集中豪雨といった自然災害は、建物の損壊やライフライン(電気、ガス、水道)の寸断を引き起こし、病院の診療機能を完全に停止させる可能性があります。災害時においても地域の医療拠点としての役割を果たし続けるためには、建物の耐震化や非常用電源の確保といったハード面の対策と、災害発生時の対応手順を定めた事業継続計画(BCP)の策定および定期的な訓練が求められます。
火災・停電
院内での火災や、落雷などによる広域停電も、診療に深刻な影響を及ぼすリスクです。特に、人工呼吸器など生命維持に直結する医療機器を使用している患者がいる場合、電源の喪失は致命的です。
スプリンクラーなどの消防設備の定期点検と、非常用発電装置の確実な作動を確認しておくことが重要です。
なぜ、院内のリスクはなくならないのか?すべての根源は「組織」にある
これまで見てきたように、病院は多種多様なリスクに囲まれています。多くの病院では、これらのリスクに対し、マニュアルの作成、研修の実施、インシデントレポートの提出といった対策を講じています。
にもかかわらず、なぜ医療ミスや労務トラブル、情報漏洩といった問題は後を絶たないのでしょうか。
その答えは、これらのリスクの大部分が、個人の意識やスキルといった属人的な要因ではなく、組織の構造的な欠陥、すなわち「組織マネジメントの不備」に根差しているからです。
「ヒューマンエラー」は個人の資質の問題ではない
医療過誤や情報漏洩といったインシデントが発生した際、その原因はしばしば「担当者の確認不足」「注意散漫」といった、個人の資質の問題として片付けられがちです。しかし、本当にそうでしょうか。著名な心理学者ジェームズ・リーズンが提唱した「スイスチーズモデル」が示すように、事故は単一の原因で起こるのではなく、組織内に存在する複数の欠陥(チーズの穴)が偶然一直線に並んだ時に発生します。
つまり、個人のエラーは事故の最終的な引き金に過ぎず、その背後にはエラーを誘発しやすい組織的な要因が隠されているのです。
エラーを誘発する「曖昧な役割」と「不明確な指示命令系統」
例えば、「この業務は、最終的に誰が責任を持って確認するのか」という役割分担が曖昧な場合、職員は「誰かがやってくれるだろう」という思い込みに陥り、確認漏れが発生しやすくなります。また、「A医師からはこう指示されたが、B看護師長からは違うことを言われた。一体どちらに従えばいいのか」といった、指示命令系統の混乱は、現場の職員を疲弊させ、判断ミスを誘発します。
これらの「曖昧さ」こそが、ヒューマンエラーが生まれる温床なのです。
個人の注意力に頼るのではなく、誰が何をすべきか、誰が誰に指示を出すのか、そのルールが明確に定義された組織構造こそが、エラーに対する最も強力な防御策となります。
「言ったはず」「聞いたはず」が生まれる、コミュニケーションの構造的欠陥
医療現場におけるリスクの多くは、コミュニケーションエラーに起因します。口頭での指示や申し送りが、「言ったはず」「いや、聞いていない」という水掛け論に発展し、重大なインシデントにつながるケースは後を絶ちません。
これは、職員間の仲が悪いから起こるのではありません。
いつ、誰が、誰に、何を、どのように伝達するのか、そしてその伝達内容が正しく理解されたことを、どのように確認するのか。
こうしたコミュニケーションの「ルール」が組織として定められていないことに、構造的な問題があるのです。
従来の医療安全対策の限界
多くの病院で熱心に取り組まれている従来の医療安全対策も、組織マネジメントという視点が欠けていると、その効果は限定的なものにならざるを得ません。形骸化するインシデントレポート|報告が目的になっていませんか?
インシデントレポート(ヒヤリ・ハット報告)は、潜在的なリスクを可視化するための重要なツールです。
しかし、その運用が「レポートを提出すること」自体を目的としてしまい、集まった情報が具体的な再発防止策、すなわち「組織のルール変更」に繋がっていなければ、何の意味もありません。
また、「報告すると自分が責められるのではないか」という雰囲気が組織内にあると、職員は正直な報告を躊躇し、重要な情報が隠蔽されてしまう危険性すらあります。
効果が持続しない職員研修|「意識向上」だけでは組織は変わらない
医療安全やハラスメント防止に関する研修は、知識の習得や意識喚起のために重要です。しかし、その効果は一時的なものに留まりがちです。
研修で「患者確認を徹底しましょう」「ハラスメントは許しません」と学んでも、日常業務に戻れば、確認作業を省略せざるを得ないほど多忙な環境や、ハラスメントが起きても誰も指摘できないような組織風土が変わらなければ、行動変容には繋がりません。
「意識」という曖昧なものに頼るのではなく、正しい行動をせざるを得ない「仕組み」を構築することこそが、本質的な解決策です。
リスクマネージャーの孤立|属人的な努力に依存する危うさ
多くの病院では、専任または兼任のリスクマネージャーが任命され、院内のリスク管理を一手に担っています。しかし、リスクマネージャーに強大な権限が与えられていない限り、その活動は各部署への「お願い」ベースにならざるを得ず、実効性のある改善策を推進することは困難です。
結果として、リスクマネージャー個人の情熱や努力に依存した、属人的な活動に陥りがちです。
リスクマネジメントは、特定の一人が担うものではなく、院長をトップとした明確な指揮命令系統のもと、組織全体で取り組むべき経営課題なのです。
【本質的解決策】リスクに強い病院は「組織マネジメント」が徹底されている
これまで述べてきたように、院内に存在するあらゆるリスクの根源は、組織の構造的な欠陥、すなわち「曖昧さ」にあります。したがって、真のリスクマネジメントとは、この「曖昧さ」を組織から徹底的に排除し、誰もが迷いなく、正しく行動できる「仕組み」を構築することに他なりません。
リスクマネジメントとは「曖昧さの排除」に他ならない
「なるべく早く」「適切に」「臨機応変に」「しっかりと」。
これらは、日常の業務指示で何気なく使われがちな言葉ですが、すべて受け手によって解釈が異なる、極めて曖昧な表現です。
「なるべく早く」とは、10分後なのか、1時間後なのか。
「適切に」とは、具体的に何をどうすることなのか。
このような曖昧な指示が、職員の判断の迷いや、期待とのズレを生み、ミスやトラブルの原因となります。
リスクに強い組織では、こうした曖昧な言葉は徹底的に排除されます。
すべての業務指示やルールは、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのような状態で」行うべきか、誰もが一意に解釈できる具体的な言葉で定義されています。
この「曖昧さの排除」こそが、組織マネジメントの第一歩であり、リスクマネジメントの核心なのです。
「ルール」がリスクを未然に防ぐ防波堤となる
組織におけるリスクを未然に防ぐ最も強力なツールは「ルール」です。患者確認の手順、情報共有の方法、ハラスメントの禁止事項、個人情報の取り扱いなど、組織として守るべき基準を明確なルールとして定めることで、職員は個人の感覚や経験に頼ることなく、統一された正しい行動をとることができます。
ルールは、職員を縛るためのものではなく、職員を迷いや判断ミスから守り、組織をリスクから守るための防波堤なのです。
なぜルールは守られないのか?
しかし、多くの病院で「マニュアルはあるのに、守られていない」という現実があります。なぜルールは形骸化するのでしょうか。
その原因は、ルールの内容そのものよりも、ルールを運用する組織の構造に問題がある場合がほとんどです。
例えば、ルール違反に対する結果責任が曖昧であったり、ルールを守らなくても特に不利益がなく、むしろ破った方が楽である、といった状況では、ルールは守られません。
また、現場の実態とかけ離れた非現実的なルールも、形骸化の原因となります。
ルールを機能させるための「位置」と「役割」の完全定義
ルールを真に機能させるためには、まず組織内のすべての「位置(役職)」と、その位置に求められる「役割」を完全に定義する必要があります。院長には院長としての役割と責任が、看護部長には看護部長としての役割と責任が、そして一般の看護師には看護師としての役割と責任があります。
そして、上位の役職者は、下位の役職者が自らの役割を正しく果たし、ルールを遵守しているかを管理・監督する責任を負います。
この責任の連鎖が明確になることで初めて、ルールは組織全体で遵守される、実効性のあるものとなるのです。
「評価制度」が職員の行動をリスク回避へと導く
組織の中で、職員の行動を最も強く方向づけるものは何か。それは「人事評価制度」です。
人は、自分が評価される行動を優先し、評価されない行動は後回しにする傾向があります。
したがって、評価制度をリスクマネジメントの観点から戦略的に設計することで、職員の行動を自律的にリスク回避へと導くことが可能になります。
評価基準の曖昧さが引き起こす、職員の不満とモチベーション低下
「上司の好き嫌いで評価が決まる」「何を頑張れば評価されるのかわからない」。このような評価基準の曖昧さは、職員の間に不公平感を生み、組織への不信とモチベーションの低下を招きます。
モチベーションが低い組織では、当然ながらリスクに対する感度も鈍くなり、ミスやトラブルが起こりやすくなります。
正しい行動が正しく評価される仕組みが、自律的なリスク管理文化を醸成する
リスクに強い組織では、評価基準が明確に定義され、全職員に公開されています。そして、その評価項目の中には、「定められた安全手順を遵守したか」「インシデントを速やかに報告し、再発防止に貢献したか」「情報管理のルールを徹底したか」といった、リスク管理に関する項目が明確に含まれています。
ルールを守り、リスク回避に貢献する行動が、昇進や昇給といった形で正しく評価される。
この仕組みがあることで、職員は上司に言われなくても、自らの行動を律し、積極的にリスク管理に取り組むようになります。
これこそが、真の意味でのリスク管理文化の醸成につながるのです。
【識学式】人事マネジメントによる病院リスクの低減策
では、これまで述べてきた組織マネジメントの理論を、病院が直面する具体的なリスクに適用すると、どのような解決策が見えてくるのでしょうか。「識学」の理論に基づいた、4つのケーススタディをご紹介します。
ケーススタディ①:「採用・離職リスク」へのアプローチ
多くの病院が、採用面接で候補者の「人柄」や「やる気」といった、曖昧な基準で採用を決定してしまっています。しかし、これが採用後のミスマッチと早期離職の大きな原因となっています。
採用時のミスマッチを防ぐ「役割定義書」の作成
識学では、まず採用するポジションに求める「役割」を具体的に定義した「役割定義書」を作成します。そこには、「どのような業務を、どのような権限と責任のもとで、どのような状態にすることを目指すのか」が、数値目標を含めて明確に記述されます。
面接では、この役割定義書を基に、候補者がその役割を遂行できるスキルと経験を持っているか、事実ベースで確認します。
これにより、「良い人だと思ったのに、入職してみたら期待した働きをしてくれなかった」というミスマッチを未然に防ぎます。
離職の真因を特定し、組織課題を解決する
職員が離職する際、「家庭の事情で」といった当たり障りのない理由が語られることがほとんどですが、その裏には組織に対する何らかの不満が隠されています。識学に基づく組織では、評価制度や役割が明確であるため、「評価に納得できない」「将来のキャリアが見えない」といった離職の真因が特定しやすくなります。
そして、その原因が個人の問題なのか、組織の仕組みの問題なのかを切り分け、仕組みに問題があれば、それを改善することで、根本的な離職率の低下を目指します。
ケーススタディ②:「労務リスク(ハラスメント等)」へのアプローチ
職場におけるハラスメントは、個人の倫理観の欠如だけで発生するのではありません。むしろ、それを許容してしまう組織の構造に、より大きな問題があります。
ハラスメントが生まれる温床は「公私混同」と「感情論」
上司が部下に対して、「飲み会に参加しないから評価を下げる」「俺の若い頃はもっと大変だった」といった、業務とは無関係な私情や感情論を持ち込むこと。これがハラスメントの温床です。組織のルールよりも個人の感情が優先される「公私混同」の状態では、健全な組織運営は不可能です。
私情を挟ませない、明確なルールに基づく組織運営
識学では、上司と部下の関係を「役割」として明確に定義し、すべてのコミュニケーションは、その役割を果たすためのものに限定されます。上司が部下を指導・評価する際は、定められたルールと事実に基づいてのみ行われ、そこに個人的な感情が入り込む余地はありません。
「〇〇というルールに違反したため、評価はこうなります」というように、すべてがルールベースで運営されることで、ハラスメントが発生しにくい、ドライで機能的な組織文化が構築されます。
ケーススタディ③:「情報漏洩リスク」へのアプローチ
個人情報の漏洩は、「うっかりミス」や「気の緩み」といった、個人の意識の問題として捉えられがちです。しかし、識学では、それすらも仕組みによって防ぐことができると考えます。
「気の緩み」や「うっかりミス」を仕組みで防ぐ
ミスは誰にでも起こり得ます。重要なのは、ミスが起こりにくい環境を仕組みとして作ることです。例えば、「患者情報を含むUSBメモリは、貸出台帳に記録し、〇時までに必ず返却する」「私物のスマートフォンを院内に持ち込む際は、カメラレンズにシールを貼る」といった、具体的で誰にでも実行可能なルールを設定します。
情報管理に関するルールの設定と、結果責任の明確化
さらに重要なのが、そのルールに違反した場合の結果責任を明確に定めておくことです。「ルールに違反し、情報漏洩を発生させた場合は、就業規則に基づき懲戒処分の対象となる」。
この結果責任が明確であるからこそ、職員はルールを「守らなければならないもの」として強く認識し、行動が変化します。
「意識を高める」のではなく、「行動を変えざるを得ない環境」を作ることが、最も確実なリスク対策なのです。
ケーススタディ④:「医療過誤リスク」へのアプローチ
医療過誤防止策として多くの病院で導入されている「ダブルチェック」。しかし、なぜダブルチェックを行っていたにもかかわらず、ミスは見逃されてしまうのでしょうか。
ダブルチェックが機能しない本当の理由
ダブルチェックが機能しない最大の理由は、「責任の所在」が曖昧になるからです。チェックする側は「最終的には実施者が責任を持つだろう」、実施する側は「誰かがチェックしてくれるから大丈夫だろう」という、無意識の責任転嫁が生じます。
二人で見ることで、かえって一人ひとりの責任感が希薄になってしまうのです。
「誰が」「何を」「いつまでに」を徹底し、責任の所在を明確にする
識学に基づく組織では、あらゆる業務において、その最終的な結果責任者が誰であるかを一人に限定します。ダブルチェックを行う場合でも、「チェック者Aは、〇〇の項目について、△△という基準に基づき確認し、その確認結果に責任を持つ」というように、それぞれの役割と責任範囲を明確に切り分けます。
また、口頭での確認だけでなく、チェックリストへの署名など、責任の所在を記録として残すことをルール化します。
このように、すべてのプロセスにおいて責任の所在を明確にすることが、形骸化したチェック体制を機能させ、医療過誤リスクを本質的に低減させる鍵となります。
なぜ、自院だけでの組織改革は失敗するのか?
「組織マネジメントの重要性は理解できた。早速、自院で取り組んでみよう」。そう決意される経営者の方も多いかもしれません。
しかし、残念ながら、内部の力だけで本質的な組織改革を成し遂げることは、極めて困難であると言わざるを得ません。
院内の人間関係としがらみ
長年かけて形成された院内の人間関係や、特定の有力者への忖度といった「しがらみ」は、改革を進める上で大きな障壁となります。「あの先生には強く言えない」「看護部から反発されるのが怖い」といった感情が、本来あるべき正しいルールの設定や、公平な評価制度の導入を妨げます。
客観的な視点の欠如
内部の人間は、自院の組織のどこに問題があるのかを、客観的に把握することが困難です。長年当たり前だと思ってきた慣習やコミュニケーションの癖が、実は組織の生産性を著しく下げている、という事実に気づくことができないのです。
外部の専門家による、先入観のない客観的な視点があって初めて、組織の本当の課題が可視化されます。
経営者が「プレイングマネージャー」から抜け出せない
多くの院長は、優れた臨床医であると同時に、経営者としての役割も担っています。日々の診療や手術で多忙を極める中で、組織改革という、腰を据えて取り組むべきテーマに十分な時間とエネルギーを割くことは、物理的に不可能です。
結果として、改革は中途半端に終わり、現場の不信感を煽るだけに終わってしまうケースも少なくありません。
リスクに強い組織への変革を支援する、外部コンサルティングという選択肢
自院だけでの改革が困難である以上、リスクに強い組織への変革を本気で目指すのであれば、組織マネジメントの専門家である外部コンサルティングの活用が、最も現実的で効果的な選択肢となります。組織コンサルティングが提供する価値とは?
優れた組織コンサルティングは、単に知識やノウハウを提供するだけではありません。しがらみのない第三者の立場から、組織の課題を客観的に分析し、経営者に耳の痛い事実も直言します。
そして、経営者と共に改革のプランを練り上げ、現場の抵抗や反発も乗り越えながら、新しい仕組みが組織に定着するまで伴走し続けます。
経営者が一人で抱え込んでいた重荷を共に背負い、改革を断行するための強力な推進力となること。これこそが、コンサルティングが提供する最大の価値です。
失敗しないコンサルティング会社の選び方
では、数あるコンサルティング会社の中から、本当に信頼できるパートナーをどう選べばよいのでしょうか。以下の3つの基準で判断することをおすすめします。医療業界への理解度は十分か
前述の通り、病院は極めて特殊な組織です。一般的な企業向けのコンサルティング理論をそのまま持ち込むだけでは、現場の実態に合わず失敗に終わります。医療法人に対する豊富な支援実績と、その特殊性を深く理解しているコンサルティング会社を選びましょう。
一時的な改善ではなく「仕組み」を構築できるか
研修やワークショップで、一時的に職員のモチベーションを高めるだけのコンサルティングでは意味がありません。問題の根源にアプローチし、組織の「ルール」や「評価制度」といった、永続的に機能する「仕組み」を構築できる、理論的背景がしっかりとしたコンサルティング会社を選ぶべきです。
経営層から現場まで、一貫した理論で指導できるか
経営層にはAという理論を、管理職にはBという理論を、というように、階層ごとに異なる指導を行うコンサルティングでは、組織に一貫性が生まれません。院長から新人職員まで、すべての階層に対して、同じ一つのブレない理論軸で指導できる。
そうした普遍性と再現性を持つメソッドを持つ会社こそ、真に組織を変える力を持っています。
まとめ:真のリスクマネジメントは、院長の「組織」への覚悟から始まる
病院経営におけるリスクマネジメントは、もはや医療安全部門や一部の担当者だけの仕事ではありません。それは、院長がトップとしてリーダーシップを発揮し、組織のあり方を根本から見直す、極めて重要な経営戦略そのものです。
インシデントレポートの山を築き、効果の薄い研修を繰り返す日々から脱却し、すべてのリスクの根源である「組織の曖昧さ」と向き合う。
そして、明確なルールと公平な評価制度という、揺るぎない「仕組み」を組織に実装する。 そのプロセスは、決して平坦な道のりではないかもしれません。
しかし、その先にこそ、職員が安心して、誇りを持って働き続けられる、そして地域社会から真に信頼される、リスクに強い病院の未来が待っています。真のリスクマネジメントは、院長であるあなたの、「組織」と向き合う覚悟から始まるのです。