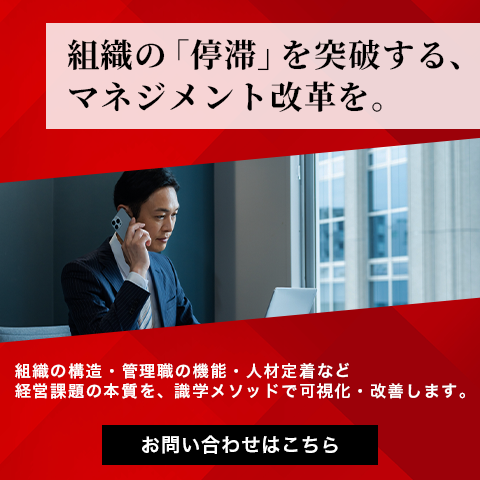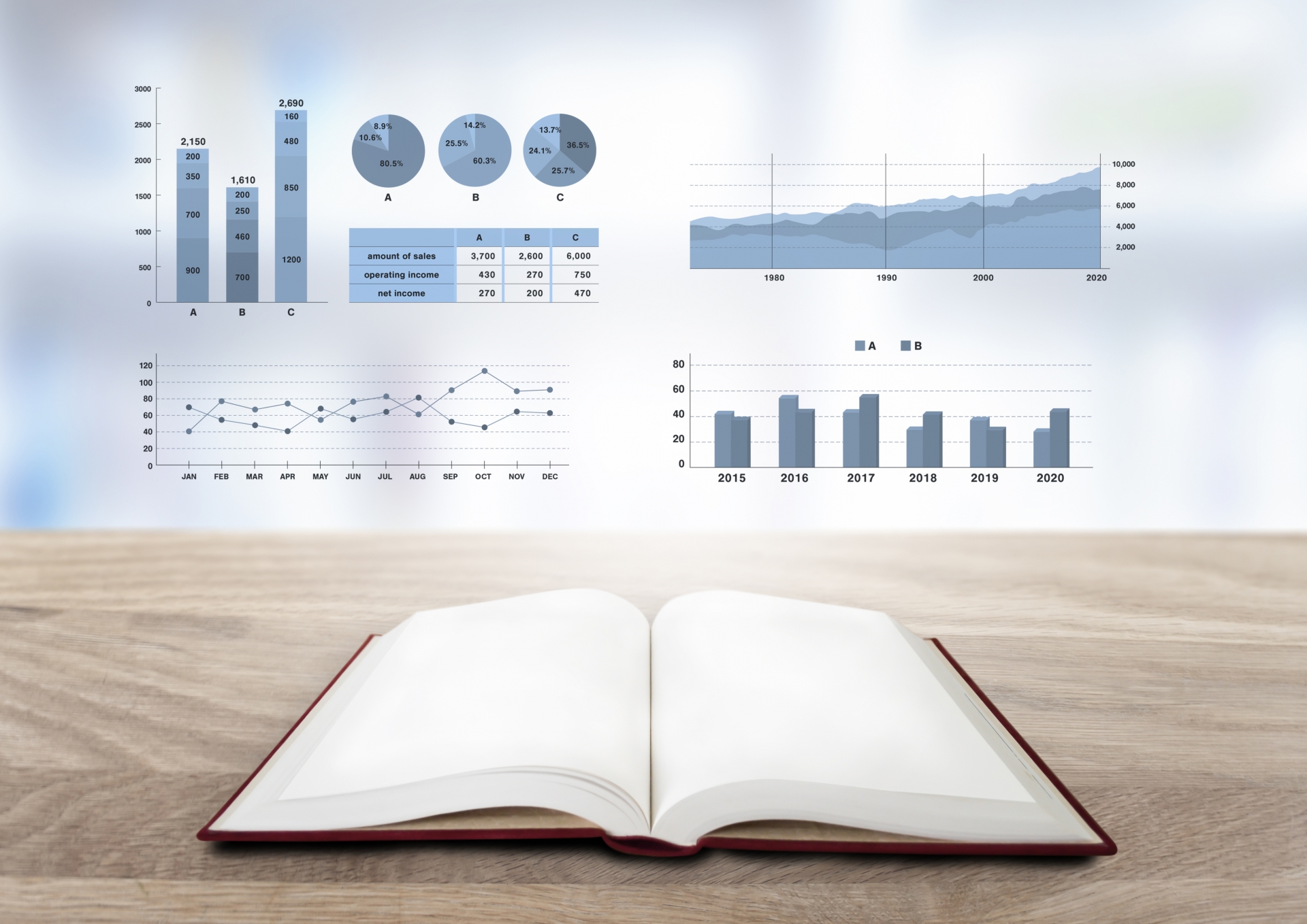
日々の診療に追われながら、人材の採用・育成、部門間の連携、そして迫り来る診療報酬改定への対応など、山積する経営課題に頭を悩ませる。
これは、現代の多くの医療法人経営者が直面している、厳しい現実ではないでしょうか。
優れた臨床医であることが、必ずしも優れた経営者であるとは限りません。
かつてのように、院長の個人的なリーダーシップや情熱だけで、複雑化した病院という組織を動かし、成長させていくことには、もはや限界が訪れています。
「本を読んでいる時間などない」。
そう思われるかもしれません。
しかし、一冊の良書との出会いは、これまで闇雲に試行錯誤を繰り返してきた時間に終止符を打ち、自院が抱える課題の本質を鋭く照らし出し、進むべき道を明確に示してくれる、何よりも価値のある「投資」となり得ます。
本記事では、多忙を極める医療法人経営者の皆様のために、なぜ今こそ組織マネジメントの本による学びが必要なのかを解き明かし、自院の課題に合わせて選ぶべき名著、そして、読書を自己満足で終わらせず、確実な組織変革へと繋げるための具体的なステップを、専門的な視点から徹底的に解説していきます。

日々の診療と経営判断に追われる中で、体系的な知識をインプットする時間を確保することは容易ではありません。
しかし、それでもなお、多忙な経営者ほど、組織マネジメントに関する古典や名著を読むべき理由が、明確に3つ存在します。
目の前の患者を救うことに全力を尽くすことは、医師として当然の責務であり、尊い行為です。
しかし、その状態に安住してしまっていては、病院という組織全体の成長は望めません。
院長の真の役割は、自らがスーパープレイヤーとして個別の問題を解決し続けることではなく、組織全体のパフォーマンスを最大化させる「仕組み」を構築し、自分が不在でも組織が自律的に動く状態を作り出すことです。
組織マネジメントの名著を読むことは、日々の臨床業務というミクロな視点から一時的に離れ、組織全体を俯瞰するマクロな視点、すなわち「経営者」としての視座を獲得するための、最も効果的なトレーニングとなります。
本を通じて、他の優れた経営者たちが、どのようにしてプレイングマネージャーから脱却し、偉大な組織を築き上げたのか、その思考の軌跡を追体験することができるのです。
このように考える経営者は少なくありません。
確かに、医療業界には特有の文化や専門性が存在します。
しかし、それは組織マネジメントの「原理・原則」が通用しない理由にはなりません。
むしろ逆です。
専門性が高いがゆえに生まれやすいセクショナリズムや、個人の経験則に頼りがちな業務プロセス、そして生命を預かるというストレスフルな環境。
こうした病院組織特有の課題を解決するためにこそ、時代や業種を超えて通用する、組織運営の普遍的な原理・原則を学ぶことが不可欠なのです。
なぜ、人は動くのか。なぜ、組織は停滞するのか。
どうすれば、個人の集まりを、一つの目標に向かう強力なチームへと変えることができるのか。
組織マネジメントの名著には、これらの根源的な問いに対する、先人たちの知恵と洞察が凝縮されています。
しかし、その前に、経営者自身が組織マネジメントに関する基本的な知識と思考のフレームワークを持っていなければ、コンサルタントの提案を正しく評価し、効果的に活用することはできません。
「なんとなく、うちの組織は風通しが悪い」「職員のモチベーションが低い気がする」。
このような曖昧な問題意識のままでは、コンサルタントに的確な相談をすることも、提案された解決策が本当に自院に適しているのかを判断することも困難です。
組織マネジメントの本を読むことは、自院が抱える漠然とした課題を、具体的なマネジメント用語(例えば、「指示命令系統の不備」「評価制度の機能不全」「役割定義の曖-昧さ」など)で捉え直し、言語化するための「共通言語」を与えてくれます。
この共通言語を持つことで初めて、自院の課題を客観的に分析し、外部の専門家とも対等に議論し、最適な解決策を共創していくことが可能になるのです。
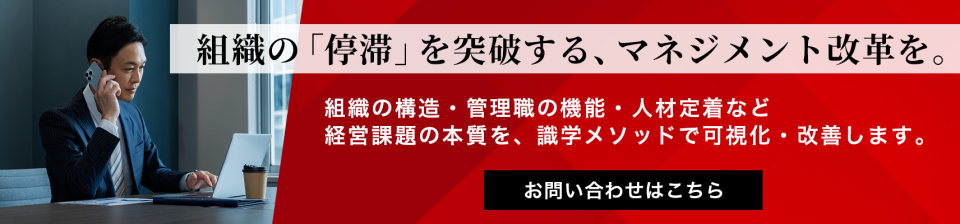
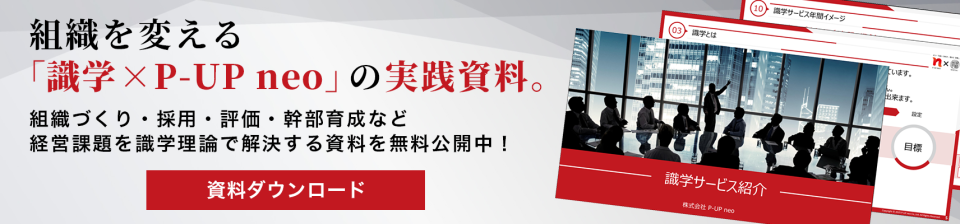

一口に組織マネジメントの本と言っても、そのテーマやレベルは様々です。
自院の組織が現在どのようなステージにあり、どのような課題に直面しているのかによって、読むべき本は異なります。
ここでは、経営者の課題認識のレベルに合わせて、3つのステージに分けて本の選び方を解説します。
このような、課題認識の初期段階にいる経営者におすすめなのが、組織マネジメントの全体像や、その根底に流れる基本的な考え方を、平易な言葉で解説してくれる入門書です。
このステージで重要なのは、細かな手法論に深入りするのではなく、まずは「良い組織とは何か」「なぜ組織には問題が発生するのか」といった、本質的な問いに対する自分なりの答えを見つけることです。
会議のやり方を変えたい」。
このように、解決すべき組織課題がある程度明確になっており、そのための具体的な解決策やツールを探している経営者には、より実践的な内容を扱った本が適しています。
目標管理制度(MBO)の具体的な設定方法、1on1ミーティングの進め方、人事評価シートの作り方、効果的な会議のファシリテーション術など、明日からでも自院で試せるような、具体的なノウハウやフレームワークが解説されている本を選びましょう。
例えば、人の動機付けに関する深層心理を扱った本、優れたリーダーに共通する思考法や意思決定プロセスを分析した本、あるいは、イノベーションが生まれ続ける組織文化をいかにして醸成するか、といったテーマを掘り下げた本などです。
これらの本は、すぐに実践できるノウハウを提供してくれるわけではないかもしれません。
しかし、経営者自身のリーダーシップ観や組織観を根底から揺さぶり、より高い視座から物事を考えるための、深い洞察とインスピレーションを与えてくれるはずです。
ここでは、前述した3つのステージを横断し、あらゆるレベルの医療法人経営者にとって、必ずや大きな気づきをもたらすであろう、不朽の名著から最新のベストセラーまで、厳選した3冊をご紹介します。
【実践編】に位置づけられる本書は、特に若手・中堅職員の育成や、彼らの主体性をいかに引き出すか、という課題に悩む経営者にとって、強力な武器となります。
本書が提唱する1on1ミーティングは、上司が部下を評価したり、業務の進捗を管理したりするための、従来の「面談」とは全く異なります。
それは、部下の経験学習を促進し、その成長を支援するために、上司が部下の「鏡」となり、対話を通じて内省を促すための時間です。
病院組織においては、日々の業務に追われ、先輩が後輩へ、あるいは上司が部下へ、じっくりと向き合う時間を確保することが極めて困難です。
その結果、多くの若手職員は、十分な指導やフィードバックを受けられないまま放置され、成長実感を得られずに離職していく、という悲劇が繰り返されています。
【思考編】に位置づけられる本書は、小手先のテクニックではなく、経営者として、そしてマネージャーとして持つべき「哲学」と「原理・原則」を、深く、そして体系的に教えてくれます。
ドラッカーは、「企業の目的は顧客の創造である」と定義しました。
これを病院経営に置き換えるならば、「病院の目的は、地域社会における患者価値の創造である」と言えるでしょう。
本書は、この崇高な目的を達成するために、組織が、そしてマネージャーが、果たすべき役割は何かを、徹底的に問いかけます。
【入門編】でありながら、その内容は極めて【実践編】に近く、特にプレイングマネージャーから脱却できずに悩む多くの医療法人経営者にとって、まさに目から鱗が落ちるような、衝撃的な気づきを与えてくれます。
しかし、その感動や気づきを、実際の組織変革へと繋げられなければ、それは単なる「自己満足」で終わってしまいます。
読書で得た知識を、血肉に変え、組織を動かす力へと転換するための、3つの具体的なステップをご紹介します。
ただ漠然と「勉強になった」で終わらせるのではなく、読書ノートやメモを用意し、「この本で解説されている〇〇という理論は、当院における△△という問題(例えば、看護部とリハビリ部の連携不足)の根本原因を説明している」「著者が指摘するリーダーの誤った行動パターンは、まさに自分自身のことだ」というように、具体的な事象と理論を紐づけて、自分の言葉で言語化していきます。
このプロセスを通じて、これまで漠然と感じていた組織の課題が、マネジメント理論というフレームワークの上で、明確な「構造」として見えてくるようになります。
課題を正しく名付けること。それが、解決に向けた第一歩です。
まずは、経営者が直接的に関与できる、一つの部門やチーム(例えば、医事課や、特定の病棟など)を選び、そこで「実験的」に実践してみることをお勧めします。
また、改革を進めようとしても、院内の抵抗やしがらみに阻まれ、思うように前に進めないこともあるでしょう。
そのような時、非常に有効なのが、客観的な視点を持つ外部の専門家を「壁打ち相手」として活用することです。
組織マネジメントのコンサルタントは、数多くの組織の変革を支援してきたプロフェッショナルです。
彼らは、経営者が言語化した課題を、より深く、そして構造的に整理し、その解決策を共に考えてくれます。
また、しがらみのない第三者の立場から、院内の抵抗勢力に対する説得や、改革を断行するための後押しをしてくれる、心強いパートナーともなり得ます。

本記事では、医療法人経営者の皆様が、組織マネジメントという、困難でありながらも避けては通れないテーマと向き合うための、読書による学びの重要性とその具体的な方法論について解説してきました。
多忙な日常の中で、腰を据えて本を読む時間を確保することは、確かに一つの挑戦かもしれません。
しかし、その一冊が、これまで何年も解決できなかった組織の根深い問題を解き明かす鍵となったり、経営者としての自身のあり方を根本から見つめ直すきっかけとなったりする可能性を秘めています。
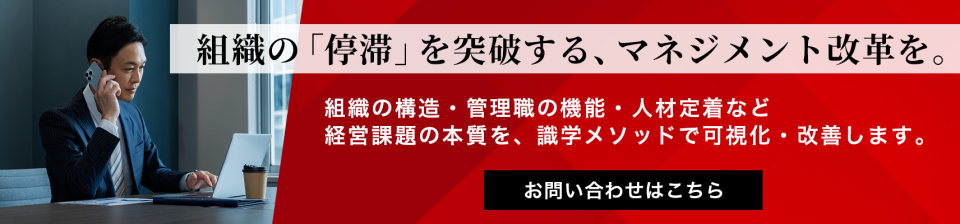
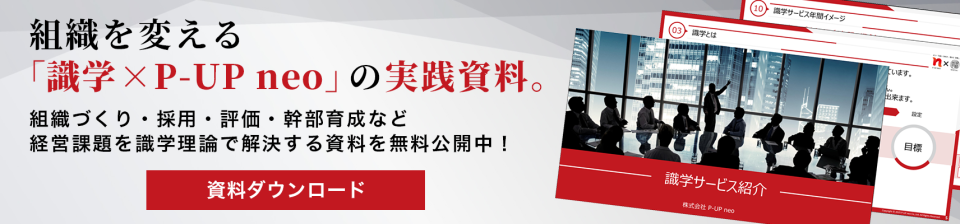

これは、現代の多くの医療法人経営者が直面している、厳しい現実ではないでしょうか。
優れた臨床医であることが、必ずしも優れた経営者であるとは限りません。
かつてのように、院長の個人的なリーダーシップや情熱だけで、複雑化した病院という組織を動かし、成長させていくことには、もはや限界が訪れています。
「本を読んでいる時間などない」。
そう思われるかもしれません。
しかし、一冊の良書との出会いは、これまで闇雲に試行錯誤を繰り返してきた時間に終止符を打ち、自院が抱える課題の本質を鋭く照らし出し、進むべき道を明確に示してくれる、何よりも価値のある「投資」となり得ます。
本記事では、多忙を極める医療法人経営者の皆様のために、なぜ今こそ組織マネジメントの本による学びが必要なのかを解き明かし、自院の課題に合わせて選ぶべき名著、そして、読書を自己満足で終わらせず、確実な組織変革へと繋げるための具体的なステップを、専門的な視点から徹底的に解説していきます。
なぜ今、医療法人経営者にこそ「組織マネジメントの本」による学びが必要なのか

日々の診療と経営判断に追われる中で、体系的な知識をインプットする時間を確保することは容易ではありません。
しかし、それでもなお、多忙な経営者ほど、組織マネジメントに関する古典や名著を読むべき理由が、明確に3つ存在します。
プレイングマネージャーから脱却し、「経営者」の視座を持つために
多くの院長は、自身も一人の臨床医として現場の最前線に立ち続ける「プレイングマネージャー」です。目の前の患者を救うことに全力を尽くすことは、医師として当然の責務であり、尊い行為です。
しかし、その状態に安住してしまっていては、病院という組織全体の成長は望めません。
院長の真の役割は、自らがスーパープレイヤーとして個別の問題を解決し続けることではなく、組織全体のパフォーマンスを最大化させる「仕組み」を構築し、自分が不在でも組織が自律的に動く状態を作り出すことです。
組織マネジメントの名著を読むことは、日々の臨床業務というミクロな視点から一時的に離れ、組織全体を俯瞰するマクロな視点、すなわち「経営者」としての視座を獲得するための、最も効果的なトレーニングとなります。
本を通じて、他の優れた経営者たちが、どのようにしてプレイングマネージャーから脱却し、偉大な組織を築き上げたのか、その思考の軌跡を追体験することができるのです。
専門職集団を率いるための、普遍的な「原理・原則」を学ぶ
「病院は、医師や看護師といった専門職の集まりだから、一般企業のマネジメント論は通用しない」。このように考える経営者は少なくありません。
確かに、医療業界には特有の文化や専門性が存在します。
しかし、それは組織マネジメントの「原理・原則」が通用しない理由にはなりません。
むしろ逆です。
専門性が高いがゆえに生まれやすいセクショナリズムや、個人の経験則に頼りがちな業務プロセス、そして生命を預かるというストレスフルな環境。
こうした病院組織特有の課題を解決するためにこそ、時代や業種を超えて通用する、組織運営の普遍的な原理・原則を学ぶことが不可欠なのです。
なぜ、人は動くのか。なぜ、組織は停滞するのか。
どうすれば、個人の集まりを、一つの目標に向かう強力なチームへと変えることができるのか。
組織マネジメントの名著には、これらの根源的な問いに対する、先人たちの知恵と洞察が凝縮されています。
外部コンサルタントに頼る前に、自院の課題を言語化する「共通言語」を得る
組織の課題解決のために、外部の経営コンサルタントの活用を検討することもあるでしょう。しかし、その前に、経営者自身が組織マネジメントに関する基本的な知識と思考のフレームワークを持っていなければ、コンサルタントの提案を正しく評価し、効果的に活用することはできません。
「なんとなく、うちの組織は風通しが悪い」「職員のモチベーションが低い気がする」。
このような曖昧な問題意識のままでは、コンサルタントに的確な相談をすることも、提案された解決策が本当に自院に適しているのかを判断することも困難です。
組織マネジメントの本を読むことは、自院が抱える漠然とした課題を、具体的なマネジメント用語(例えば、「指示命令系統の不備」「評価制度の機能不全」「役割定義の曖-昧さ」など)で捉え直し、言語化するための「共通言語」を与えてくれます。
この共通言語を持つことで初めて、自院の課題を客観的に分析し、外部の専門家とも対等に議論し、最適な解決策を共創していくことが可能になるのです。
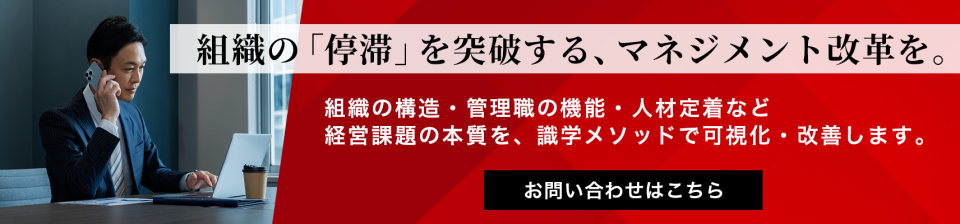
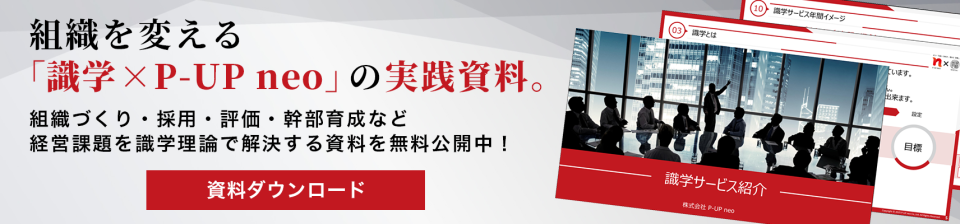
【課題別】自院の状況に合わせて選ぶ、組織マネジメント本の選び方

一口に組織マネジメントの本と言っても、そのテーマやレベルは様々です。
自院の組織が現在どのようなステージにあり、どのような課題に直面しているのかによって、読むべき本は異なります。
ここでは、経営者の課題認識のレベルに合わせて、3つのステージに分けて本の選び方を解説します。
ステージ①【入門編】:組織課題の全体像と本質を理解したい経営者向け
「何から手をつければいいのか、正直わからない」「組織の問題は感じているが、それが何なのかを明確に言語化できない」。このような、課題認識の初期段階にいる経営者におすすめなのが、組織マネジメントの全体像や、その根底に流れる基本的な考え方を、平易な言葉で解説してくれる入門書です。
このステージで重要なのは、細かな手法論に深入りするのではなく、まずは「良い組織とは何か」「なぜ組織には問題が発生するのか」といった、本質的な問いに対する自分なりの答えを見つけることです。
ステージ②【実践編】:具体的なマネジメント手法や仕組みを導入したい経営者向け
「職員の離職率が高い。評価制度を見直したい」「部門間の連携が悪すぎる。会議のやり方を変えたい」。
このように、解決すべき組織課題がある程度明確になっており、そのための具体的な解決策やツールを探している経営者には、より実践的な内容を扱った本が適しています。
目標管理制度(MBO)の具体的な設定方法、1on1ミーティングの進め方、人事評価シートの作り方、効果的な会議のファシリテーション術など、明日からでも自院で試せるような、具体的なノウハウやフレームワークが解説されている本を選びましょう。
ステージ③【思考編】:次世代のリーダー育成や、持続可能な組織文化を醸成したい経営者向け
組織がある程度成熟し、目先の課題解決だけでなく、5年後、10年後を見据えた、より持続可能で強靭な組織作りを目指すステージにいる経営者には、より高度で、時に哲学的なテーマを扱う本をおすすめします。例えば、人の動機付けに関する深層心理を扱った本、優れたリーダーに共通する思考法や意思決定プロセスを分析した本、あるいは、イノベーションが生まれ続ける組織文化をいかにして醸成するか、といったテーマを掘り下げた本などです。
これらの本は、すぐに実践できるノウハウを提供してくれるわけではないかもしれません。
しかし、経営者自身のリーダーシップ観や組織観を根底から揺さぶり、より高い視座から物事を考えるための、深い洞察とインスピレーションを与えてくれるはずです。
組織マネジメントのおすすめ本3選
それでは、具体的にどのような本を読めばよいのでしょうか。ここでは、前述した3つのステージを横断し、あらゆるレベルの医療法人経営者にとって、必ずや大きな気づきをもたらすであろう、不朽の名著から最新のベストセラーまで、厳選した3冊をご紹介します。
「シリコンバレー式 最強の育て方」世古詞一著
本書は、Googleなどで採用され、大きな成果を上げている人材育成の手法「1on1ミーティング」について、その具体的な実践方法を解説した一冊です。【実践編】に位置づけられる本書は、特に若手・中堅職員の育成や、彼らの主体性をいかに引き出すか、という課題に悩む経営者にとって、強力な武器となります。
本書が提唱する1on1ミーティングは、上司が部下を評価したり、業務の進捗を管理したりするための、従来の「面談」とは全く異なります。
それは、部下の経験学習を促進し、その成長を支援するために、上司が部下の「鏡」となり、対話を通じて内省を促すための時間です。
病院組織においては、日々の業務に追われ、先輩が後輩へ、あるいは上司が部下へ、じっくりと向き合う時間を確保することが極めて困難です。
その結果、多くの若手職員は、十分な指導やフィードバックを受けられないまま放置され、成長実感を得られずに離職していく、という悲劇が繰り返されています。
「マネジメント」P.F.ドラッカー著
「経営学の父」と称されるピーター・F・ドラッカー。その思想の集大成とも言える本書は、時代を超えてすべての経営者が読むべき、組織マネジメントの「聖書」です。【思考編】に位置づけられる本書は、小手先のテクニックではなく、経営者として、そしてマネージャーとして持つべき「哲学」と「原理・原則」を、深く、そして体系的に教えてくれます。
ドラッカーは、「企業の目的は顧客の創造である」と定義しました。
これを病院経営に置き換えるならば、「病院の目的は、地域社会における患者価値の創造である」と言えるでしょう。
本書は、この崇高な目的を達成するために、組織が、そしてマネージャーが、果たすべき役割は何かを、徹底的に問いかけます。
「リーダーの仮面 「いちプレーヤー」から「マネジャー」に頭を切り替える思考法」安藤 広大著
本書は、近年、多くの経営者から注目を集める組織コンサルティング会社「識学」の代表である著者が、そのマネジメント理論のエッセンスを、物語形式でわかりやすく解説したベストセラーです。【入門編】でありながら、その内容は極めて【実践編】に近く、特にプレイングマネージャーから脱却できずに悩む多くの医療法人経営者にとって、まさに目から鱗が落ちるような、衝撃的な気づきを与えてくれます。
読書を「自己満足」で終わらせない。知識を組織変革に繋げる3つのステップ
素晴らしい本との出会いは、時に経営者の人生を変えるほどのインパクトを持ちます。しかし、その感動や気づきを、実際の組織変革へと繋げられなければ、それは単なる「自己満足」で終わってしまいます。
読書で得た知識を、血肉に変え、組織を動かす力へと転換するための、3つの具体的なステップをご紹介します。
ステップ①:自院の組織課題と、本の理論を結びつけて言語化する
本を読みながら、あるいは読み終えた後に、必ず行うべきなのが、「自院の現状」と「本の理論」を結びつける作業です。ただ漠然と「勉強になった」で終わらせるのではなく、読書ノートやメモを用意し、「この本で解説されている〇〇という理論は、当院における△△という問題(例えば、看護部とリハビリ部の連携不足)の根本原因を説明している」「著者が指摘するリーダーの誤った行動パターンは、まさに自分自身のことだ」というように、具体的な事象と理論を紐づけて、自分の言葉で言語化していきます。
このプロセスを通じて、これまで漠然と感じていた組織の課題が、マネジメント理論というフレームワークの上で、明確な「構造」として見えてくるようになります。
課題を正しく名付けること。それが、解決に向けた第一歩です。
ステップ②:まずは一つの部門・チームから、スモールスタートで実践してみる
本で学んだ新しいマネジメント手法を、いきなり病院全体で導入しようとするのは、リスクが高く、現場の抵抗も大きくなります。まずは、経営者が直接的に関与できる、一つの部門やチーム(例えば、医事課や、特定の病棟など)を選び、そこで「実験的」に実践してみることをお勧めします。
ステップ③:客観的な視点を持つ外部の専門家(壁打ち相手)を見つける
本を読んでも、「理論は理解できたが、これを自院の複雑な状況に、具体的にどう応用すればよいのかわからない」という壁に突き当たることは、少なくありません。また、改革を進めようとしても、院内の抵抗やしがらみに阻まれ、思うように前に進めないこともあるでしょう。
そのような時、非常に有効なのが、客観的な視点を持つ外部の専門家を「壁打ち相手」として活用することです。
組織マネジメントのコンサルタントは、数多くの組織の変革を支援してきたプロフェッショナルです。
彼らは、経営者が言語化した課題を、より深く、そして構造的に整理し、その解決策を共に考えてくれます。
また、しがらみのない第三者の立場から、院内の抵抗勢力に対する説得や、改革を断行するための後押しをしてくれる、心強いパートナーともなり得ます。
良書との出会いは、病院経営の未来を変える第一歩

本記事では、医療法人経営者の皆様が、組織マネジメントという、困難でありながらも避けては通れないテーマと向き合うための、読書による学びの重要性とその具体的な方法論について解説してきました。
多忙な日常の中で、腰を据えて本を読む時間を確保することは、確かに一つの挑戦かもしれません。
しかし、その一冊が、これまで何年も解決できなかった組織の根深い問題を解き明かす鍵となったり、経営者としての自身のあり方を根本から見つめ直すきっかけとなったりする可能性を秘めています。
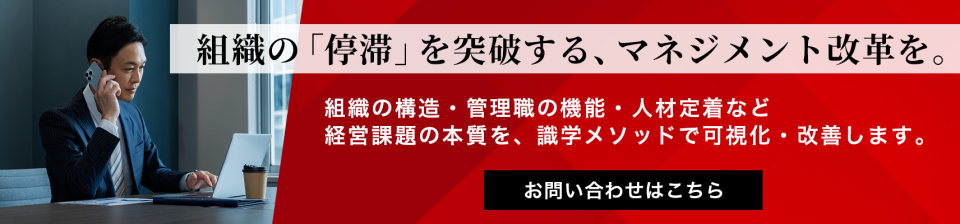
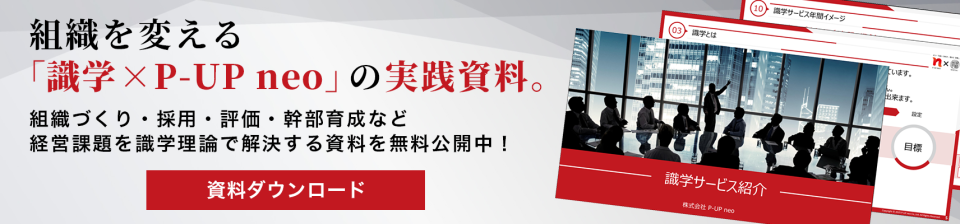
本気の組織改革なら
「識学 × P-UP neo」
この記事の監修者

有馬大悟 Arima Daigo
株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント
《資格》
識学認定コンサルタント
《プロフィール》
慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。
社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。
他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。
非営利法人における初年度更新率=満足度は100%