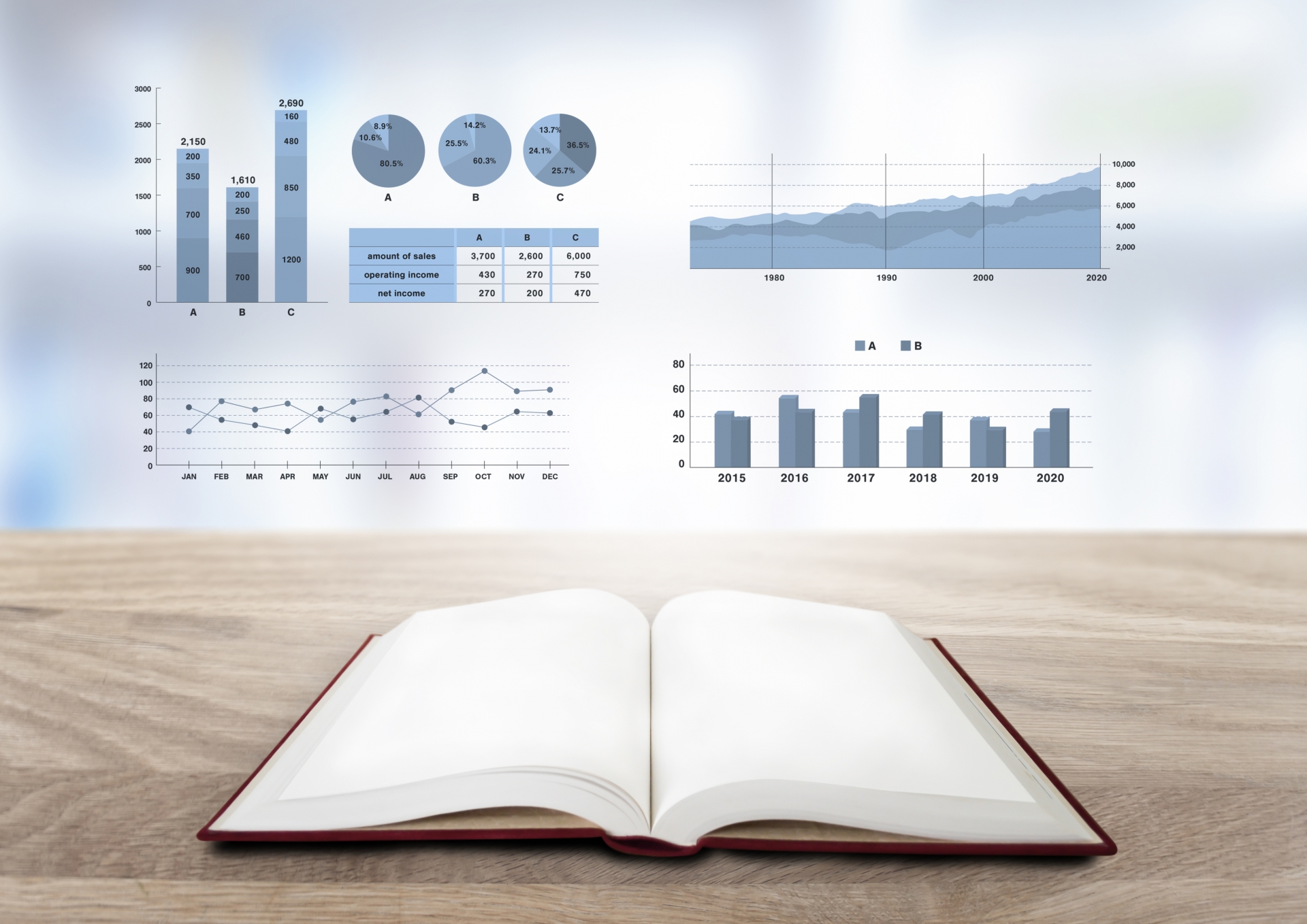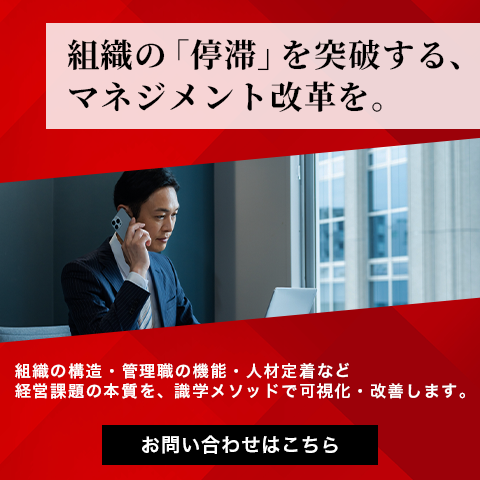「職員には、もっと主体的に動いてほしい」
「なぜ、あれほど伝えたはずの指示が、現場の末端まで浸透しないのだろうか」
「部門間の連携が悪く、いつも同じような問題が繰り返されている」
日々の診療と並行して、組織の舵取りという重責を担う院長・経営者の皆様の中には、このような悩みを抱え、自身のマネジメント能力に限界を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
多くの院長は、その卓越した臨床能力とリーダーシップで組織を牽引しようと奮闘します。
しかし、院長の情熱や「頑張り」だけでは、組織は動きません。
むしろ、院長が頑張れば頑張るほど、職員は指示待ちになり、組織の自律性は失われていくという皮肉な現実があります。
真の病院経営におけるマネジメントとは、院長個人のスキルやカリスマ性に依存するものではありません。
それは、院長の指示が自動的に現場の隅々まで浸透し、職員一人ひとりが自らの役割を理解して、組織の目標達成に向けて自律的に動くための「仕組み」を構築し、運用することに他なりません。
本記事では、多くの病院経営者が陥りがちなマネジメントの罠を解き明かし、院長の指示が浸透しない構造的な原因を分析します。
その上で、組織が自律的に動くための本質的な「仕組み」の作り方を、具体的なステップに沿って徹底的に解説していきます。
医師、看護師、薬剤師、技師、事務職員といった、多種多様な専門性を持つ人材が集まり、それぞれが複雑に連携することで、初めて質の高い医療が提供されます。
この複雑な組織を、院長が日々の細かな業務にまで介入し、マイクロマネジメントしようとすれば、どうなるでしょうか。
院長自身の時間は瞬く間になくなり、本来注力すべき経営戦略の立案や、高度な診療といった、院長にしかできない重要な業務に時間を割けなくなります。
さらに深刻なのは、組織への影響です。
院長の指示がなければ何も決まらない、動けないという状況が常態化すれば、職員は次第に自分で考えることをやめ、「指示待ち」の状態に陥ります。
中間管理職は育たず、現場の主体性は失われ、組織全体の成長は完全に停滞してしまうでしょう。
もし、自院のマネジメントが「院長の頑張り」によって、かろうじて成り立っている状態であるならば、それは持続可能性の観点から極めて危険なシグナルです。
院長が体調を崩したり、退任したりした瞬間に、組織が崩壊するリスクを常に孕んでいるのです。

「院長個人の頑張り」に依存する経営は、なぜ生まれてしまうのでしょうか。
そこには、多くの善良で有能な院長たちが、知らず知らずのうちにはまってしまう、3つの典型的なマネジメントの罠が存在します。
こうした「カリスマ性」を持つ院長は、確かに組織を強力に牽引することができます。
職員は院長を尊敬し、その一言一句に耳を傾け、高いモチベーションで業務に取り組むでしょう。
しかし、このマネジメントスタイルは、諸刃の剣です。
組織の求心力が院長個人に集中しすぎると、職員は「院長のために」働くようになり、組織のルールや目標のために働くという意識が希薄になります。
院長の価値観が、組織の公式なルールよりも優先されてしまうのです。
また、院長の意向を忖度するあまり、健全な意見交換が行われなくなり、組織の意思決定に客観性が失われる危険性もあります。
そして何より、その院長がいなくなった後、組織は拠り所を失い、空中分解してしまうリスクを常に抱えることになります。
名医であればあるほど、患者は院長を頼り、現場も院長の判断を求めます。
しかし、院長の本来の役割は、自らが最高のプレイヤーであり続けることではありません。
組織全体のパフォーマンスを最大化させる「最高の監督(マネージャー)」であることです。
プレイヤーとしての業務に時間を奪われ、マネジメント、すなわち「組織の仕組み作り」を怠れば、院長がいる間は現場が回っても、組織としての成長は望めません。
むしろ、院長が現場に介入しすぎることで、中間管理職の権限が侵され、指示命令系統が混乱し、組織全体の生産性を低下させているケースすら少なくないのです。
業績が上がらない、あるいは組織に問題が発生した際、その原因を職員の「やる気」や「意識」といった、目に見えない感情的な要素に求めてしまう。
これもまた、多くのリーダーが陥る罠です。
「もっと頑張れ」という精神論や、「君ならできると信じている」といった期待の言葉は、一時的に職員を鼓舞する効果はあるかもしれません。
しかし、それによって組織が持続的に変わることはありません。
なぜなら、人の感情は移ろいやすく、客観的な基準がないため、マネジメントの拠り所としては極めて不安定だからです。
「頑張り」の基準は人それぞれであり、「信頼」という言葉だけでは、具体的に何をすべきかが伝わりません。
感情で人を動かそうとするマネジメントは、再現性がなく、組織に無用な「気遣い」や「忖度」といった、非生産的なコミュニケーションを生み出す温床となります。
この問題は、院長の伝え方が悪いからでも、職員の理解力がないからでもありません。
その原因は、組織の「構造」そのものに潜んでいます。
院長が良かれと思って発した指示が、受け手によって全く異なる解釈をされ、期待とは違う結果を生んでしまう。
これは、病院組織において日常的に見られる光景です。
院長がイメージする「いい感じ」とは、「3ヶ月後には、独り立ちして夜勤に入れるレベル」かもしれません。
しかし、看護部長は「まずは一年かけて、じっくり基礎を教えること」が「いい感じ」だと解釈するかもしれません。
この解釈のズレが、後になって「なぜ、まだ独り立ちできないんだ」「いや、今は基礎を固める時期です」といった、不毛な対立を生み出します。
さらに問題なのは、指示が曖昧であるために、結果に対する責任の所在も不明確になることです。
目標が未達に終わった際、「指示が曖昧だったからだ」「いや、受け手の解釈が間違っている」といった水掛け論に発展し、誰も責任を取らない、という事態を招きます。
この時、看護部は「それはソーシャルワーカー(MSW)の仕事だ」と考え、MSWは「まずは主治医の退院許可がなければ動けない」と考え、リハビリ部門は「退院後の生活を見据えたリハビリ計画は、看護部からの情報提供があってこそだ」と考える。
このように、各部門が「自分の仕事の範囲はここまで」と線引きし、その範囲外の業務に対しては責任を負おうとしない。
これがセクショリナズムの正体です。
この問題の根源は、職員の協調性の欠如にあるのではありません。
「退院支援」という一つの目標を達成するために、それぞれの部門、それぞれの役職が、具体的に「何を」「どこまで」行う責任があるのか、その役割分担が組織のルールとして明確に定義されていないことに、構造的な原因があるのです。
院長の指示が現場で実行されない最大の理由は、その指示された行動が、職員自身の評価に直結していないからです。
なぜなら、それを頑張っても、自分の給与や昇進には直接影響しないからです。
院長のビジョンや指示は、それがいかに崇高なものであっても、職員一人ひとりの評価、そして処遇にまで落とし込まれ、連動していなければ、単なる「お題目」で終わってしまいます。
指示を浸透させるためには、その指示通りの行動が、職員にとって最も「得」である、という仕組みを作ることが不可欠なのです。
その答えは、マネジメントの捉え方を、院長個人の「スキル」や「リーダーシップ」といった属人的なものから、組織を動かすための客観的な「仕組み」へと、根本的に転換させることにあります。
そのためには、個人の能力や感情に依存するのではなく、誰もが同じように理解し、従うことができる、明確で公平な「仕組み」によって組織を運営する必要があります。
その仕組みとは、具体的には「明確な役割定義」「曖昧さを排除したルール」、そして「公平な評価制度」という、3つの柱から成り立っています。
この3つが有機的に連動することで、組織はまるで精密機械のように、機能的かつ自律的に動き始めるのです。
むしろ、職員を日々の業務における「迷い」から解放し、本来の業務に集中させるための、強力な拠り所となるものです。
「この場合、誰に報告すればいいのだろうか」「どこまでが自分の権限で決定していいことなのだろうか」。
こうした迷いは、職員の思考を停止させ、業務の遅延や、責任のなすりつけ合いを生み出します。
報告・連絡・相談の経路、会議の運営方法、業務の承認プロセスといった、組織運営のあらゆる側面において、明確なルールが定められていれば、職員は迷うことなく、迅速かつ正確に行動することができます。
ルールは、組織の血流をスムーズにする、生命線なのです。
院長が掲げる経営ビジョンや年度目標を、部門目標、そして個人目標へとブレークダウンし、その達成度を評価の最も重要な基準とする。
そして、その評価結果が、昇給、賞与、昇進といった処遇に、明確なルールに基づいて反映される。
この仕組みを構築することで、職員一人ひとりの日々の行動が、組織全体の目標達成と一直線に結びつきます。
職員は、院長のビジョンを「自分事」として捉え、その実現に貢献することが、自らの評価を高める最善の道であると理解します。
評価制度とは、院長の思想を、組織の隅々にまで浸透させるための、最強のコミュニケーションツールなのです。
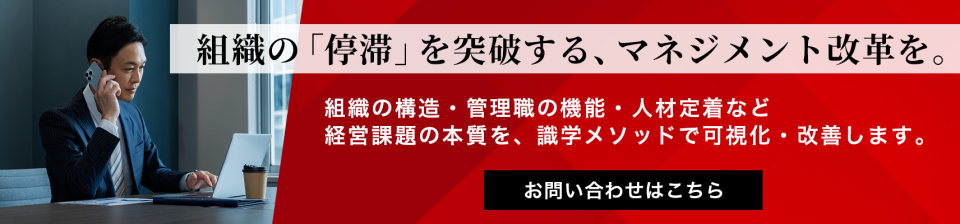
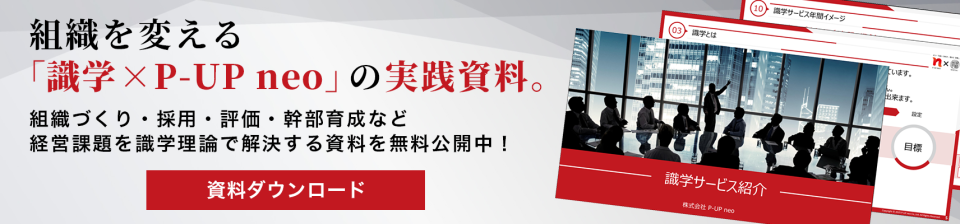

「仕組み」によるマネジメントへの転換は、具体的にどのような手順で進めていけばよいのでしょうか。
ここでは、強い病院組織を作るための改革を、3つのステップに分けて解説します。
まずは、組織図を基に、院内に存在するすべての「位置(役職)」を洗い出します。
そして、それぞれの役職について、「現在、誰が、どのような業務を行っているか」を客観的な事実として可視化します。
本来であれば、各職員は直属の上司にのみ報告し、指示を仰ぐべきですが、実際には、院長が中間管理職を飛び越えて現場に指示を出したり、部門間で非公式な指示系統が生まれていたり、といった混乱が生じているケースが多くあります。
この「指揮命令の混乱」こそが、組織の生産性を著しく下げている元凶です。
まずは、この実態を正確に把握することが重要です。
例えば、「看護部長」の役割は、「看護部全体の労務管理と、年度目標として設定された看護サービスの品質指標を達成することに、最終的な結果責任を負う」といった具合です。
この役割定義が、以降のすべての改革の土台となります。
しかし、それらが守られていないとすれば、その原因は大きく二つ考えられます。
一つは、ルールの内容が「~するよう努める」「~を心がける」といった曖昧な表現で書かれており、人によって解釈の余地があること。
もう一つは、ルールを破った場合の結果が明確でないため、職員にとってルールを守る必然性がないことです。
そして、最も重要なのが、そのルールが遵守されているかを、誰が、どのように監督するのか、そして、ルール違反があった場合には、どのような結果(例えば、人事評価へのマイナス反映など)が生じるのかを、あらかじめ明確に定めておくことです。
この結果責任の明確化があって初めて、ルールは組織内で実効性を持つものとなります。
新しい評価制度では、個人の主観的な「頑張り」ではなく、ステップ①で定義した「役割」を、どれだけ果たせたか、その「結果」を客観的な事実に基づいて評価する仕組みを構築します。
そして、その評価項目を期初に上司と部下が合意の上で、具体的な行動目標にまで落とし込みます。
このプロセスを通じて、職員は、自らの評価を高めるためには、日々何をすべきかを明確に認識し、自律的に行動できるようになるのです。
なぜなら、そこには内部からの改革を阻む、強力な3つの障壁が存在するからです。
長年かけて形成された院内の人間関係や、特定の有力者への忖度、そして変化を嫌う組織の慣性は、新しい仕組みを導入する上で、想像以上に強力な抵抗勢力となります。
経営者自身も、その「しがらみ」の中で物事を進めなければならず、本来あるべき理想的な改革案が、院内の力学によって骨抜きにされてしまうケースが後を絶ちません。
内部の人間にとっては「当たり前」の光景、例えば、目的が曖昧なまま毎朝行われているカンファレンスや、責任者が不在のまま進められる会議などが、実は組織の生産性を著しく下げている根本原因である、という事実に気づくことができません。
この客観的な視点の欠如が、本質的な課題を見過ごし、対症療法に終始させてしまうのです。
目の前の患者の対応に追われる中で、腰を据えて組織全体の仕組みを設計し、改革を推進していくための時間と精神的なエネルギーを確保することは、物理的に不可能です。
組織改革は、片手間でできるような簡単なものではありません。
現状分析、課題特定、解決策の立案、現場への説明、制度の導入、そして定着までのフォローアップと、膨大な工数を要します。
結果として、改革への意欲はあっても、「いつかやろう」と先延ばしにされ続けてしまうのです。

これらの障壁を乗り越え、本質的なマネジメント改革を最短距離で、かつ確実に実行するための一つの有効な手段が、組織マネジメントを専門とする外部コンサルティングの活用です。
改革を成功に導くための、強力な「推進力」と、経営者に寄り添う「伴走者」としての価値を提供します。
しがらみのない第三者の立場から、組織の課題を客観的に分析し、経営者が気づいていない問題点や、院内の人間関係からは言いにくい耳の痛い事実も直言します。
そして、経営者と共に改革のプランを練り上げ、現場の抵抗や反発も乗り越えながら、新しい仕組みが組織に定着するまで伴走し続ける。
経営者が一人で抱え込んでいた重荷を共に背負い、改革を断行するためのパートナーとなること。
これこそが、コンサルティングが提供する最大の価値です。
特に、病院という特殊な組織の改革を任せるパートナーは、慎重に見極める必要があります。
財務改善や増患マーケティングといった領域だけでなく、組織の根幹である人事マネジメントに深い知見と実績を持っているか。
そして何より、個人の経験則や精神論に頼るのではなく、どんな組織にも応用可能な、普遍的で再現性のある「マネジメントの型(理論)」を持っているか。
この2つの基準で、信頼できるパートナーを選ぶことが、改革の成否を大きく左右します。
それは、院長個人のリーダーシップやコミュニケーション能力といった、曖昧で属人的な「スキル」に依存するものではありません。
それは、院長のビジョンや指示が、組織の末端まで正確に、かつ自動的に伝達され、職員一人ひとりが自らの役割に基づいて自律的に行動することを可能にする、客観的で再現性のある「仕組み」そのものです。
院長の仕事は、日々発生する問題に追われ、火消しに奔走することではありません。
院長の真の仕事は、問題が発生しにくい、あるいは問題が発生しても組織が自律的に解決できる「仕組み」を設計し、構築し、そして維持し続けることです。
その仕組み作りにこそ、経営者としての貴重な時間とエネルギーを投下する。
その決断が、院長自身の負担を軽減し、職員の成長を促し、そして病院を持続的な成長軌道に乗せるための、最も確実で、最も価値ある一歩となるはずです。
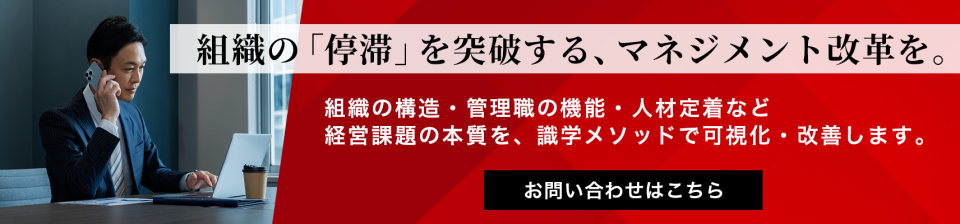
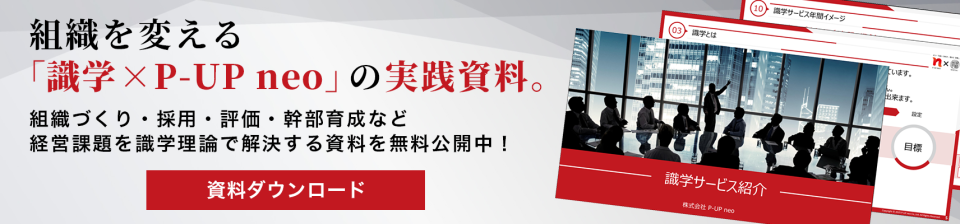

「なぜ、あれほど伝えたはずの指示が、現場の末端まで浸透しないのだろうか」
「部門間の連携が悪く、いつも同じような問題が繰り返されている」
日々の診療と並行して、組織の舵取りという重責を担う院長・経営者の皆様の中には、このような悩みを抱え、自身のマネジメント能力に限界を感じている方も少なくないのではないでしょうか。
多くの院長は、その卓越した臨床能力とリーダーシップで組織を牽引しようと奮闘します。
しかし、院長の情熱や「頑張り」だけでは、組織は動きません。
むしろ、院長が頑張れば頑張るほど、職員は指示待ちになり、組織の自律性は失われていくという皮肉な現実があります。
真の病院経営におけるマネジメントとは、院長個人のスキルやカリスマ性に依存するものではありません。
それは、院長の指示が自動的に現場の隅々まで浸透し、職員一人ひとりが自らの役割を理解して、組織の目標達成に向けて自律的に動くための「仕組み」を構築し、運用することに他なりません。
本記事では、多くの病院経営者が陥りがちなマネジメントの罠を解き明かし、院長の指示が浸透しない構造的な原因を分析します。
その上で、組織が自律的に動くための本質的な「仕組み」の作り方を、具体的なステップに沿って徹底的に解説していきます。
マネジメントが「院長個人の頑張り」に依存していませんか?
病院という組織は、院長ただ一人の力で動かせるほど単純なものではありません。医師、看護師、薬剤師、技師、事務職員といった、多種多様な専門性を持つ人材が集まり、それぞれが複雑に連携することで、初めて質の高い医療が提供されます。
この複雑な組織を、院長が日々の細かな業務にまで介入し、マイクロマネジメントしようとすれば、どうなるでしょうか。
院長自身の時間は瞬く間になくなり、本来注力すべき経営戦略の立案や、高度な診療といった、院長にしかできない重要な業務に時間を割けなくなります。
さらに深刻なのは、組織への影響です。
院長の指示がなければ何も決まらない、動けないという状況が常態化すれば、職員は次第に自分で考えることをやめ、「指示待ち」の状態に陥ります。
中間管理職は育たず、現場の主体性は失われ、組織全体の成長は完全に停滞してしまうでしょう。
もし、自院のマネジメントが「院長の頑張り」によって、かろうじて成り立っている状態であるならば、それは持続可能性の観点から極めて危険なシグナルです。
院長が体調を崩したり、退任したりした瞬間に、組織が崩壊するリスクを常に孕んでいるのです。
多くの病院経営者が陥る、3つのマネジメントの罠

「院長個人の頑張り」に依存する経営は、なぜ生まれてしまうのでしょうか。
そこには、多くの善良で有能な院長たちが、知らず知らずのうちにはまってしまう、3つの典型的なマネジメントの罠が存在します。
罠①:「カリスマ院長」のリーダーシップに依存してしまう
卓越した医療技術と、人を惹きつける人間的な魅力。こうした「カリスマ性」を持つ院長は、確かに組織を強力に牽引することができます。
職員は院長を尊敬し、その一言一句に耳を傾け、高いモチベーションで業務に取り組むでしょう。
しかし、このマネジメントスタイルは、諸刃の剣です。
組織の求心力が院長個人に集中しすぎると、職員は「院長のために」働くようになり、組織のルールや目標のために働くという意識が希薄になります。
院長の価値観が、組織の公式なルールよりも優先されてしまうのです。
また、院長の意向を忖度するあまり、健全な意見交換が行われなくなり、組織の意思決定に客観性が失われる危険性もあります。
そして何より、その院長がいなくなった後、組織は拠り所を失い、空中分解してしまうリスクを常に抱えることになります。
罠②:「プレイングマネージャー」から抜け出せず、本来の役割を果たせない
特に中小規模の病院やクリニックの院長に多く見られるのが、自身も一人のプレイヤーとして、日々の診療業務の最前線に立ち続ける「プレイングマネージャー」の罠です。名医であればあるほど、患者は院長を頼り、現場も院長の判断を求めます。
しかし、院長の本来の役割は、自らが最高のプレイヤーであり続けることではありません。
組織全体のパフォーマンスを最大化させる「最高の監督(マネージャー)」であることです。
プレイヤーとしての業務に時間を奪われ、マネジメント、すなわち「組織の仕組み作り」を怠れば、院長がいる間は現場が回っても、組織としての成長は望めません。
むしろ、院長が現場に介入しすぎることで、中間管理職の権限が侵され、指示命令系統が混乱し、組織全体の生産性を低下させているケースすら少なくないのです。
罠③:客観的な「事実」ではなく、主観的な「感情」で人を動かそうとする
「なぜ、私の思いが伝わらないんだ」「もっとプロ意識を持って仕事に取り組んでほしい」。業績が上がらない、あるいは組織に問題が発生した際、その原因を職員の「やる気」や「意識」といった、目に見えない感情的な要素に求めてしまう。
これもまた、多くのリーダーが陥る罠です。
「もっと頑張れ」という精神論や、「君ならできると信じている」といった期待の言葉は、一時的に職員を鼓舞する効果はあるかもしれません。
しかし、それによって組織が持続的に変わることはありません。
なぜなら、人の感情は移ろいやすく、客観的な基準がないため、マネジメントの拠り所としては極めて不安定だからです。
「頑張り」の基準は人それぞれであり、「信頼」という言葉だけでは、具体的に何をすべきかが伝わりません。
感情で人を動かそうとするマネジメントは、再現性がなく、組織に無用な「気遣い」や「忖度」といった、非生産的なコミュニケーションを生み出す温床となります。
なぜ、院長の指示は現場に浸透しないのか?その構造的な原因
「院長の指示が、現場の末端まで正しく伝わらない」。この問題は、院長の伝え方が悪いからでも、職員の理解力がないからでもありません。
その原因は、組織の「構造」そのものに潜んでいます。
原因①:指示が「曖昧」で、人によって解釈が変わってしまう
マネジメントにおけるすべての問題は、指示の「曖昧さ」から始まると言っても過言ではありません。院長が良かれと思って発した指示が、受け手によって全く異なる解釈をされ、期待とは違う結果を生んでしまう。
これは、病院組織において日常的に見られる光景です。
「いい感じにやっておいて」が引き起こす、現場の混乱と責任の所在の不明確化
例えば、院長が看護部長に「新人教育、いい感じにやっておいて」と指示したとします。院長がイメージする「いい感じ」とは、「3ヶ月後には、独り立ちして夜勤に入れるレベル」かもしれません。
しかし、看護部長は「まずは一年かけて、じっくり基礎を教えること」が「いい感じ」だと解釈するかもしれません。
この解釈のズレが、後になって「なぜ、まだ独り立ちできないんだ」「いや、今は基礎を固める時期です」といった、不毛な対立を生み出します。
さらに問題なのは、指示が曖昧であるために、結果に対する責任の所在も不明確になることです。
目標が未達に終わった際、「指示が曖昧だったからだ」「いや、受け手の解釈が間違っている」といった水掛け論に発展し、誰も責任を取らない、という事態を招きます。
原因②:職員一人ひとりの「役割」が明確に定義されていない
指示が正しく伝わらないもう一つの大きな原因は、そもそもその指示を受け取るべき「役割」が、組織内で明確に定義されていないことです。「それは私の仕事ではない」―セクショナリズムが生まれる温床
例えば、「退院支援を強化するように」という院長の指示が出されたとします。この時、看護部は「それはソーシャルワーカー(MSW)の仕事だ」と考え、MSWは「まずは主治医の退院許可がなければ動けない」と考え、リハビリ部門は「退院後の生活を見据えたリハビリ計画は、看護部からの情報提供があってこそだ」と考える。
このように、各部門が「自分の仕事の範囲はここまで」と線引きし、その範囲外の業務に対しては責任を負おうとしない。
これがセクショリナズムの正体です。
この問題の根源は、職員の協調性の欠如にあるのではありません。
「退院支援」という一つの目標を達成するために、それぞれの部門、それぞれの役職が、具体的に「何を」「どこまで」行う責任があるのか、その役割分担が組織のルールとして明確に定義されていないことに、構造的な原因があるのです。
原因③:「評価」と「日々の行動」が結びついていない
人は、自分が評価される行動を優先し、評価されない行動は後回しにする生き物です。院長の指示が現場で実行されない最大の理由は、その指示された行動が、職員自身の評価に直結していないからです。
何をすれば評価されるのかが不明確では、職員は動けない
院長が「これからは患者満足度の向上が最重要課題だ」と繰り返し訴えても、人事評価の基準が、依然として「業務の正確性」や「上司との協調性」といった項目だけであれば、職員は患者満足度を向上させるための具体的な行動(例えば、丁寧な説明や、親身な声かけなど)を、積極的に取ろうとはしないでしょう。なぜなら、それを頑張っても、自分の給与や昇進には直接影響しないからです。
院長のビジョンや指示は、それがいかに崇高なものであっても、職員一人ひとりの評価、そして処遇にまで落とし込まれ、連動していなければ、単なる「お題目」で終わってしまいます。
指示を浸透させるためには、その指示通りの行動が、職員にとって最も「得」である、という仕組みを作ることが不可欠なのです。
【本質】病院経営におけるマネジメントとは「仕組み」で組織を動かすこと
では、これらの構造的な問題を解決し、院長の指示が浸透し、組織が自律的に動く状態を実現するためには、どうすればよいのでしょうか。その答えは、マネジメントの捉え方を、院長個人の「スキル」や「リーダーシップ」といった属人的なものから、組織を動かすための客観的な「仕組み」へと、根本的に転換させることにあります。
脱・属人化。カリスマ院長がいなくても成長し続ける組織へ
真に強い組織とは、特定のカリスマリーダーがいなくても、組織として設定された目標に向かって、持続的に成長し続けられる組織です。そのためには、個人の能力や感情に依存するのではなく、誰もが同じように理解し、従うことができる、明確で公平な「仕組み」によって組織を運営する必要があります。
その仕組みとは、具体的には「明確な役割定義」「曖昧さを排除したルール」、そして「公平な評価制度」という、3つの柱から成り立っています。
この3つが有機的に連動することで、組織はまるで精密機械のように、機能的かつ自律的に動き始めるのです。
「ルール」が職員の行動の拠り所となり、迷いをなくす
組織における「ルール」は、職員を縛り付けるためのものではありません。むしろ、職員を日々の業務における「迷い」から解放し、本来の業務に集中させるための、強力な拠り所となるものです。
「この場合、誰に報告すればいいのだろうか」「どこまでが自分の権限で決定していいことなのだろうか」。
こうした迷いは、職員の思考を停止させ、業務の遅延や、責任のなすりつけ合いを生み出します。
報告・連絡・相談の経路、会議の運営方法、業務の承認プロセスといった、組織運営のあらゆる側面において、明確なルールが定められていれば、職員は迷うことなく、迅速かつ正確に行動することができます。
ルールは、組織の血流をスムーズにする、生命線なのです。
「評価制度」が院長のビジョンと現場の行動を一直線に結びつける
そして、組織という船を、院長が目指す目的地へと導くための、最も強力なエンジンとなるのが「人事評価制度」です。院長が掲げる経営ビジョンや年度目標を、部門目標、そして個人目標へとブレークダウンし、その達成度を評価の最も重要な基準とする。
そして、その評価結果が、昇給、賞与、昇進といった処遇に、明確なルールに基づいて反映される。
この仕組みを構築することで、職員一人ひとりの日々の行動が、組織全体の目標達成と一直線に結びつきます。
職員は、院長のビジョンを「自分事」として捉え、その実現に貢献することが、自らの評価を高める最善の道であると理解します。
評価制度とは、院長の思想を、組織の隅々にまで浸透させるための、最強のコミュニケーションツールなのです。
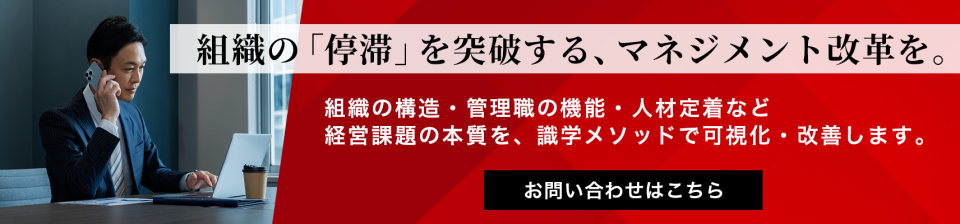
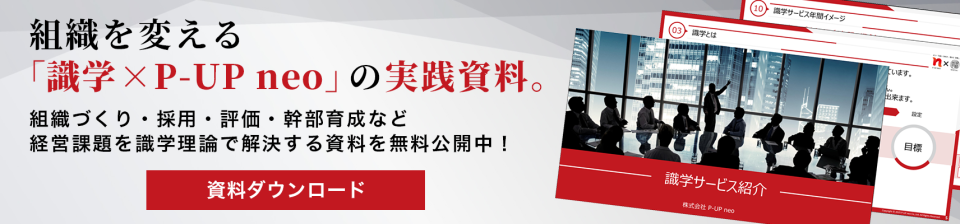
強い病院組織を作るための、マネジメント改革3つのステップ

「仕組み」によるマネジメントへの転換は、具体的にどのような手順で進めていけばよいのでしょうか。
ここでは、強い病院組織を作るための改革を、3つのステップに分けて解説します。
ステップ①:組織課題の可視化と「位置・役割」の完全定義
改革の第一歩は、現状を正しく認識することから始まります。まずは、組織図を基に、院内に存在するすべての「位置(役職)」を洗い出します。
そして、それぞれの役職について、「現在、誰が、どのような業務を行っているか」を客観的な事実として可視化します。
誰が、誰に、何を報告・相談・連絡するのか
次に、現在の指示命令系統(レポートライン)を明らかにします。本来であれば、各職員は直属の上司にのみ報告し、指示を仰ぐべきですが、実際には、院長が中間管理職を飛び越えて現場に指示を出したり、部門間で非公式な指示系統が生まれていたり、といった混乱が生じているケースが多くあります。
この「指揮命令の混乱」こそが、組織の生産性を著しく下げている元凶です。
まずは、この実態を正確に把握することが重要です。
各役職が担うべき「結果責任」の明確化
現状把握が終わったら、次にあるべき姿、すなわち、それぞれの「位置(役職)」が、本来担うべき「役割」と「結果責任」を、曖昧さを排除した具体的な言葉で再定義します。例えば、「看護部長」の役割は、「看護部全体の労務管理と、年度目標として設定された看護サービスの品質指標を達成することに、最終的な結果責任を負う」といった具合です。
この役割定義が、以降のすべての改革の土台となります。
ステップ②:曖昧さを排除した「ルール」の設定と徹底
役割が定義されたら、次に、その役割を果たすための具体的な行動基準となる「ルール」を設定していきます。なぜ院内のルールは守られないのか?
多くの病院には、既に就業規則や各種マニュアルといったルールが存在します。しかし、それらが守られていないとすれば、その原因は大きく二つ考えられます。
一つは、ルールの内容が「~するよう努める」「~を心がける」といった曖昧な表現で書かれており、人によって解釈の余地があること。
もう一つは、ルールを破った場合の結果が明確でないため、職員にとってルールを守る必然性がないことです。
ルール違反に対する結果責任を明確にする
新しいルールを設定する際は、「誰が」「何を」「いつまでに」「どのような状態で」行うべきかを、誰もが一意に解釈できる具体的な言葉で記述します。そして、最も重要なのが、そのルールが遵守されているかを、誰が、どのように監督するのか、そして、ルール違反があった場合には、どのような結果(例えば、人事評価へのマイナス反映など)が生じるのかを、あらかじめ明確に定めておくことです。
この結果責任の明確化があって初めて、ルールは組織内で実効性を持つものとなります。
ステップ③:「評価制度」の再構築と運用
改革の総仕上げとなるのが、人事評価制度の再構築です。新しい役割定義とルールに基づき、職員の行動を正しい方向へと導くための、強力なインセンティブ設計を行います。頑張りではなく「結果」を正しく評価する仕組み
日本の組織に根強く残る「頑張り」や「プロセス」を評価する文化は、客観性に欠け、職員の不満の温床となります。新しい評価制度では、個人の主観的な「頑張り」ではなく、ステップ①で定義した「役割」を、どれだけ果たせたか、その「結果」を客観的な事実に基づいて評価する仕組みを構築します。
評価項目を具体的な行動目標にまで落とし込む
評価項目は、「リーダーシップ」「協調性」といった曖昧なものではなく、「担当部門の目標達成率」「部下の時間外労働時間の削減率」「新規プロジェクトの計画達成度」など、可能な限り定量的、あるいは客観的な事実で測定できるものを設定します。そして、その評価項目を期初に上司と部下が合意の上で、具体的な行動目標にまで落とし込みます。
このプロセスを通じて、職員は、自らの評価を高めるためには、日々何をすべきかを明確に認識し、自律的に行動できるようになるのです。
なぜ、自院だけでのマネジメント改革は失敗しやすいのか?
これらの改革ステップは、理論上は明快ですが、いざ自院の力だけで実行しようとすると、多くの場合、途中で頓挫してしまいます。なぜなら、そこには内部からの改革を阻む、強力な3つの障壁が存在するからです。
長年の慣習や院内の人間関係が変革を阻む
「昔から、このやり方でやってきたんだ」「あの先生に反対されたら、何も進まない」。長年かけて形成された院内の人間関係や、特定の有力者への忖度、そして変化を嫌う組織の慣性は、新しい仕組みを導入する上で、想像以上に強力な抵抗勢力となります。
経営者自身も、その「しがらみ」の中で物事を進めなければならず、本来あるべき理想的な改革案が、院内の力学によって骨抜きにされてしまうケースが後を絶ちません。
客観的な視点の欠如により、本質的な課題を見誤る
「灯台下暗し」という言葉があるように、毎日同じ環境にいると、その組織のどこに問題があるのか、客観的に見ることが極めて難しくなります。内部の人間にとっては「当たり前」の光景、例えば、目的が曖昧なまま毎朝行われているカンファレンスや、責任者が不在のまま進められる会議などが、実は組織の生産性を著しく下げている根本原因である、という事実に気づくことができません。
この客観的な視点の欠如が、本質的な課題を見過ごし、対症療法に終始させてしまうのです。
経営者が日々の診療業務に追われ、改革に集中できない
特に中小規模の病院では、院長がプレイングマネージャーとして、日々の診療業務の中心を担っているケースがほとんどです。目の前の患者の対応に追われる中で、腰を据えて組織全体の仕組みを設計し、改革を推進していくための時間と精神的なエネルギーを確保することは、物理的に不可能です。
組織改革は、片手間でできるような簡単なものではありません。
現状分析、課題特定、解決策の立案、現場への説明、制度の導入、そして定着までのフォローアップと、膨大な工数を要します。
結果として、改革への意欲はあっても、「いつかやろう」と先延ばしにされ続けてしまうのです。
組織マネジメント改革を成功に導く、外部パートナーという選択肢

これらの障壁を乗り越え、本質的なマネジメント改革を最短距離で、かつ確実に実行するための一つの有効な手段が、組織マネジメントを専門とする外部コンサルティングの活用です。
組織コンサルティングが提供する本質的な価値とは?
優れたコンサルタントは、単なるアドバイザーではありません。改革を成功に導くための、強力な「推進力」と、経営者に寄り添う「伴走者」としての価値を提供します。
しがらみのない第三者の立場から、組織の課題を客観的に分析し、経営者が気づいていない問題点や、院内の人間関係からは言いにくい耳の痛い事実も直言します。
そして、経営者と共に改革のプランを練り上げ、現場の抵抗や反発も乗り越えながら、新しい仕組みが組織に定着するまで伴走し続ける。
経営者が一人で抱え込んでいた重荷を共に背負い、改革を断行するためのパートナーとなること。
これこそが、コンサルティングが提供する最大の価値です。
失敗しないコンサルティング会社の選び方
ただし、コンサルティング会社ならどこでも良いというわけではありません。特に、病院という特殊な組織の改革を任せるパートナーは、慎重に見極める必要があります。
財務改善や増患マーケティングといった領域だけでなく、組織の根幹である人事マネジメントに深い知見と実績を持っているか。
そして何より、個人の経験則や精神論に頼るのではなく、どんな組織にも応用可能な、普遍的で再現性のある「マネジメントの型(理論)」を持っているか。
この2つの基準で、信頼できるパートナーを選ぶことが、改革の成否を大きく左右します。
マネジメントとはスキルではない。構築すべき「仕組み」である
本記事を通じて、病院経営における真のマネジメントとは何か、その輪郭をご理解いただけたのではないでしょうか。それは、院長個人のリーダーシップやコミュニケーション能力といった、曖昧で属人的な「スキル」に依存するものではありません。
それは、院長のビジョンや指示が、組織の末端まで正確に、かつ自動的に伝達され、職員一人ひとりが自らの役割に基づいて自律的に行動することを可能にする、客観的で再現性のある「仕組み」そのものです。
院長の仕事は、日々発生する問題に追われ、火消しに奔走することではありません。
院長の真の仕事は、問題が発生しにくい、あるいは問題が発生しても組織が自律的に解決できる「仕組み」を設計し、構築し、そして維持し続けることです。
その仕組み作りにこそ、経営者としての貴重な時間とエネルギーを投下する。
その決断が、院長自身の負担を軽減し、職員の成長を促し、そして病院を持続的な成長軌道に乗せるための、最も確実で、最も価値ある一歩となるはずです。
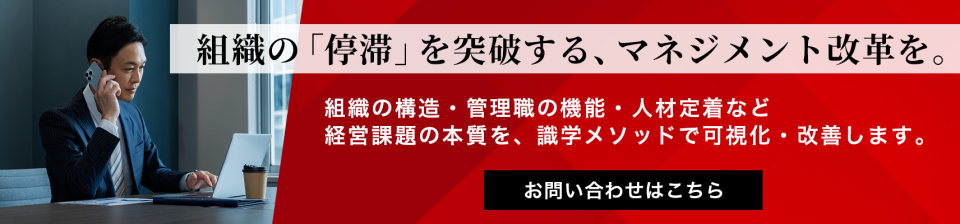
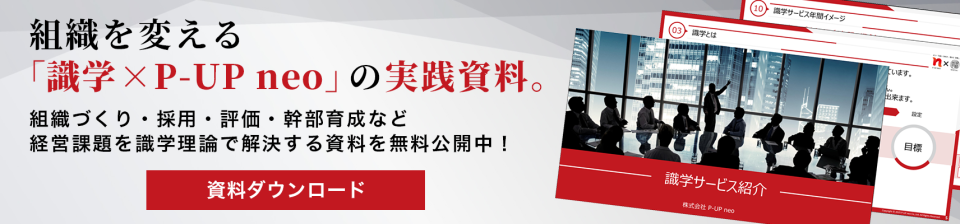
本気の組織改革なら
「識学 × P-UP neo」
この記事の監修者

有馬大悟 Arima Daigo
株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント
《資格》
識学認定コンサルタント
《プロフィール》
慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。
社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。
他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。
非営利法人における初年度更新率=満足度は100%