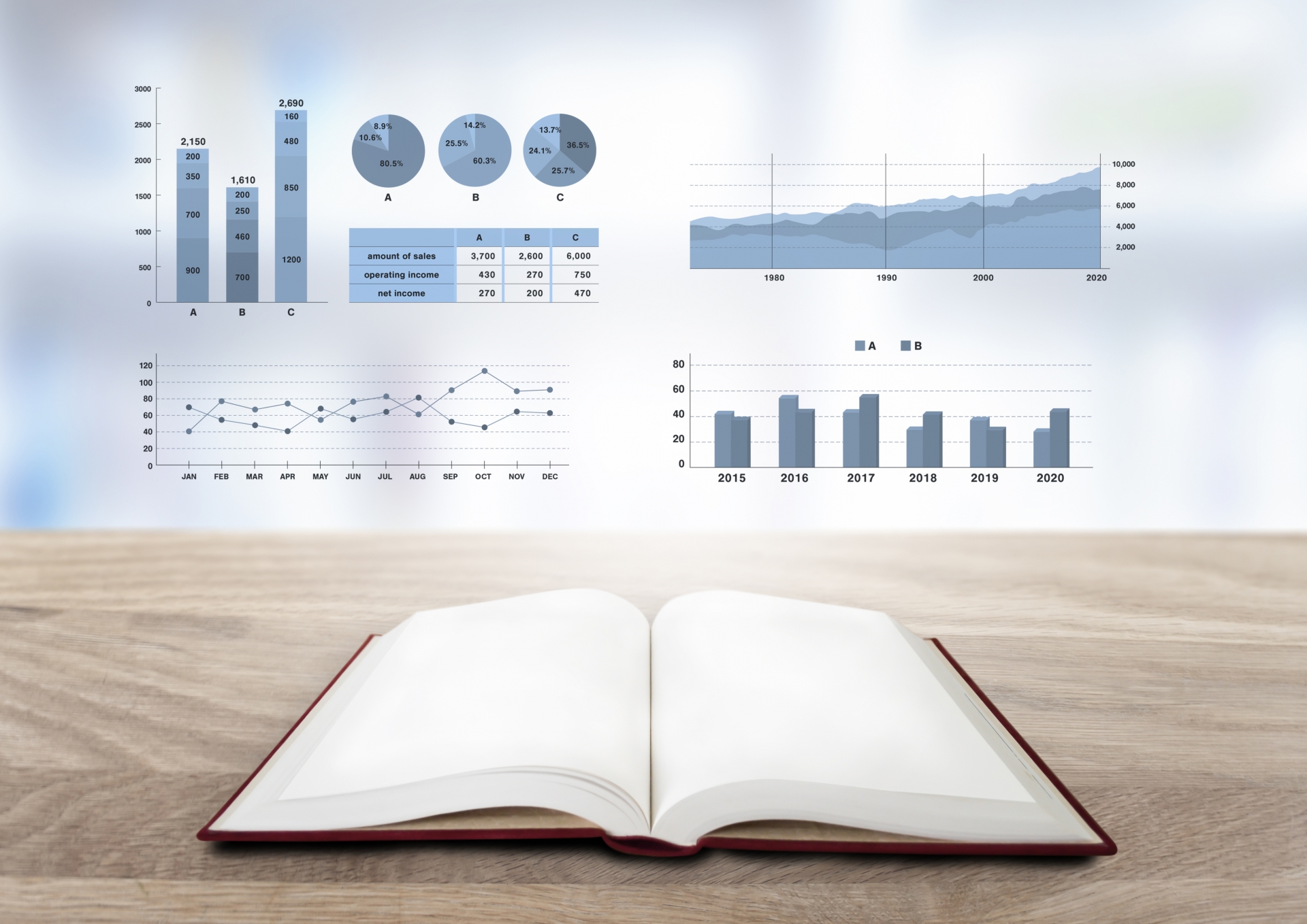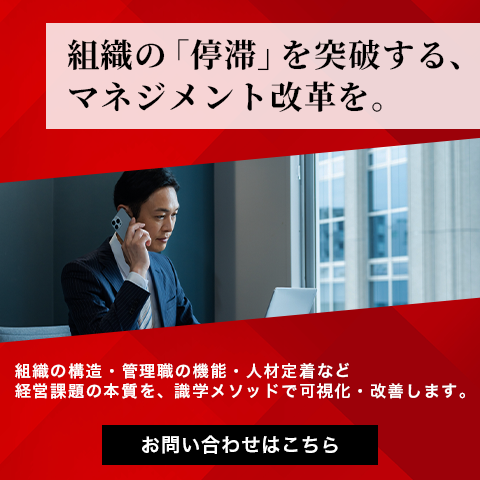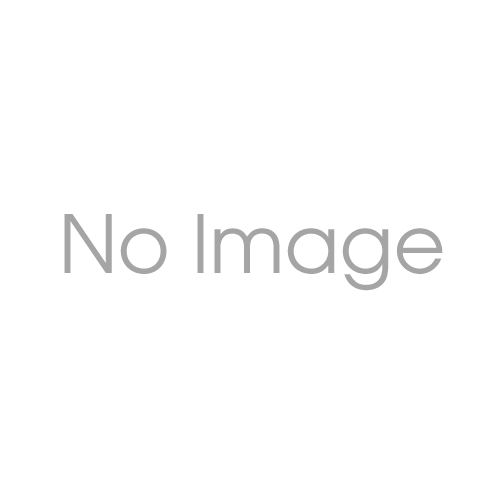
医療法人の経営者として、新任看護師長や事務長の育成に頭を悩ませていませんか?
優秀な医療スタッフが管理職になっても、マネジメントがうまくいかずに離職してしまうケースは少なくありません。
医療現場特有の課題を理解せずに一般的な研修を導入しても、期待した効果は得られないでしょう。
本記事では、医療法人における新任管理職研修の重要性から失敗しやすいポイント、成功に導くための具体的な流れを解説します。
自院に最適な新任管理職研修を構築するための、参考としてください。
本気の組織改革なら
「識学 × P-UP neo」
医療法人における新任管理職研修とは?

新任管理職研修とは、初めて管理業務に就く人材を対象に、必要な心構えやスキルを体系的に提供する教育プログラムです。
とくに専門職が多い医療法人において、管理職の育成は組織の将来を大きく左右します。
プレイヤーとして優秀な人材が、必ずしも優れたマネージャーになれるわけではないからです。
これまで個人の専門技術を磨いてきた職員が、今後はチーム全体の成果に責任を持つ立場へと変わります。
この大きな役割転換を円滑に進め、組織の理念を体現するリーダーを育てるために研修は欠かせません。
法人の成長基盤を築くための要となる投資といえます。
一般企業と医療法人の研修の違い
一般企業と医療法人の研修におけるもっとも大きな違いは、「使命」と「職員の特性」です。
利益追求が主目的となる一般企業に対し、医療法人は地域医療に貢献するという、公共性が高く重い使命を担っています。
そのため、管理職には高い倫理観と責任感が求められます。
また、医師や看護師といった高度な専門性を持つ職員をまとめるには、特殊な配慮をしなければなりません。
それぞれの専門性を尊重しつつ、チーム医療を促進する質の高い調整能力が不可欠です。
そのため、医療法人の現実に即した研修でなければ、実践的な効果は期待できないでしょう。
管理職研修は意味がないのか?機能不全がもたらす経営リスク

管理職研修を軽視する医療法人では、深刻な経営リスクが顕在化しています。
適切な研修を受けていない管理職はチームをまとめられず、組織全体のパフォーマンス低下を招くでしょう。
管理職の機能不全がもたらすおもなリスクを、以下3つに整理しました。
- チーム医療の質が低下する
- 優秀な人材が離職する
- 労務トラブルが発生する
それぞれ見ていきましょう。
チーム医療の質が低下する
管理職のマネジメント能力不足は、チーム医療の質の低下に直結します。
多職種が連携して1人の患者を支える医療現場では、管理職がその潤滑油とならなければなりません。
部門間の連携を促し、チーム全体に明確な方針を示す役割を担っているからです。
この機能が失われると、職員間の情報共有が滞り、円滑なコミュニケーションも失われます。
結果として、各職種がそれぞれの判断で動いてしまい、医療サービスの質にばらつきが生まれるでしょう。
チーム全体をまとめる管理職の育成こそが、質の高い医療提供の基盤となります。
優秀な人材が離職する
管理職が適切に機能しない職場では、優秀な人材ほど早く見切りをつけて離職する傾向があります。
自身の成長が感じられなかったり、正当な評価を受けられなかったりするためです。
部下のキャリアに寄り添い、働きがいのある環境を作ることも管理職の責務といえます。
とくに医療業界は人材獲得競争が激しいため、1人の離職が採用コストの増大や残された職員の負担増につながります。
管理職の育成は、採用活動以上に重要な人材定着のための施策です。
職員が安心して働き続けられる組織を作るうえで、管理職の役割は大きくなります。
労務トラブルが発生する
管理職の労務知識の欠如は、深刻な労務トラブルを引き起こす火種となります。
長時間労働やハラスメントといった問題は、管理職の不適切な言動やマネジメントが原因で発生する場合が少なくありません。
一度トラブルが発生すれば、法人の信頼が失墜するだけでなく、対応に多大な時間とコストを要します。
職員が心身ともに健康で働ける環境を維持するためには、管理職が労働法規やコンプライアンスを正しく理解しなければなりません。
適切な研修を通して管理職の労務管理能力を高めることは、組織を守るためのリスクマネジメントといえるでしょう。
新任管理職研修の目的

新任管理職研修は、単に知識を詰め込む場ではありません。
プレイヤーからマネージャーへの意識改革を促し、組織全体の成長につなげるための貴重な機会です。
明確な目的意識を持って実施することで、研修の効果を最大化できます。
ここでは、新任管理職研修における4つの目的を説明します。
- プレイヤー意識から脱却させる
- マネジメントスキルを習得させる
- 組織全体のパフォーマンスを高める
- スタッフの離職防止と定着を図る
これらの目的を達成することが、法人の持続的な発展につながります。
プレイヤー意識から脱却させる
研修の主要な目的は、プレイヤー意識からの脱却を促すことです。
個人の成果を追求する立場から、チーム全体の成果に責任を持つ立場へと意識を転換させます。
自身が手を動かすのではなく、部下に仕事を任せ、チームとして成果を出すことの重要性を理解してもらいます。
この意識改革がなければ、管理職はいつまでも1人の優秀なプレイヤーのままです。
部下を信頼して仕事を任せることができず、結果として自分だけが忙しくなり、チームは成長しません。
管理職としての自覚と覚悟を持たせることが、育成の第一歩です。
マネジメントスキルを習得させる
管理職として成果を出すために欠かせない、マネジメントスキルを体系的に習得させることも大きな目的です。
これまで自己流で対応してきた業務も、理論やフレームワークを学ぶことで、より効果的に実践できます。
たとえば、目標設定や進捗管理、部下との面談方法、会議の進め方などがあげられます。
これらの実践的なスキルは、チームの生産性を高めるうえで欠かせません。
経験則だけに頼るのではなく、再現性のあるスキルを身につけさせることで、管理職は自信を持ってリーダーシップを発揮できるでしょう。
組織全体のパフォーマンスを高める
新任管理職の育成は、最終的に組織全体のパフォーマンスを向上させるのが目的です。
管理職一人ひとりの能力が高まることで、その配下にあるチームの生産性が向上します。
そして、各チームの成果が積み重なることで、法人全体の業績向上につながります。
管理職は、経営層の示す方針を現場に浸透させ、実行部隊であるチームを動かす結節点です。
この結節点が円滑に機能することで、組織全体の意思決定が迅速になり、戦略の実行力も高まります。
管理職育成は、組織力を底上げするためのもっとも効果的な投資といえるでしょう。
スタッフの離職防止と定着を図る
部下が働きがいを感じられる環境を作り、離職を防止することも研修の大切な目的です。
職員の離職理由の上位には、常に「直属の上司との人間関係」があげられます。
つまり、管理職の言動や関わり方が、部下の定着率に大きな影響を与えるということです。
研修を通じて部下との信頼関係の築き方や、キャリア支援のあり方を学んでもらいます。
これにより、職員が安心して長く働ける職場環境の実現を目指します。
新たな人材の採用が困難な時代において、今いる職員の定着を図ることは、法人の安定経営に欠かせません。
新任管理職研修のおもな内容

新任管理職研修で扱う内容は多岐にわたりますが、管理職として早期に立ち上がるために欠かせない、核となるテーマが存在します。これらを体系的に学ぶことで、受講者は自身の役割と責任を深く理解し、実践に生かせるでしょう。
ここでは、多くの研修で共通して扱われる5つの主要な内容を紹介します。
- 管理職の役割認識
- 組織目標の設定と浸透
- 部下の指導と育成
- 人事評価とフィードバック
- 労務管理とコンプライアンス
これらは、管理職が身につけるべき基本的な土台となります。
管理職の役割認識
研修の導入部分では、管理職に求められる役割の理解を深めます。
プレイヤー時代との違いを明確にし、チームの成果に責任を持つ立場であることを自覚させるのが目的です。
自分が何を期待されているのかを正しく認識することから、管理職としての第一歩が始まります。
具体的には、経営理念の体現者としての役割や部門の目標達成責任、部下の育成責任などがあげられるでしょう。
これらの役割を理解することで、日々の業務における判断基準が明確になります。
自身の立ち位置を客観的に把握し、思考や行動を変えるきっかけを提供できます。
組織目標の設定と浸透
法人の経営目標を理解し、自部門の目標に落とし込むスキルを学びます。
設定した目標を、部下たちが納得できる形で伝え、チーム全体に浸透させる方法を習得することが有用です。
管理職には、なぜこの目標を追いかけるのか、その背景や意義を語る力が求められます。
目標が単なる数字のノルマとしてではなく、チーム共通の目指す姿として共有されることで、部下の主体的な行動が生まれます。
目標設定と浸透は、チームを1つの方向に導くための作業といえるでしょう。
部下の指導と育成
部下一人ひとりの能力や個性に合わせて、適切な指導や育成を行うためのスキルを学びます。
ティーチングとコーチングの違いを理解し、状況に応じて使い分ける方法を習得します。
具体的には、効果的な褒め方や叱り方、業務の任せ方や成長を促す質問の仕方など、実践的なコミュニケーション技術が中心です。
部下の成長は、チームの成果に直結するだけでなく、管理職自身の喜びにもつながります。
部下の可能性を最大限に引き出す関わり方を身につけることは、信頼されるリーダーになるための必須条件です。
人事評価とフィードバック
部下の人事評価を適切に行い、その結果を成長につなげるためのフィードバック面談の技術を学びます。
評価は部下の処遇を決めるだけでなく、育成のためのコミュニケーション手段です。
評価基準の正しい理解や、評価エラーを避けるための注意点を習得します。
また、部下の納得感を高め、次へのモチベーションを引き出すための面談の進め方も大切です。
客観的な事実に基づき期待を込めて伝えるフィードバックは、部下との信頼関係を深めるうえで大きな効果を発揮するでしょう。
労務管理とコンプライアンス
職員が安全かつ健康に働ける職場環境を維持するための、労務管理とコンプライアンスの知識を学びます。
労働時間管理やハラスメント防止、メンタルヘルス対策など、管理職として知っておくべき法律やルールを正しく理解することが目的です。
これらの知識は、意図せずして加害者になることを防ぎ、職員と組織を守るために欠かせません。
労務リスクを未然に防ぎ、すべての職員が安心して働ける職場を作ることは、管理職の責務の1つです。
法令遵守の意識を高め、適切な対応が取れるように備えます。
医療法人が新任管理職研修で陥りやすい失敗と対策
医療法人が新任管理職研修を実施する際には、特有の理由から失敗に陥りやすいケースがいくつか存在します。
ここでは、研修で陥りがちな6つの失敗例とその対策を解説します。
- 一般企業向け研修をそのまま導入してしまう
- 目的が曖昧なまま研修を始めてしまう
- 自院の課題と研修内容が一致しない
- 外部業者に丸投げで当事者意識がない
- 事後フォローがなく行動が変わらない
- 経営層の期待と現場ニーズがずれている
これらの失敗パターンを事前に知ることで、同じ轍を踏むリスクを減らせます。
一般企業向け研修をそのまま導入してしまう
よくある失敗の1つが、一般企業向けの研修プログラムをそのまま導入してしまうことです。
医療現場の特殊性を考慮していないため、内容が抽象的すぎたり、実務とかけ離れていたりして、受講者の共感を得られません。
対策として、医療業界に特化した研修会社を選定するか、カスタマイズを依頼することが賢明です。
医師や看護師といった専門職のマネジメントや、チーム医療の推進といった、医療法人ならではの課題を盛り込む必要があります。
目的が曖昧なまま研修を始めてしまう
「他院もやっているから」といった理由で、研修の目的を明確にしないまま始めてしまうケースも失敗につながります。
目的が曖昧だと研修内容の選定基準がぶれてしまい、受講者にも研修の意図が伝わりません。
対策は、研修を通じて管理職に「どうなってほしいのか」というゴールを具体的に設定することです。
たとえば「部下の主体性を引き出せるようになってほしい」など、具体的な行動で定義します。
明確な目的を経営層と現場で共有することが、研修を成功させるための第一歩です。
自院の課題と研修内容が一致しない
研修内容が、自院が本当に抱えている課題とずれている場合、効果は期待できません。
たとえば、コミュニケーション不足が課題なのに、労務管理の知識ばかりを教えても、現場の問題は解決しないでしょう。
この失敗を避けるためには、研修を企画する前に、現場の管理職や職員へのヒアリングを行い、組織の課題を正確に把握しなければなりません。
そのうえで、課題解決に直結する内容を研修プログラムに組み込みます。
現状分析に基づいた研修設計が、投資対効果を高めることにつながります。
外部業者に丸投げで当事者意識がない
研修の企画から運営までを外部業者に丸投げし、人事部や経営層が関与しないケースもよくある失敗です。
これでは、研修が他人事になってしまい、法人としての本気度が受講者に伝わりません。
対策として、経営者自らが研修の冒頭で期待を伝えたり、人事担当者が運営に積極的に関わったりすることが有効です。
法人全体で新任管理職の成長を支援しているという姿勢を示すことで、受講者の学習意欲も高まります。
研修は業者に委託するものではなく、自院が主体となって進めるプロジェクトと認識することが大切です。
事後フォローがなく行動が変わらない
研修で学んだことを、現場で実践するためのフォローアップがなければ、内容はすぐに忘れ去られてしまいます。
「研修中はやる気になったが、日常業務に戻ると元どおり」というのは、もっとも避けたい失敗パターンです。
研修後には、上司との面談で実践計画を立てたり、数ヶ月後にフォローアップ研修を実施したりするなど、継続的な支援が欠かせません。
研修は単発のイベントではなく、育成プロセスの一部と捉えるべきです。
学んだことを行動に移し、定着させるための仕組みで設計することが、研修の成果を確実なものにします。
経営層の期待と現場のニーズがずれている
経営層が管理職に期待する役割と、管理職自身が現場で感じている課題や必要なスキルにずれがある場合、研修は空回りします。
経営層の理想論だけを押し付けても、現場の実態に合わないため、受講者は反発を感じてしまうでしょう。
このミスマッチを防ぐには、研修企画の段階で、経営層と新任管理職の双方から意見を聞く機会を設けることが効果的です。
トップダウンの期待と、ボトムアップのニーズをすり合わせ、両者が納得できる研修目標と内容を設定します。
この方法自体が、組織内の相互理解を深めるよい機会にもなります。
新任管理職研修を成功に導くための流れとポイント
新任管理職研修を成功させるには、思いつきで進めるのではなく、戦略的な計画と実行が不可欠です。研修の企画から効果測定までを一連の流れとして捉え、各段階で適切なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、研修を成功に導くための5つのポイントを解説します。
- 誰をどう育てるかを定義する
- 自院だけの最適な研修を作る
- 外部委託先を選定する
- 研修効果を最大化する
- 効果を測定し改善する
詳しく見ていきましょう。
誰をどう育てるかを定義する
研修計画の最初のステップは、育成のゴールを明確に定義することです。
誰を対象に、どのような能力を伸ばし、最終的にどうなってほしいのかという方向性が定まらなければ、効果的な研修は設計できません。
まずは育成の全体像を描くことが重要です。
研修の土台となるゴール設計について、以下3つの観点から紹介します。
- 理想の管理職像を明確にする
- 職種ごとの役割への期待を整理する
- 研修の成果指標を設定する
これらを事前に定義することで、研修の軸が定まり、関係者間の認識のズレを防げます。
理想の管理職像を明確にする
研修の出発点は、自院が求める理想の管理職像を具体的に描くことです。
法人の理念やビジョンに基づき、どのようなリーダーシップを発揮してほしいのかを言語化します。
これが研修内容や評価基準すべての土台となるからです。
たとえば「部下の声に耳を傾け、主体性を引き出すリーダー」といった人物像を明確にします。
経営層で議論を重ねて共通認識を持つことで、育成の方向性がブレなくなります。
職種ごとの役割への期待を整理する
理想の管理職像を土台としながら、職種ごとの特性を踏まえた役割と期待を整理します。
医師や看護師長、技師長や事務部門の管理職では、求められるマネジメントの形が異なるためです。
それぞれの専門性や業務内容に合わせた育成目標を設定することが有用です。
たとえば、看護師長にはチームの結束力を高める調整能力が、事務管理職には業務効率化を推進する企画力がとくに求められるかもしれません。
このように役割を具体化することで、より実践的な研修内容を検討できます。
研修の成果指標を設定する
研修の成果を客観的に測るための指標、いわゆるKPIを設定します。
研修が「やりっぱなし」で終わるのを防ぎ、投資対効果を検証するために不可欠なプロセスです。
何を達成すれば研修が成功したといえるのかを、事前に定義しておく必要があります。
たとえば「受講者の研修後アンケートの満足度」といった短期的な指標だけではありません。
「部下のエンゲージメントスコアの向上」や「担当部門の離職率の低下」など、中長期的な組織の変化を指標とすることも有効です。
>>関連記事はこちら「病院経営を改革するKPI設定方法とは?メリットや手順について解説」
自院だけの最適な研修を作る
育成のゴールが定まったら、次はそのゴールを達成するための研修プログラムを具体的に作成します。
市販のパッケージ研修をそのまま使うのではなく、自院の状況に合わせて内容を最適化することが、研修効果を高めるうえで効果的です。
ここでは、自院に最適な研修プログラムを作成するための2つの要点を見ていきましょう。
- 自院の課題に合わせて内容を設計する
- チーム医療を機能させる要素を組み込む
これらの視点を持つことで、研修はより実践的で意味のあるものになります。
自院の課題に合わせて内容を設計する
研修プログラムは、自院が抱える組織の課題を解決するために設計します。
事前に実施したヒアリングやアンケートの結果に基づき、課題の優先順位をつけ、それに応じた内容を盛り込むことが大切です。
たとえば、若手職員の離職が課題であれば、部下とのコミュニケーションや育成に関する内容を手厚くします。
残業時間の多さが課題であれば、業務効率化やタイムマネジメントの比重を大きくするなどです。
このように課題解決志向で設計することで、研修は現場にとって価値の高いものとなり、受講者の納得感も高まります。
チーム医療を機能させる要素を組み込む
医療法人ならではの視点として、チーム医療を円滑に機能させるための要素を研修に組み込むことが大切です。
管理職には自部門だけでなく、他職種と効果的に連携し、組織全体の成果を最大化する役割が求められます。
具体的には、他職種への理解を深めるためのワークショップや、部門間の連携をテーマにした事例研究などが有効です。
職種間の壁を取り払い、円滑なコミュニケーションを促進するハブとしての役割を自覚させます。
これにより、患者へ提供する医療の質を、組織全体で高めていく意識へとつながります。
外部委託先を選定する
質の高い研修を実施するには、信頼できる外部委託先の選定が大切です。数多くの研修会社やコンサルティング会社の中から、自院の理念や課題に真に寄り添ってくれるパートナーを見極めなければなりません。
ここでは、後悔しない外部委託先を選定するための2つのポイントを解説します。
- 本質的な課題解決力を見極める
- 費用対効果を具体的に確認する
それぞれ見ていきましょう。
本質的な課題解決力を見極める
委託先選びでは、表面的な研修プログラムだけでなく、その裏側にある課題解決力を見極めなければなりません。
単に知識を提供するだけでなく、自院の本質的な課題を深く理解し、解決に導く提案をしてくれるかどうかが判断基準となります。
そのためには、過去の実績、とくに医療業界での支援実績を確認することが有効です。
担当コンサルタントとの面談を通じて、課題認識の深さや解決への熱意を感じ取ります。
研修という手段の提供だけでなく、組織の未来を共に考えてくれる委託先こそが、真に選ぶべき相手といえるでしょう。
費用対効果を具体的に確認する
研修費用が、その投資に見合う効果を生むのかを具体的に確認することも大切です。
単に見積金額の安さだけで判断するのではなく、どのような成果が期待できるのか、その根拠までを詳しく確認する姿勢が求められます。
たとえば、研修後のフォローアップ体制や、効果測定への協力の有無も判断材料です。
費用の中にどこまでのサービスが含まれているのかを明確にします。
複数の業者から提案を受け、費用と提供価値を比較検討することで、もっとも費用対効果の高い委託先を選定できます。
研修効果を最大化する
研修プログラムと委託先が決まったら、次はその効果を最大限に引き出すための環境を整えます。
研修は受講者本人だけの努力で成功するものではありません。
組織全体で研修を支援し、学びを実践につなげるための仕かけ作りが不可欠です。
ここでは、研修効果を最大化するための3つの取り組みを紹介します。
- 経営者自ら研修の重要性を伝える
- 現場の上司を巻き込み実践を支援する
- 人事評価制度と連動させ行動を促す
これらの取り組みが、研修の成果を大きく左右します。
経営者自ら研修の重要性を伝える
研修の冒頭や節目で、経営者自らが受講者に向けてメッセージを伝えることは効果的です。
なぜこの研修を実施するのか、そして受講者に何を期待しているのかを、経営者の言葉で直接語りかけます。
これにより、受講者は法人としての本気度を感じ取り、研修に対する意識が高まります。
「やらされ感」が払拭され、主体的な学習意欲が引き出されるでしょう。
経営者の期待を直接聞くことは、新任管理職にとって大きなモチベーションとなり、研修への集中力を高める効果があります。
現場の上司を巻き込み実践を支援する
研修で学んだことを現場で生かすためには、新任管理職の上司、つまり経営層やさらに上の役職者の協力が欠かせません。
研修内容を上司と共有し、受講者が実践しようとすることを積極的に支援する体制を築きます。
たとえば、研修後に受講者と上司が面談し、研修での学びに基づいた行動目標を設定。
上司は日々の業務の中で、その目標達成に向けたフィードバックやサポートを行います。
このように上司が伴走者となることで、研修での学びは一過性のものでなく、現場に根付いた行動へと変わっていきます。
人事評価制度と連動させ行動を促す
研修で学んだ行動やスキルを、人事評価の項目に組み込むことも有効な手段です。
研修で求められる理想の管理職像と、評価される管理職像を一致させることで、行動変容への動機づけをより強力にできます。
たとえば、研修で「部下の育成」について学んだのであれば、評価項目にも「部下育成への貢献度」といった内容を設けます。
研修での学びが、自身の評価に直接つながることを示すことで、受講者はより真剣に実践に取り組むようになるでしょう。
研修と人事制度を連動させることは、組織が求める行動を文化として定着させるための戦略的な一手です。
効果を測定し改善する
研修を実施したあとは、その効果を客観的に測定し、次年度以降の改善につなげるプロセスが有用です。研修は一度実施して終わりではなく、継続的に改善を重ねていくことで、その質を高められます。
ここでは、研修の効果測定と改善のための2つを説明します。
- 受講者の行動変化を具体的に把握する
- 次年度に向けて研修内容を改善する
詳しく見ていきましょう。
受講者の行動変化を具体的に把握する
研修の効果は、受講者の満足度アンケートだけで測るべきではありません。
肝心なのは、研修後に受講者の「行動」がどう変わったかを具体的に把握することです。
そのために、研修から数ヶ月後に本人やその上司、部下に対して多面的なヒアリングやアンケートを実施します。
たとえば「部下への声かけが増えた」「会議の進め方が建設的になった」など、具体的な行動の変化を収集します。
これらの定性的な情報こそが、研修の真の効果を示す貴重なデータとなり、今後の育成方針を考えるうえでの示唆を与えてくれます。
次年度に向けて研修内容を改善する
効果測定によって得られたデータや意見をもとに、次年度の研修プログラムを見直し、改善します。
効果が高かった内容は継続・強化し、あまり効果が見られなかった内容は見直すか、別の内容に差し替えるといった判断を行いましょう。
たとえば「もっと実践的なケーススタディを増やしてほしい」という意見が多ければ、次年度は演習の時間を増やすといった改善が考えられます。
このように、PDCAサイクルを回し続けることで、研修プログラムは年々洗練されていきます。
まとめ:新任管理職研修を通じた成長が医療法人の未来を創る
新任管理職の育成は、法人全体の成長に不可欠です。
しかし、研修だけで組織の課題がすべて解決するわけではありません。
より根本的なマネジメントの仕組みを見直すことが、持続的な成長へとつながります。
もし「管理職が機能しない」「従業員の離職が絶えない」といった課題にお悩みなら、P-UP neoにおまかせください。
意識構造に着目したマネジメント理論「識学」と、自らも組織改革を成功させた実践的なノウハウを組み合わせ、貴院の課題解決を支援します。
まずは、サービスが詳しく分かる資料のダウンロードや、無料セミナーから始めてみませんか?
マネジメントの正解を知りたい方は、ぜひお気軽にご相談ください。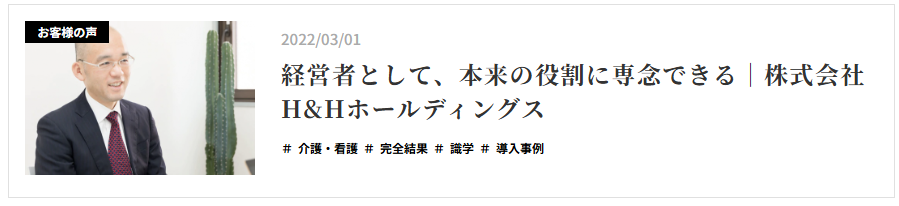
本気の組織改革なら この記事の監修者 有馬大悟 Arima Daigo 株式会社P-UP neo 事業開発室 室長 識学上席コンサルタント 《資格》 識学認定コンサルタント 《プロフィール》 慶応大学卒業後、塾講師、TV局AD、家庭教師を経て2012年にP-UPに入社。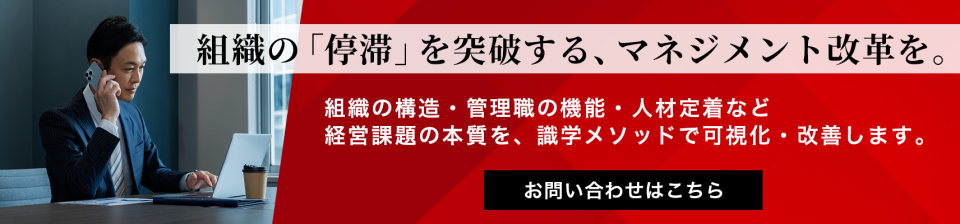
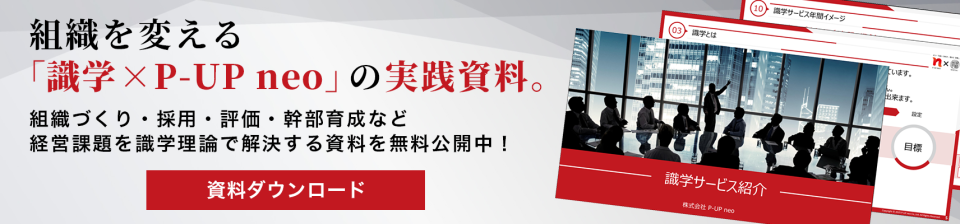
「識学 × P-UP neo」
社会インフラである医療、介護福祉、学校法人から海外医療法人の制度設計~管理職育成~新人採用の仕組みを構築し、組織成長に貢献。
他言語、異文化制度設計、管理手法の確立を実践し組織成長を実現可能です。
非営利法人における初年度更新率=満足度は100%